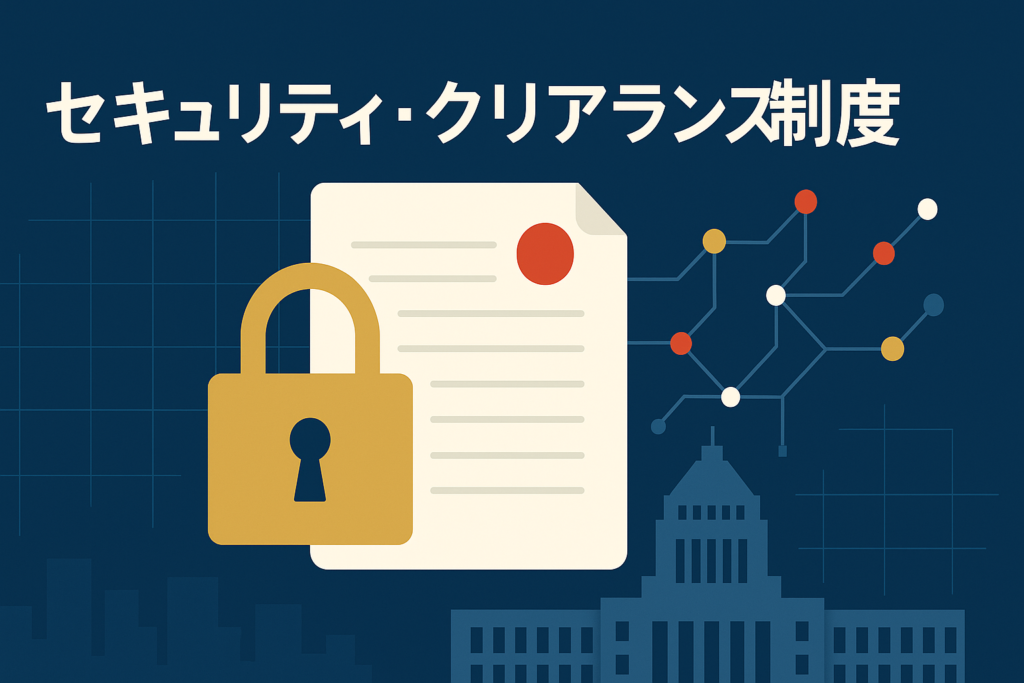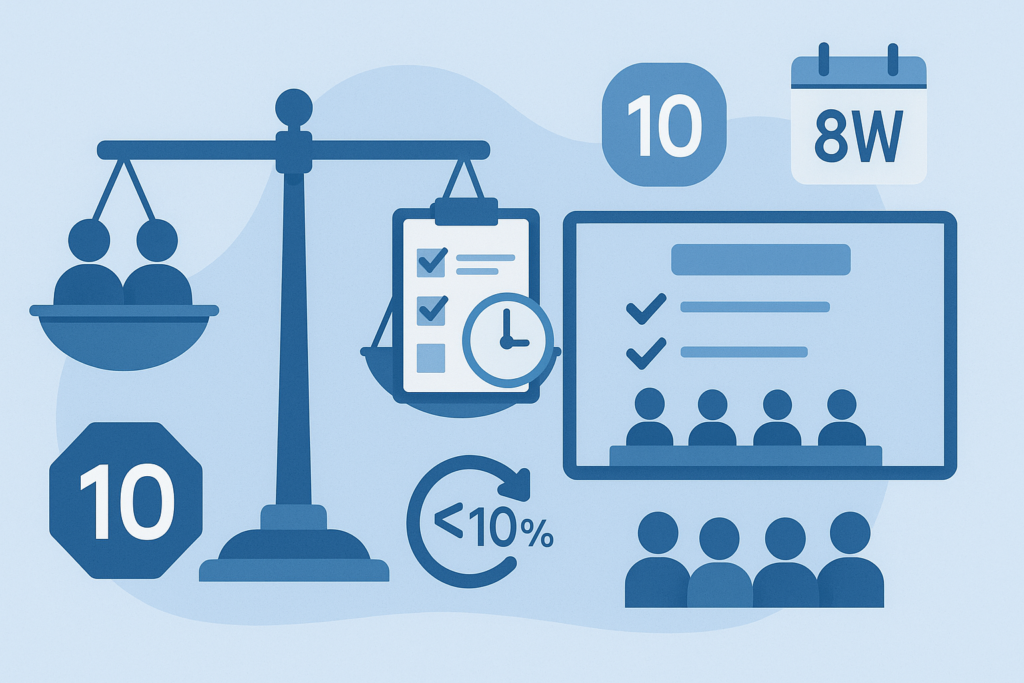はじめに
2020年6月、公益通報者保護法が改正されたことにより、一定規模の事業者(常時使用する従業員数が300人を超える事業者)において内部通報制度の整備が義務付けられました。
実際に、内部告発をきっかけに不祥事が明らかになるケースも少なくないため、内部通報制度は極めて重要な意義をもつ制度です。
このたび、政府は、通報者の保護を強化するための指針をまとめ、通報者に降格や減給といった処分を行った場合には、処分を行った役員などを懲戒処分にするよう企業に求めていくとしています。
通報者保護を含む内部通報の運用策については、8月中に消費者庁により告示される予定です。
今回は、「内部通報制度」について、その全体像をわかりやすく解説します。
1 内部通報制度とは
「内部通報制度」とは、企業内の不正行為などに係る情報を早期に取得し、問題点を把握するとともに、その早期是正を図る仕組みのことをいいます。
一般的に、日々の業務で発生する報告事項については、上司を通じてその報告が行われます。
ですが、不正行為に係る情報を報告事項とする場合に、このやり方を徹底してしまうと、報告を受ける側が不正に関与しているような場合に、不正行為を隠蔽されたり揉み消されたりする可能性があります。
内部通報制度は、このようなことがないように別の報告ルートを設けることで、不正発見に繋げるための制度であり、自浄作用としての役割を期待されているのです。
2 内部通報制度を導入するメリット
内部通報制度を導入するメリットは、主に、以下の3点です。
- 不正行為の予防
- 不正行為の早期発見
- 信頼性の獲得
(1)不正行為の予防
企業内で内部通報制度が整備されていれば、従業員等は不正行為などを行った場合には自分が通報されるという意識をもつようになります。
これにより、不正行為を未然に予防する効果を期待することができます。
(2)不正行為の早期発見
内部通報制度は、不正行為の早期発見に資するものです。
不正行為を早期に発見できれば、早期是正により、被害の拡大を防ぐことができます。
(3)信頼性の獲得
取引を行う際に、その相手方において内部通報制度が整備されているかどうかを考慮する事業者が増えています。
これは、不正行為が発生することは避けられないとしたうえで、相手方に自浄能力を求めている表れだといえます。
内部通報制度が整備され、適切に運用されていれば、取引先から信頼性を獲得することができ、ひいては、社会的な評価を高めることにも繋がります。
3 内部通報制度を導入する際の3つのポイント
内部通報制度を導入する際のポイントは、以下の3点です。
- 通報者の保護
- 独立した通報窓口の設置
- 不利益を受けないことの明確化
(1)通報者の保護
通報したことを理由に会社から不利益な扱いを受けるのであれば、誰もこの制度を利用しないでしょう。
内部通報制度がきちんと機能するためには、通報者の利益が守られていなければなりません。
そのため、事業者には、以下のような対応が求められます。
①通報者の特定につながる情報の取扱い
通報者の特定につながる情報が不当に拡散されないよう、情報の共有範囲を規程などで明確にしておく必要があります。
また、通報者を特定しようとする行為を防止するために必要な措置を事前に講じておくことも必要です。
さらに、社内教育を実施するなどして、これらの行為が行われた場合は懲戒処分等の対象となることを周知することが必要です。
②通報窓口の環境整備
通報を受けて、調査を実施する際には、その対象者が通報者を推測することができないよう、通報があった事実についても伏せておく必要があります。
その意味で、通報窓口の環境は極めて重要な要素となります。
電話で通報が入った場合に、そのやり取りが周囲に漏れていたり、通報を受け付ける際の面談において、窓口担当者以外にも誰が面談に来ているかがわかったりするような環境では、到底通報があった事実を秘匿することはできません。
そのため、通報があった事実が外部からわからないように、通報窓口の環境を整備する必要があります。
(2)独立した通報窓口の設置
一般的に、通報窓口は社内に設置されることが多いといえますが、企業における不正行為は、経営陣などの上層部が関与して行われることが少なくありません。
そのため、通報窓口は経営陣から完全に独立していることが望ましいといえます。
たとえば、社外の法律事務所に通報窓口としての役割を担ってもらい、社内に設置する通報窓口と併用することが考えられます。
(3)不利益を受けないことの明確化
通報者が通報時にもっとも気にすることは、通報後に会社から不利益な扱いを受けないかということです。
そのため、事業者においては、通報者に対して不利益な取扱いをしてはならないということを規程などで明記しておく必要があります。
また、通報者が不利益な取扱いを受けていないかどうかを把握するための措置や不利益な取扱いを受けていることが判明した場合の救済措置、不利益な取扱いを行った役員等に対する懲戒処分等の措置などについても、社内できちんと構築しておくことが必要です。
4 まとめ
企業による不祥事が後を絶たない現代において、内部通報制度は極めて重要な意義をもつ制度です。
自浄能力や信頼性の向上に資する制度でもあるため、事業者においては、機能性のある内部通報制度を構築することが大切です。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。