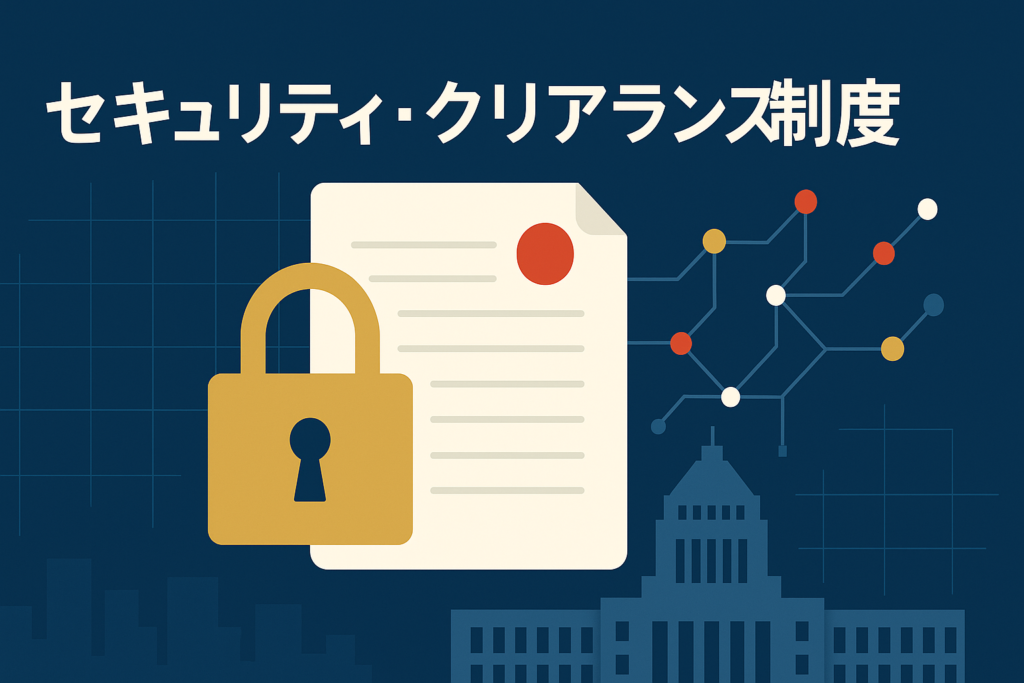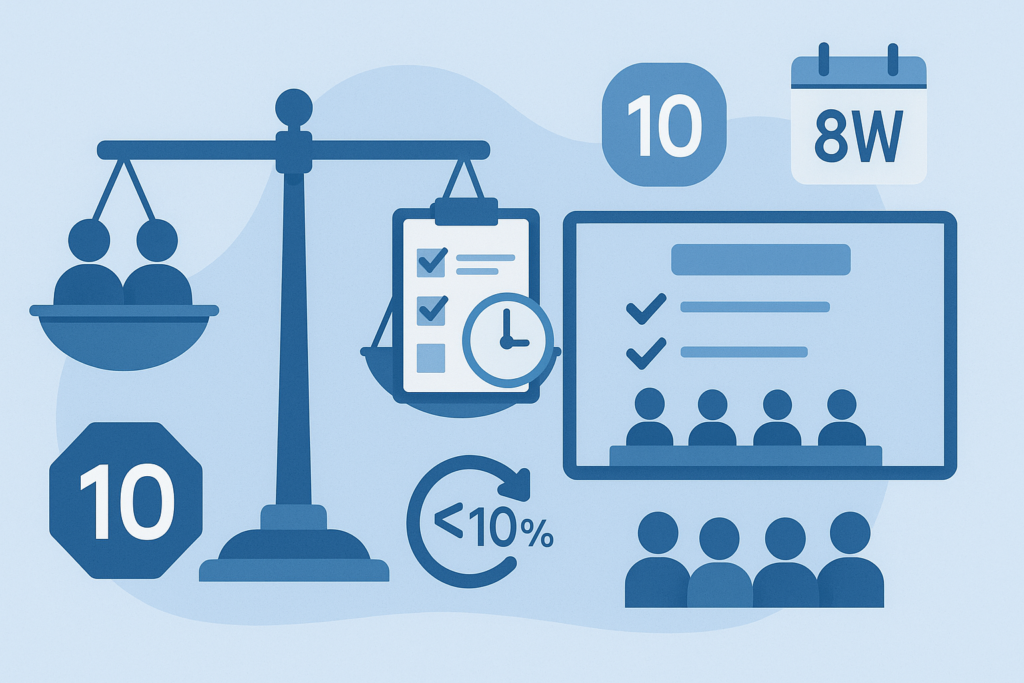契約交渉の代理人に弁護士以外は認められるべきか?
弁護士法第72条は、弁護士以外が法律事務を行うことを禁止しています。この法律は、報酬を得る目的で訴訟事件や法律事務を扱うことを、弁護士のみの独占業務としています。しかし、契約交渉や契約書作成はどこまで弁護士の独占業務に含まれるのか、その解釈が揺れています。
きっかけとなったのは、プロ野球選手の契約交渉に関する最近のニュースです。
プロ野球選手が球団との契約交渉を行う際の代理人に弁護士以外は認めないなどとするルールは、独占禁止法に違反するおそれがあるとして、公正取引委員会は12球団などで構成される団体に対し警告を出しました。
プロ野球選手の代理人 弁護士限定は独禁法違反のおそれ 公取委
この公正取引委員会の警告は、「プロ野球選手が球団との契約交渉を行う際の代理人」を「弁護士に限定する」のは独占禁止法違反のおそれがある、と言っていますが、そもそも契約交渉は弁護士にしかできない業務なのではないかという疑問があります。
ちなみに、この件について、公正取引委員会の見解は弁護士法上問題があるという趣旨の弁護士側(日弁連や各単位会)の声明は出ていません。
タレントビジネスやスポーツビジネスにおけるマネジメント会社やエージェント会社は多くあり、この件に関する弁護士法第72条の解釈もはっきりしているとは言えません。
そもそもマネジメント会社やエージェント会社がやっている契約交渉は全て違法である、と宣言して、それが認められなかった場合の波及効果が大きすぎることも影響しているのかも知れません。
この記事では、弁護士資格がないエージェント会社やコンサルティング会社が他人の契約交渉を代行することの法的な是非について考察します。
エージェント会社とマネジメント会社の違い
2024年9月、公正取引委員会がプロ野球12球団で構成される「日本プロフェッショナル野球組織」に対し、選手の代理人を弁護士に限定するルールは独占禁止法違反の可能性があると警告を出しました。このルールは2000年に導入されたもので、選手が弁護士以外の代理人を契約交渉に利用することを制限していました。
これにより、選手は日本の弁護士資格を持たない海外の代理人を選べないなど、選択肢が制限されていたことが問題視されています。実際、選手会はこのルールに対し以前から改善を求めていました。
ところで、エージェントとマネージメントというのはどう違うのでしょうか。
一般的に、エージェント契約は、クライアントの代理人(エージェント)が特定の業務、特に商取引や契約交渉などをクライアントに代わって行う契約です。これに対し、マネージメント契約は、クライアントの日常的な業務やキャリア全般に対する支援や管理を行う契約です。
主な違いとしては、エージェント契約は特定の契約や取引に関する代理業務が中心なのに対し、マネージメント契約はクライアントのキャリア全般にわたる支援や戦略的管理が中心です。
エンターテインメント業界やスポーツ界では、タレントや選手のキャリアやブランド構築を目的として用いられます。マネージャーはクライアントの日常的な活動の計画、調整、プロモーションなど広範囲にわたる業務を管理します。
業務の内容は類似する部分もありますが、一般的には、エージェントは個別的、単発的なタスクを取扱い、マネジメントは長期的、総合的なタスクを取り扱うという点に違いがあります。
弁護士以外が契約交渉を行うことの法的問題
ここで焦点となるのが、弁護士法第72条です。弁護士法は弁護士以外が報酬を得る目的で「法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務」を取り扱うことを禁止しています。では、契約交渉や契約書の作成は「法律事務」に該当するのでしょうか?
契約交渉や契約書締結の代行、日常的な意味では法律に関係する仕事で「法律事務」に含まれると言えそうですが、条文上、法律事務は「法律事件に関して」行うこととされています。この点に関しては、事件性必要説と、事件性不要説の対立があります。
事件性必要説は、法的紛争が具体化、顕在化している必要があるという考え方です。例えば、交通事故で、被害者が治療費の請求をしているのに加害者が払わない、という状況はまさに法的紛争が具体化しています。この場合は事件性があるので、被害者か加害者の代理で和解契約書を作成することは典型的な「法律事務」に該当してきます。
他方、離婚をする際に当事者に離婚をすることや養育費の支払いなどについて全く争いがない場合は、法的紛争が具体化、顕在化していないので事件性がなく、この場合に何らかの書面の作成を代理で行うことは「法律事務」には該当しない、という考え方です。
この点は裁判例によっても若干のブレがあり、法的紛争が具体化していないとしても、潜在的に紛争性があるのであれば事件性ありと考える見解もあります。
他方、事件性不要説はこのような事件性がなくても弁護士の独占業務である「法律事務」にあたるという考え方です。例えば、上記の離婚の例で、離婚合意書を作成する場合、紛争性が全くなくても、例えば養育費に関して誤った法的認識に基づいた書面を作成しては当事者に不利益になるでしょうと。ですから、事件性はなくても、法的権利の創設などに関する事務は広く「法律事務」に当たると考えるわけです。
ただ、事件性不要説に立つとさすがに広すぎるという場面もあります。例えば、不動産管理会社は騒音トラブルや退去費の精算業務に関する業務を代行することがありますが、これは弁護士法上問題ないのか、また、タレントマネジメント会社は、出演先とギャラの交渉をして契約書の作成を代行します。もちろん、こういった場合にもめごとになれば弁護士に業務を引き継ぐでしょうか、事件性不要説に立つと事件性が全くなくても法的権利関係に関する法律事務の代行を有償で行えば弁護士法違反の問題が生じてきます。弁護士法自体古い法律ということもあり、どこで線を引くかが曖昧なまま現在まで改正されずに来てしまったという側面もあるように思います。
最近の公的な見解では、AIによる契約書チェックツールに関する判断において、事件性必要説に立ちつつ検討が行われているので、少なくとも裁判所や法務省は、弁護士法72条は何らかの事件性があることを前提とした規定であると理解しているのではないかと推測できます。
-
弁護士法第 72 条の「訴訟事件…その他一般の法律事件」に関し、一般に、「法律事件」とは、法律上の権利義務に関し争いや疑義があり、又は新たな権利義務関係の発生する案件をいうとされるところ、同条の「その他一般の法律事件」に該当するというためには、同条本文に列挙されている「訴訟事件、非訟事件及び…行政庁に対する不服申立事件」に準ずる程度に法律上の権利義務に関し争いがあり、あるいは疑義を有するものであるという、いわゆる「事件性」が必要であると考えられ、この「事件性」については、個別の事案ごとに、契約の目的、契約当事者の関係、契約に至る経緯やその背景事情等諸般の事情を考慮して判断されるべきものと考えられる。
(中略)
もとより、上記(1)、(2)以外の場合であって、いわゆる企業法務において取り扱われる契約関係事務のうち、通常の業務に伴う契約の締結に向けての通常の話合いや法的問題点の検討については、多くの場合「事件性」がないとの当局の指摘に留意しつつ、契約の目的、契約当事者の関係、契約に至る経緯やその背景事情等諸般の事情を考慮して、「事件性」が判断されるべきものと考えられる。
AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第 72 条との関係について(令和 5 年 8 月 法務省大臣官房司法法制部)
この解釈の幅があるため、現在の法律の下では弁護士以外がどこまで契約交渉に関与できるかが明確ではありませんが、一つのポイントになりそうなのが、いわゆる企業法務における通常の話し合いや法的問題の検討については弁護士法第72条のスコープから外れているという示唆がある点です。
弁護士法における非弁行為の禁止は、事件屋等の介入によって一般市民が被害に遭うことを防止することがその趣旨にあると言われていますが、ビジネスシチュエーションにおける法的な話し合いまで弁護士の独占業務とするのはさすがに広すぎるということが読み取れます。ただ、法文のどこにも、事業者取引か消費者取引かの区別が書かれていないので、解釈でそのような線を引いてしまうのにはテクニカルな問題が発生してしまうということでしょう。これは、そもそも時代に合った形で弁護士法を改正すべきであるという立法論の話になってきてしまいます。
エージェント代行会社の新しい可能性
もし、今後弁護士以外の代理人が契約交渉を行うことが認められると、新たなエージェント代行会社が次々と誕生する可能性があります。これらの会社は、弁護士以外にも交渉やビジネスに精通した専門家を抱え、選手やクライアントに多様なサービスを提供できるでしょう。
そもそも、スポーツビジネスにおける代理人交渉において法的な解釈が問題となるのは1割か2割ほどでしょう。年俸交渉で問題となるのは、多くの場合、選手のパフォーマンスや業績への貢献度合い、在籍することにより発生するシナジー効果などです。
こういった分析は法律を知っていたとしても上手くいくとは限りません。むしろ、AIを使った大量の基礎データに基づく提案書作成や、所属チームの会計データを分析した上での査定基準の評価などが重要となってきますが、こういった業務は弁護士が得意とするところではありません。
そもそも弁護士は株式会社のように外部調達で出資を受けると弁護士法違反となる可能性がありますから、AIを使ったエージェント活動はAI開発に長けた株式会社が行う方が適しています。また、会計分析については公認会計士やコンサルティング会社の方が適しているでしょう。
-
多国籍交渉のサポート:特に外国人選手や海外の企業が絡む契約では、国際的なビジネス慣行や法律に詳しいコンサルタントが契約交渉を代行できる。
ビジネス面でのアドバイス:法的な側面だけでなく、ビジネスの視点から最適な契約条件を提供する。
提案交渉:データ分析、アカウンティング手法を用いた条件交渉
契約後のサポート:契約書が締結された後も、実務的な運用や条件の見直しを継続的に支援する。
資産運用や生活サポート:選手の長期的キャリアを見据えた周辺サポート
これらのサービスは、従来の弁護士が提供する法律的なサポートとは異なる価値を持ち、契約交渉における新たな選択肢として期待されます。
弁護士資格とエージェント業務の境界線
新たなエージェント代行会社が台頭する可能性がある一方で、弁護士法の規制も依然として重要な要素です。法的リスクを伴う契約交渉において、どこまでが「法律事務」とみなされるかの線引きは引き続き議論が必要です。法律の専門知識が欠けた代理人が関与することで、依頼者が不利な契約を結ぶリスクも否定できません。
また、コンサルティング会社がエージェントとして活動する場合、その範囲や業務内容を法的にどのように整備するかが重要となります。適切な資格を持たない者が契約交渉を行うことができるのか、それとも部分的にしか関与できないのか、規制当局や立法機関がより明確な指針を打ち出す必要があります。
今後の展望:エージェント代行サービスの可能性と課題
プロ野球の事例に限らず、今後もさまざまな業界で代理人制度の見直しや新しいサービスの登場が期待されます。しかし、法的な制約と実務的なニーズの間で、バランスを取ることが求められます。
エージェント代行サービスが広がることで、ビジネスの現場においてより柔軟で効率的な契約交渉が実現する可能性があります。ただし、その一方で法的リスクや不適切な代理人選択による弊害も考えられるため、厳密なルール整備と監督が不可欠です。
今後の流れとして、そもそも弁護士がこういった新しい分野におけるビジネスを独占することは不可能であり、また適切でないという状況を理解し、むしろエージェント業、マネジメント業に対する社会的ニーズの増加を見据えてどのようなポジション取りをしていくのかが重要となっていきます。
また、マネジメント業務、エージェント業務についてどのような部分で付加価値を出していくことが今後の差別化につながるのかという分析も重要になってくると覆います。
まとめ:弁護士以外の代理人の可能性と課題
今回のプロ野球選手の代理人問題を通じて、弁護士資格がない者が契約交渉を代行することの是非が改めて浮き彫りになりました。もしこれが認められると、エージェント代行会社が様々なサービスを提供し、新しいビジネスモデルが誕生する可能性があります。しかし、その一方で、法的なリスクや依頼者保護の観点から、慎重な議論とルール整備が必要です。
今後、法改正や新たなガイドラインが制定されるか注目が集まります。代理人制度の発展により、クライアントがより良い選択肢を持てるような仕組みが構築されることを期待します。