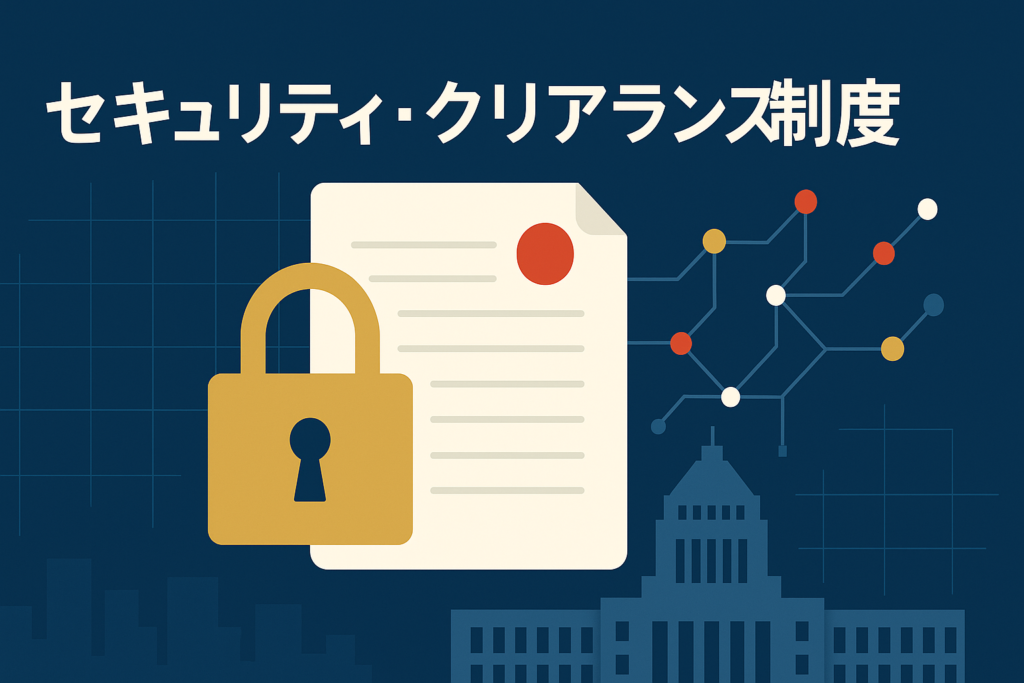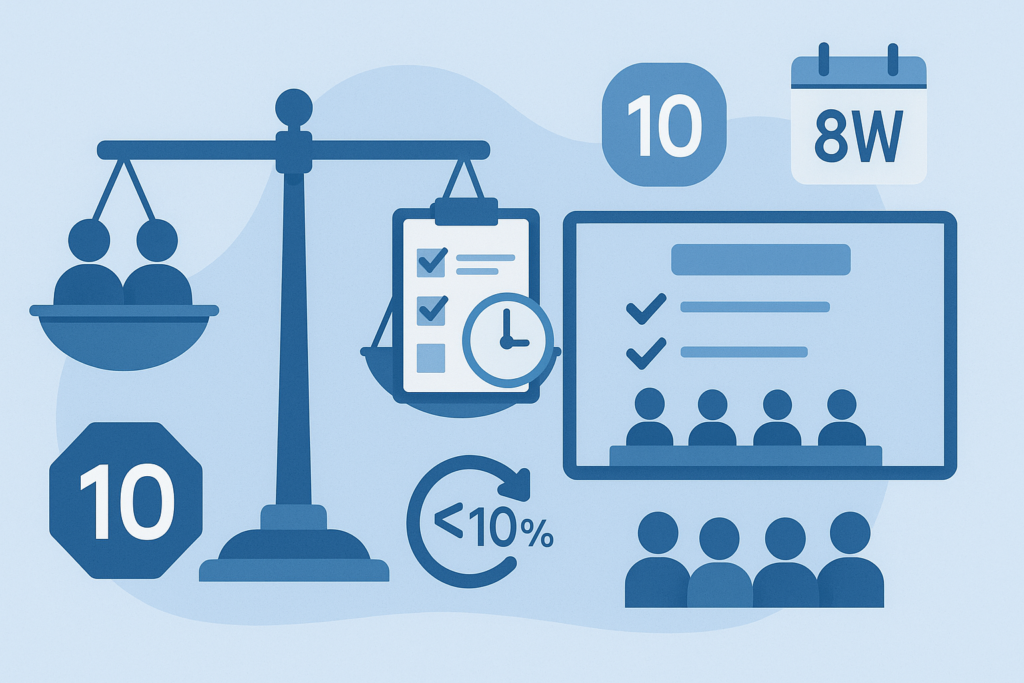はじめに
みずほ銀行のシステム障害が問題になっています。
2021年2月から3月にかけて計4回のシステム障害を起こしたみずほフィナンシャルグループは、その後再発防止策を公表し、いったんは事態が収束したようにも思えました。
ですが、8月20日に再びシステム障害を起こしたことで、金融庁は急遽「報告徴求命令」を発令しました。
行政機関から発令される命令や処分(監督措置)にはさまざまな種類があり、その種類によって事業者がとるべき対応にも違いが出てきます。
事業者は、行政機関が行う監督措置の種類を知ることで、業務遂行への意識を見直すことができ、万一監督措置を受けた場合にも慌てずに対応することが可能になります。
今回は、行政機関が行う監督措置の種類を弁護士がわかりやすく解説します。
1 監督措置の種類
監督措置は監督官庁が所管する事業者を対象に行われるものですが、大きく分けて「行政指導」と「行政処分」の2つの種類があります。
(1)行政指導とは
「行政指導」は、行政手続法により以下のように定義されています。
-
【行政手続法2条6号】
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう
簡単にいうと、事業者に改善を促すために行われる指導や勧告などを「行政指導」といいます。
行政指導を行う場合には法律上の根拠が必要とされていないため、行政指導を受けた事業者は必ず指導に従わなければならないということではありません。
指導に従うかどうかは、事業者が自由に決定することができます。
もっとも、行政指導に従わない場合には、以下で見る「行政処分」を受ける可能性があります。
そのため、行政指導を受けた場合はその内容を十分に精査し、内容が適切だと考えられる場合は従っておいた方が無難だといえるでしょう。
(2)行政処分とは
「行政処分」は、判例上以下の定義が確立されています。
-
【最判昭和39年10月29日】
公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によつて、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう
少しわかりにくいかもしれませんが、簡単に言い換えると、行政機関の行為によって国民の権利義務を発生させることが法律で認められているものを「行政処分」といいます。
行政処分の例としては「許可」が挙げられます。
法律上必要とされる許可を受けることによって、事業者は一定の事業を行う権利を取得し、事業を始めることができるのです。
金融庁がみずほ銀行に行った「報告徴求命令」は、行政機関である金融庁が銀行法に基づいて報告書を提出するよう命令するもの(義務付けるもの)であるため、行政処分にあたります。
2 一般的な監督措置の流れ
監督措置の流れは、根拠となる法令や省庁によって違いがあります。
以下では、一般的な監督措置の流れについて見ていきます。
- ヒアリング
- 立入検査
- 報告徴求
- 改善勧告・改善命令
- 業務停止処分・取消処分
↓
↓
↓
↓
(1)ヒアリング
何らかの問題が発生した場合、まずは監督官庁などによりヒアリングが実施されます。
ここでは、主に事実関係や今後の対応についてヒアリングが行われ、問題が軽微だと判断されれば口頭で指導を受けるなどして改善を促されます。
(2)立入検査
ヒアリングを実施した結果、問題が重大であると判断された場合、職員などによる立入検査が実施されることがあります。
立入検査では、現場に赴いた職員が責任者などにヒアリングを実施するとともに、現場にある書類等を細かく確認します。
必要があれば、書類のコピーなどを持ち帰るということもあります。
(3)報告徴求
立入検査を実施した結果、事業者に重大な法令違反などがあると疑われる場合には、詳しい事情を文書で報告するよう求められます。
金融庁がみずほ銀行に対して求めたのが、この報告徴求です。
(4)改善勧告、改善命令
立入検査や提出された報告書から事業を改善する必要があると判断された場合には、「改善勧告」または「改善命令」が出されます。
「改善勧告」とは、言葉のとおり改善するよう勧告することをいい、これは行政指導にあたります。
これに対し「改善命令」は、行政処分にあたります。
事業者からすれば、改善勧告には必ずしも従う必要はありませんが、改善命令には必ず従わなければなりません。
(5)業務停止処分・取消処分
事業者による法令違反行為が悪質であるような場合には、業務停止処分が出される可能性があります。
具体的な停止期間は事案の性質や根拠となる法令によって異なりますが、業務停止処分を受けると事業者はその期間事業を行うことができなくなります。
また、改善命令に従わなかった場合には、許可や免許が取消される可能性もあります。
この場合、事業者は将来にわたり事業を行うことができなくなります。
3 監督措置に従わなかった場合の罰則
行政機関による監督措置に従わなかった場合、その多くでは罰則が設けられています。
監督措置に従わない行為としては、たとえば以下のような行為が挙げられます。
- 報告徴求に応じないこと
- 正当な理由なく立入検査を拒否すること
- 改善命令に従わないこと
- 業務停止処分に従わないこと
具体的な罰則の内容は根拠となる法令によって異なりますが、懲役刑や罰金刑が設けられていることが多いといえます。
4 まとめ
監督措置を受けないよう適切に業務を遂行していくことが大切ですが、気が付かないうちに法令に違反するケースもあります。
監督措置を受けたとしても、その種類や内容をきちんと確認したうえで適切に対応することが大切です。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。