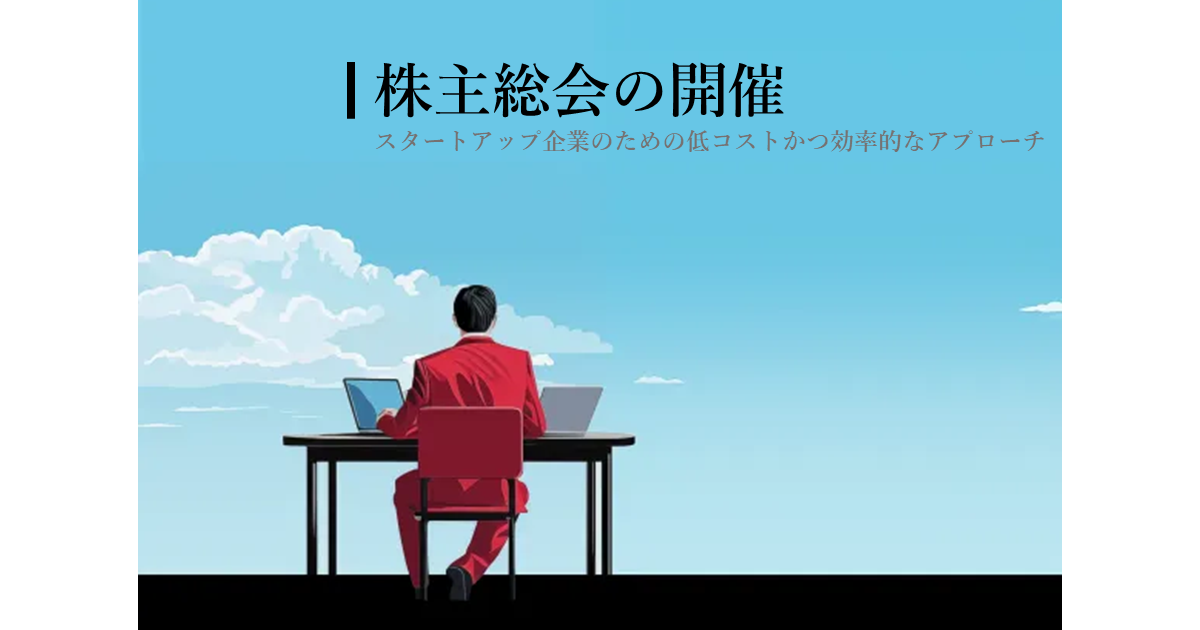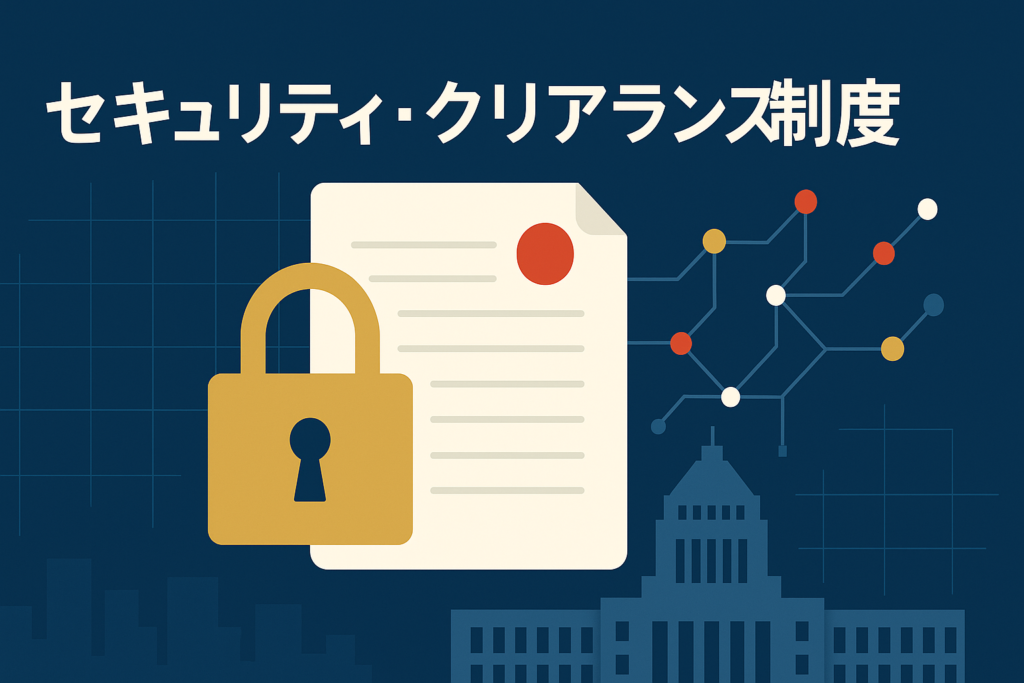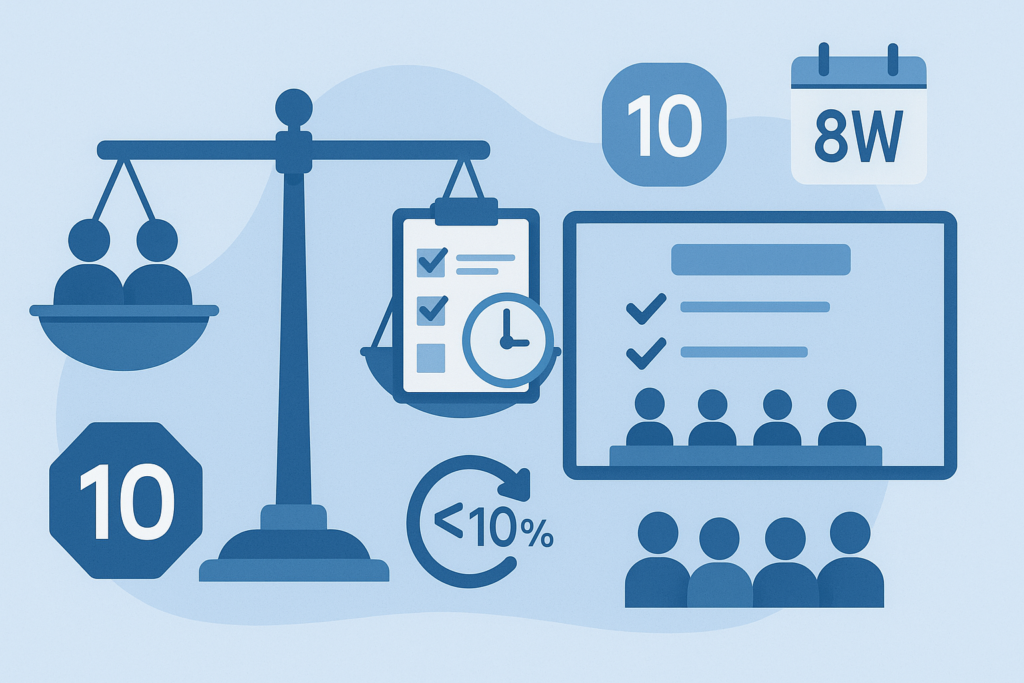はじめに
会社経営者にとって、株主総会は経営の方針を決定し、株主とのコミュニケーションを図る重要な場です。
他方で、スタートアップ企業における会社経営者は、資源を最大限に活用しながら、株主総会を効率的かつ低コストで開催する方法を常に模索しています。スタートアップ段階では、株主の数も少なく、かつ会社の意思決定を迅速に進めたいというニーズがある反面、株主総会に関する手続きを理解していないと、以下のようなリスクを抱えることになります。
- 会社の意思決定がさかのぼって取り消されうる
- 資金調達時のデューデリジェンスで問題視される
- 株主から手続き違反・法令違反を指摘される
- 登記手続きがスムーズに進まない
今回は、株主総会の開催に関する重要な側面を解説し、経営者がこの重要なイベントを最大限に活用するとともに、法的なリスクを回避するための知識について解説します。
1 会社経営者が知るべき法的要件
会社法に基づく株主総会の開催には、一定の法的要件があります。たとえば、株主総会の招集通知は書面でなければならず、株主総会の目的である事項を明確に記載する必要があります(会社法299条2項、4項)。また、会社法では、株主総会の決議の方法や特別決議が必要な事項についても規定しています。
株主総会に開催には様々な方法がありますが、まずは通常開催の方法を正確に理解して、開催と議事録の作成をしてみることをお勧めします。それによって、株主総会の全体像がイメージできるからです。そのようなイメージができてから、ケースに応じて委任状による決議や書面による株主総会の決議を試してみる方法がよいと思います。何事も、まずは基本を押さえることが重要です。
2 株主総会招集通知の期間制限について
株主総会の招集通知に関する期間は、会社の種類によって異なります。具体的には、公開会社の場合、株主総会の日の2週間前までに株主に対して招集通知を発しなければならず、非公開会社では1週間前までに発する必要があります。さらに、取締役会非設置会社の場合は、定款でさらに短縮することが可能です。これらの規定は、会社法第299条第1項に基づいています。
この規定は、株主に対して総会の開催について十分な準備時間を与えるためのものです。株主総会の招集通知は、株主が会社の重要な意思決定に参加するための重要な手段であり、株主が総会に参加し、意見を述べる機会を確保するために必要な情報を提供するものです。したがって、これらの期限は、株主の権利を保護し、株主総会の透明性と公正性を確保するために重要な役割を果たしています。
招集通知期間については、取締役会非設置会社において定款で1週間よりも短い期間を定めることができるとされている場合もありますが、余りにも日程に余裕のない招集通知は避けた方が無難です。通知の発送日から開催が可能な期間のカウントで数え間違えをしていたり、土日を挟んでいたために委任状などの返送が事実上間に合わないなどの問題が生じることもあるからです。
3 委任状による議決権行使
議決権行使のためには、代理人が委任状を会社に提出し、議決権行使を行います。この際、会社(株主総会の議長)は、提出された委任状の内容を確認します。
なお、上場会社の実務では、株主が代理権授与の意思を表示した書面として委任状を使用します。また、その真正性を確認するため、会社が株主に送付した議決権行使書面等の提出を求めることが一般的です。
また、賛否の記載欄の設置について、委任状には、賛否を示すための記載欄が必要です。これは、株主の意思を正確に反映するために重要です。
仮に記載がない場合、委任状は白紙委任として扱われます。なお、会社提案の議案について賛否を記載する欄を欠いた委任状を無効として扱いが法令違反であるとして株主総会決議取消事由が存在すると認められることもあります(東京地裁平成19年11月22日判決・モリテックス株主総会決議取消請求訴訟参照)。また、賛否の指示に反する議決権行使は、無権代理として無効となり得ます。
なお、賛否についての記載がない場合もありうるため、会社としては、議決権行使書面に賛否の記載がない場合には会社提案に賛成するものとして処理することを予め決めておくこともできます。
議決権の委任状による行使は、スタートアップ企業でもよく用いられており、ポピュラーな手法です。
4 書面による株主総会決議の可能性
会社法第319条に基づき、決権を行使できる株主全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした場合、物理的な株主総会を開催することなく、提案を可決する株主総会決議があったとみなすことができます。これにより、会社経営者は株主総会の報告事項に関しても、同様の要件のもとで報告を省略することが可能となります。
書面による株主総会決議は一見簡便でよい方法に見えますが、招集通知段階で、提案される議案の内容を明確にし、株主に対して十分な情報提供を行う必要があります。また、株主全員からの同意がなければいけない点も高いハードルとなります。
どちらにせよ書面を提出してもらうのであれば、委任状の方が簡便でよく知られているため、あえて書面による株主総会決議を選択するメリットは小さいのかも知れません。
5 株主総会のリモート開催について
会社法においては、株主総会のリモート開催についての直接的な言及はありません。しかし、デジタル技術の進歩と、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響により、リモートでの株主総会の実施が増加しています。このような形態の株主総会は、物理的な場所に依存せず、株主のアクセスを容易にし、より幅広い株主の参加を促進することができます。
経済産業省による「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド案」では、株主総会の概念を拡張し、インターネット等の手段を用いた参加を可能にしています。リアル株主総会に加えて、遠隔地の株主が法的な「出席」を伴わずに審議を傍聴できる「ハイブリッド参加型バーチャル株主総会」、及びインターネットを用いて法的な「出席」が可能な「ハイブリッド出席型バーチャル株主総会」が提案されています。
さらに、物理的な株主総会を開催せず、インターネットのみで出席する「バーチャルオンリー型株主総会」も検討されており、これらの方法は株主総会への参加・出席機会を拡大し、株主との対話を深めるための選択肢として提示されています。
出席を伴わないバーチャルな参加をする場合は、事前に招集通知の送付と議決権代理行使の機会を十分与えているのであれば、委任状による安定的な議決の確保ができるため、よい方法であると言えます。
完全バーチャルな株主総会を実施するためには、まだまだハードルが高いと言えます。
6 まとめ
株主総会は、会社経営者にとって、企業の将来を左右する重要なイベントです。スタートアップから大企業まで、あらゆる規模の会社で、株主との良好な関係を築き、経営の透明性を高めるために役立つ機会となります。効果的な株主総会の開催は、会社の成功への鍵となるでしょう。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。