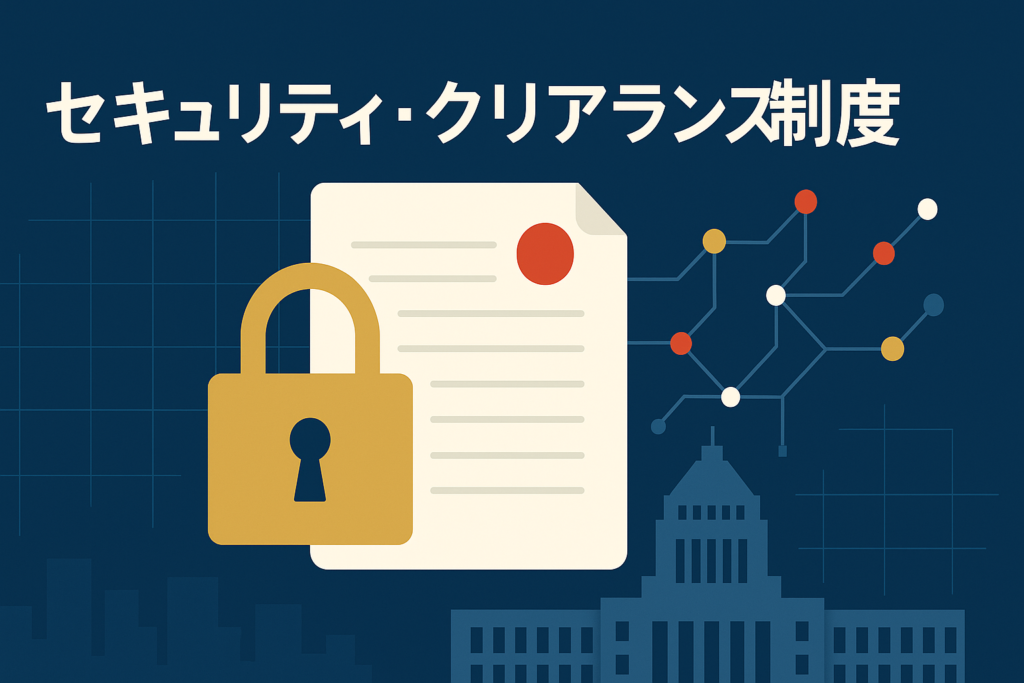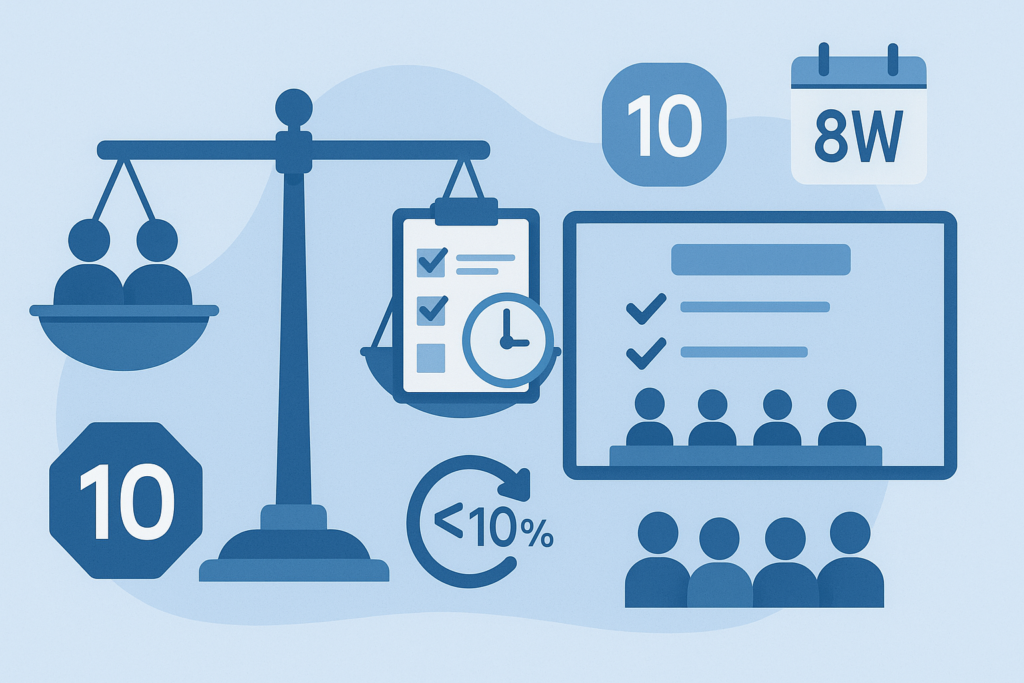はじめに
弁護士の勝部です。
ChatGPTを契約書チェックやレビュー作業に活かしたいけれど、プロンプトがわからないとお困りではありませんか。
そもそも、契約書レビュー作業は複雑で、一般的には弁護士などの専門家でないとタッチできない(素人が下手にチェックすると間違える)と思われがちですが、ChatGPTの特性を理解してプロンプトを組めば、実用上使えないこともないというのが私の感覚的な感想です。
この記事では、契約書レビューを生業とする弁護士が考える「契約書レビューとChatGPT」「契約書レビューに効くプロンプト」をいくつかご紹介します。
-
【免責事項】
本ブログの記事は、ChatGPTを活用した契約書レビューに関する技術的な解説を目的としています。提供された情報は一般的な知識に基づいており、特定の法律的アドバイスを意図するものではありません。契約書のレビューに関しては、必ず自己責任で判断し、必要に応じて専門家の意見を求めることを推奨いたします。また、社内ポリシー、倫理規定、法令適合性については、各自の判断に委ねます。当ブログの内容に基づいて生じた結果や損害については、一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
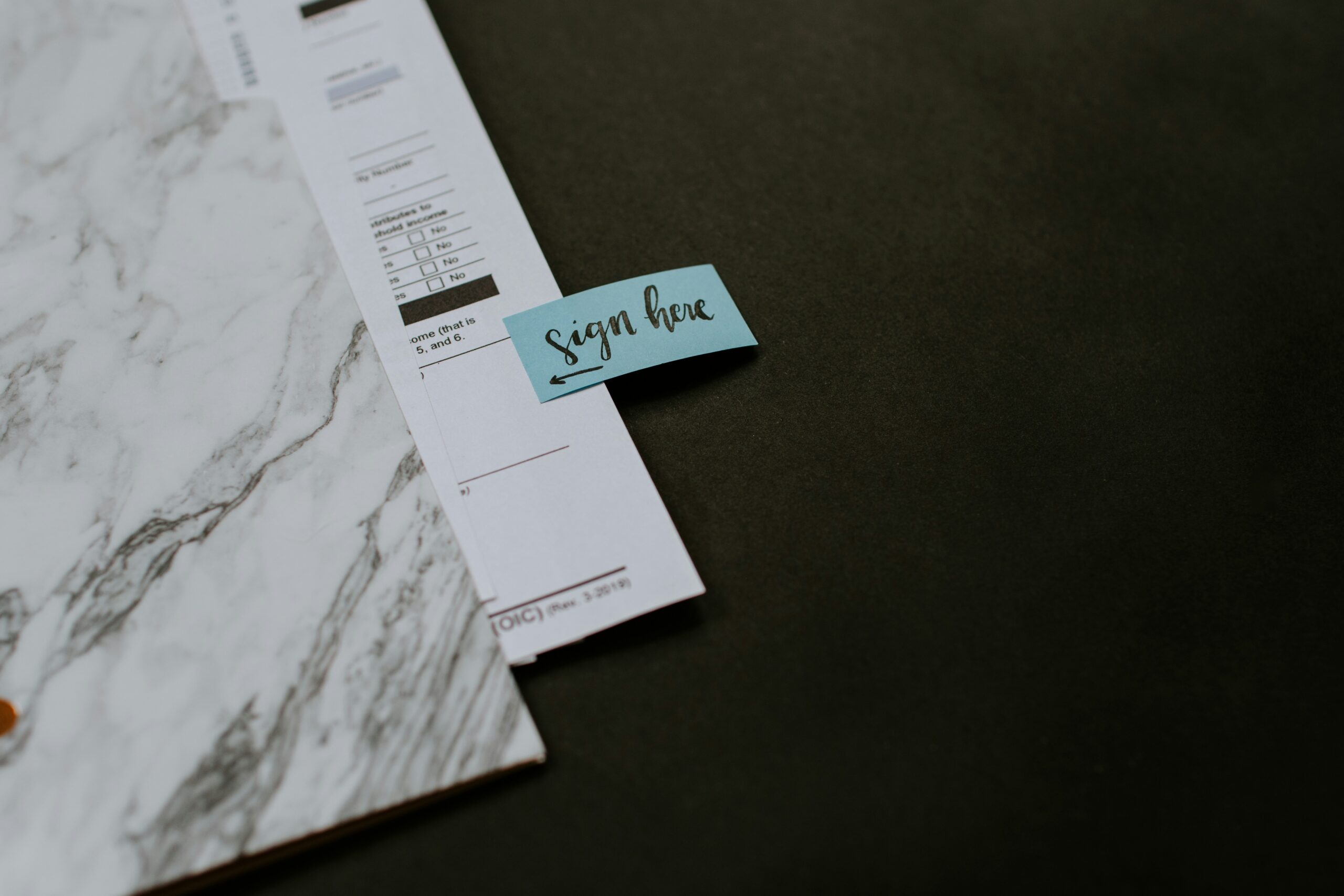
1. そもそもChatGPTは契約書レビューで使えるの?
ChatGPTは法律のような専門性の高い分野においては使えない、間違いだらけだ。だから契約書レビューには使えない、と思う方も多いかもしれません。
確かに、ChatGPTを仮想弁護士に見立てて法律相談をする、というような使い方をしても、現時点(2024年10月時点)において正確な回答を出すことは難しい印象です。
しかし、これはChatGPTが本質的に言語処理エンジンであり、あらゆる法的前提や背景データが提供されていない状況で質問をされるからです。
ChatGPTは法律知識を持つ弁護士や専門家とは異なり、法的知識や解釈の方向性をデータとして持っているわけではありません。
また、弁護士は法律業務をするときには、法的効果に影響しそうな事実関係を自ら設定して周辺事実の深掘りしていきます。
こういった前提の違いがあるのですから、弁護士のレビューとAIのレビューで品質に差が出るのはある意味で当然のことと言えます。
しかし、ChatGPTの「使い方」を工夫すれば、契約書レビューにおいても有用なツールとなり得ます。
なぜならば、ChatGPTは前提となる情報さえ特定すれば、その限られた情報を言語法則に従って処理するのは間違いなく得意で、かつ途轍もなく早いです。
例えば、特定の契約書の文章全文を与え、その内容に基づいた具体的な質問をする場合、ChatGPTは比較的正確に契約書の条文を指摘し、それに基づいて答えを教えてくれます。
たとえば、「この契約書を締結した後に甲が支払期限に代金を支払わなかった場合、どのようなペナルティが発生するのか?」という形で質問をすれば、ChatGPTは契約書内の該当する条項を即座に探し当て探し、要点をまとめて提示します。
つまり、ChatGPTを契約書レビューに活用する際には、具体的な契約書の内容や質問の仕方が重要なのです。
適切なプロンプトを用いることで、効果的に契約書の内容を確認し、リスクや条項の確認を迅速に行うことが可能です。
ただし、契約書レビュー・交渉を弁護士に任せた場合のクオリティと比較すると、ここの書かれているプロンプトによる答えだけで全く足りないというのが正直なところです。
例えば、弁護士が契約書レビューをすることを想定すると、最低でも以下の視点から何度も内容をチェックしています。
-
【弁護士が契約書レビューにおいて確認するポイントの例】
契約書の文言から意味が特定できるか
内容が間違っていないか、制定法体系と齟齬が生じていないか
抜け漏れがないか
よりよい表現はないか
そもそも違法ではないか
契約当事者の間で不公平な内容となっていないか
業界の相場と比較して不当ではないか
この契約当事者との間でバランスが取れているか
想定外の事故をカバーしているか
裁判になったときに適切に働くか
例えば、裁判になったときに「この一文があったから勝った」という経験が豊富なのは弁護士の強みです。また、契約書はただ書いてあるから全てその通りに裁判官が効果を認めるとも限らず、文章としては成り立っているものの実際の効果は危ういという感覚は経験がなければ持ちようがありません。そういった視点も踏まえた契約書チェックとAIのチェックを比べるのは現時点ではナンセンスです。
ただ、ここで紹介するChatGPTのプロンプトを使えば、各契約条項の意味を理解し、契約当事者に契約条項がどのように作用するのか、といった最低限のところを探ることが可能です。
2. 弁護士に依頼しておけば抜け漏れなんて絶対にないんじゃないの?
弁護士の契約書チェックはそれぞれの法律事務所が二重三重にチェックポイントを置いてチェックするのが通常なので、一般的にはミスは含まれていないことが多いですが、そうでないこともあります。
それは、いわゆる大手の法律事務所や、一部上場企業などのクラスの会社が出してくる契約書でも同じです。
こういった「レベルの高い」契約書であれば、そもそも間違いや漏れなんてそうそうあるはずがない、という先入観があるかも知れませんが、正直なところ全くそんなことはありません。
大きな会社が裁判で出してきた契約書であっても完璧ではなく、私が経験しただけでも、必要な条項が抜けている、利用規約に特定のトラブルを想定した条項が抜けているか不十分である、そもそも自動更新規定のセッティング漏れで契約が終了していた、などのケースがありました。
私個人でもそれなりに目にしているので、問題なく取引が終了した契約書であっても細かく読むと意外と落とし穴があったりする可能性があります。
弁護士は法律のプロではあるものの、契約書だけをレビューして下さいとポンと渡された状態では、重箱の隅を突くような細かな事例設定までは意外と想像し切れていないこともありえます。
また、契約書を締結する際にあらゆる場面を想定して条項を足していくと言っても、コストとの関係で一つの契約書にはそこまで時間を掛けられないこともあります。
その結果、
・普通はこのひな形を使うからこれを微修正してそのまま使えばいいや、ということで漏れが発生
・条項を組み合わせたり変更したことで想定していなかった不整合が発生する
というようなことが起きてしまうのだと思います。
これがプログラミングであればデバッガを使って論理的なミスに気が付けたり、運用しているうちにエラーが発生して修正箇所が分かることもあります。
しかし契約書は問題が起きたときでないと精読されない傾向があるので、間違いがあっても気が付くきっかけが少なく、ミスが見過ごされがちになるのです。
3. ChatGPTの方が優れている点~先入観が一切ないこと
むしろ、ChatGPTなどのAIは、「先入観なく、文章を書いてある通り理解・処理する」という面で人間よりも優れているのかも知れません。
心理学者ダニエル・カーネマンの著書『ファスト&スロー』によれば、人間の意思決定や判断の多くは無意識のバイアスや先入観に左右され、その結果としてミスや誤判断が生まれることが多いとされています。
カーネマンは、これらのバイアスが迅速な意思決定を助ける一方で、思い込みに基づいた誤りの原因となることを指摘しています。
ChatGPTのすごいところは、余計な前提知識を入れずに、日本語を日本語として解釈し、処理することです。
その結果、思い込みで気が付かなかった「別の読み方や解釈」を示唆してくれることがあります。また、記述が足りていないため本来の意図が確定し切れていない箇所や、主語と述語が対応していない箇所、意味の定義がなされていない箇所、などを見つけるのに助かることがあります。
これは、実は人間が苦手としているところで、人間は、「こうだろう」という無意識の予測を前提に文章を読んでしまうので、勝手に善解したり、記述の欠損を脳内補完したりして、ミスを見逃してしまうことが多くあります。
ChatGPTは先入観を持たずに読むということは結構得意なように見えます。
逆にChatGPTには、契約交渉をする際に、こういう風に提案すれば通りやすいとか、この業界ではこの辺りの数字が相場とか、この条項は一見不利に見えるが実は別の条項でバランスを取っている、というような実質的な読み方はまるでダメです。
訓練すればそこもいけるようになるのかも知れませんが、当面は、このような実質的な解釈は弁護士に任せた方が無難だと考えています。
4. ChatGPTで契約書レビューを行うプロンプト例
それでは、ここから、ChatGPTを使った契約書レビューの例を見ていきたいと思います。
契約書の文章ですが、ここでは、文化庁のウェブサイトにあった業務委託契約書を例として使っていきたいと思います。
契約書の文章自体は省略していますが、生成結果はこの契約書ひな形を入力した実際の結果を例示しています。
(1) 契約書の条項を大づかみするプロンプト
-
【プロンプト】
あなたは、法的な書面の分析に詳しい専門家です。
以下の契約書の契約条項について、この条項の意味を法律の知識がなくても分かるように300文字以内で説明してください。
###
第1条(業務内容)
○○○(以下略)
-
【生成結果】
この契約書の第1条は、発注者が受注者に特定の業務(「本業務」)を依頼する内容を示しています。業務には、作品の制作、納品、保守・修理、広告宣伝の協力などが含まれます。具体的には、作品の素材や大きさ、納期、保守の頻度などの詳細が設定されます。また、まだ決まっていない事項については、協議を経て期限内に決定し、書面で通知することが求められています。これにより、業務の範囲や条件を明確にし、トラブルを防ぐ仕組みが整っています。
まあ、これは類例でも多くある使い方ですね。
「法的な書面の分析に詳しい専門家」という形で役割を与えることで、ある程度生成の方向性を示すことが可能です。
条項の意味を大まかに理解するという意味では一応使えるかなという感じです。
(2) 契約書の条項に定め漏れがないかチェックするプロンプト
-
【プロンプト】
あなたは、法的な書面の分析に詳しい専門家です。
以下の契約書の契約条項について質問します。
この条項から読み取れないものの、本来は決めておくべきことがあれば指摘してください。また、この契約書を作成した方に不明点を質問する場合の質問文を併せて作成してください。
###
第7条 (実績公表)
○○○(以下略)
-
【生成結果】
質問文: 「第7条に関して、以下の点についてご確認させてください。
1. 実績公表の際、どの程度の詳細を公開することが許可されているのか具体的な基準はありますか?
2. 公表する前に、発注者の承認を得る必要があるか教えてください。
3. 実績の公表はいつ行われる予定でしょうか?
4. 秘密保持義務に違反した場合の責任について、どのように定めていますか?」
契約書では、ぼんやりとした表現なので、一見重要なことが定められているように見えて、実は具体的なことは余り確定的に書かれていないということも少なくありません。そのような条項のリスクをチェックすることも想定できます。
弁護士的に、この条文で気になるのはむしろ実績公表は無期限に許されるのかどうかで、その点の質問が抜けています。
ただ、例えばこの質問をきっかけに公表にあたり発注者の承諾を得ることが条文に盛り込まれたとしたら、承諾を与える際に期限を設けたり、不適切な公表には承認を与えないというコントロールが可能になります。
このまま張り付けて先方に送りつけるとやや“うざい”内容なので、もう少しポイントを絞った方がいい印象ですが、指摘の方向性は間違っていないかなと思います。
(3) 契約書の条項から権利義務関係を抽出するプロンプト
-
【プロンプト】
あなたは、法的な書面の分析に詳しい専門家です。
以下の契約書の契約条項について、以下の処理をしてください。
(1)この条項から、甲がどのような権利が発生し、また、甲がどのような義務を負うのかを抽出してください。もし、甲に権利が発生せず、または、義務を負わない場合はその旨記載してださい。
(2)この条項から、乙がどのような権利が発生し、また、乙がどのような義務を負うのかを抽出してください。もし、乙に権利が発生せず、または、義務を負わない場合はその旨記載してださい。
(3)この条項は甲乙どちらに有利ですか、それとも中立ですか?理由とともに説明してください。
###
第7条 (実績公表)
○○○(以下略)
-
【生成結果】
(1)甲(発注者)の権利と義務
権利:甲は、感染症の流行や自然災害等の不可抗力によって本業務が中止・延期となった場合に、当該業務に関する対価の請求を拒むことができます。
義務:甲は、受注者(乙)が既に行った業務の割合に応じて対価を請求される場合には、その請求を拒むことはできません。
(2)乙(受注者)の権利と義務
権利:乙は、感染症の流行や自然災害等の不可抗力によって本業務が中止・延期となった場合に、既に行った業務の割合に応じて対価を請求することができます。
義務:乙には直接的な義務は記載されていませんが、業務の履行を行うことが前提となっているため、甲との協議に基づく決定に従う必要があると解釈されます。
(3)この条項の有利性
甲に有利: この条項は甲に有利と考えられます。なぜなら、甲は不可抗力による業務の中止・延期が発生した場合に対価の請求を拒む権利を有しており、経済的リスクを軽減できます。さらに、乙に対して支払うべき対価が減少する可能性があるため、甲にとって有利な条件と言えます。
どんな複雑な契約書も、結局、当事者の権利義務を確定させるために締結するのですから、ある意味本質を突いた使い方と言えます。
法的文章の読み解きについて専門的な訓練を受けた弁護士であればこういった情報処理はお手のものですが、それ以外の方にも分かりやすい結果を抽出するというメリットがあるかも知れません。
ただ、これ自体は言語的な情報処理に過ぎないので、法的解釈という視点からは不十分なものもありうることは注意が必要です。
(4) 契約書全体から必要な情報を抽出し、シミュレーションをするプロンプト
-
【プロンプト】
あなたは、法的な書面の分析に詳しい専門家です。
以下の契約書の契約条項について、以下の[質問]に回答してください。
[質問]この契約書では、契約期間はいつからいつまでですか?その情報は第何条に書かれていますか?
###
契約書全文をペースト
○○○(以下略)
-
【生成結果】
契約書における契約期間は、第12条に記載されています。具体的には、契約の有効期間は「○年○月○日から○年○月○日まで」と定められており、この期間に基づいて契約が有効であることが示されています。
読んでみると確かに12条に期間の定めがあります。
こういった単純な質問であればある程度間違えずに生成してくれるようです。
(5) 契約書全体からリスクを抽出するプロンプト
-
【プロンプト】
あなたは、法的な書面の分析に詳しい専門家です。
以下の契約書の契約条項について、以下の[質問]に回答してください。
[質問]この契約を締結した場合において甲の最大のリスクは何ですか?
そのリスクの解決するためにはこの契約書にどのような修正をすべきかを教えてください。
###
契約書全文をペースト
○○○(以下略)
-
【生成結果】
受注者の最大のリスクは、納入物が発注者の仕様や要求に適合しない場合に生じる責任や損害賠償の可能性です。具体的には、以下のようなリスクがあります:
1. 納入物の不適合: 発注者が納入物の検査を行い、不合格とした場合、受注者は修正や再納入を行う責任があります。これに伴い、追加のコストや時間が発生する可能性があります。
2. 契約解除のリスク: 発注者が契約を解除する事由に該当した場合、受注者は損害賠償を請求されるリスクがあります(第13条)。
3. 著作権の問題: 受注者が発注者の要求に基づいて制作した作品に対して、第三者からの権利侵害の請求が生じた場合、受注者がその責任を負うことになります(第5条)。
リスクを解決するための契約書の修正提案
1. 納入物の適合に関する明確な基準: 第4条(納入・検査等)の内容を見直し、納入物が発注者の要求に適合するための具体的な基準を明記します。また、発注者が検査を行う際の基準や手続きについても明確化することが望ましいです。
2. 修正期間の明確化: 不合格の場合の修正期間や回数を明確に定め、受注者が適切に納入物を修正できるようにします。また、再納入に関する条件を具体化し、コスト負担のルールも明示します。
3. 契約解除に関する明確な条件設定: 第13条(解除)の条件をより明確にし、受注者が契約解除に対する保護を受けられるようにします。例えば、契約解除に至る前に修正の機会を与えることを盛り込むことが考えられます。
4. 責任の範囲の明確化: 第5条(権利)において、第三者からの権利侵害の請求に対する責任の範囲や、受注者が発注者に通知する義務について具体的に記載し、受注者の責任が不当に広がらないようにします。
これらの修正により、受注者のリスクを軽減し、より明確で安全な契約関係を構築することができます。
割と契約書レビューでありそうな使い方でプロンプトを組んでみました。
ただ、ハッキリ言って抽象度の高い質問(例えばリスクとはどういう条件のどの範囲のものまでを含むのか曖昧過ぎる)については怪しい解答が結構あります。
この使い方による生成結果は鵜呑みにせずに、弁護士にチェックを頼んだ方がよいと思いますね。
何か生成精度を上げるよい方法があるのかも知れませんが、多分人間の弁護士が直接ジャッジした方がよいのかなと思います。現状は。
まとめ
本記事では、契約書レビュー業務の重要性を俯瞰し、ChatGPTを活用することで法務業務の効率化が可能であることを紹介しました。
契約書の内容を迅速かつ正確に分析するためには、具体的なプロンプトの使い方が鍵となります。
実用的なプロンプトとして、契約書の条項確認、リスク分析、条件変更の影響評価など、さまざまな質問方法を提案しました。
これらのプロンプトを駆使することで、法務業務がより効率的かつ効果的に行えるようになります。
冒頭にお示しした免責事項にご注意の上、ChatGPTを活用して、合理的思考に基づく戦略的な法務構築を進めていきましょう。