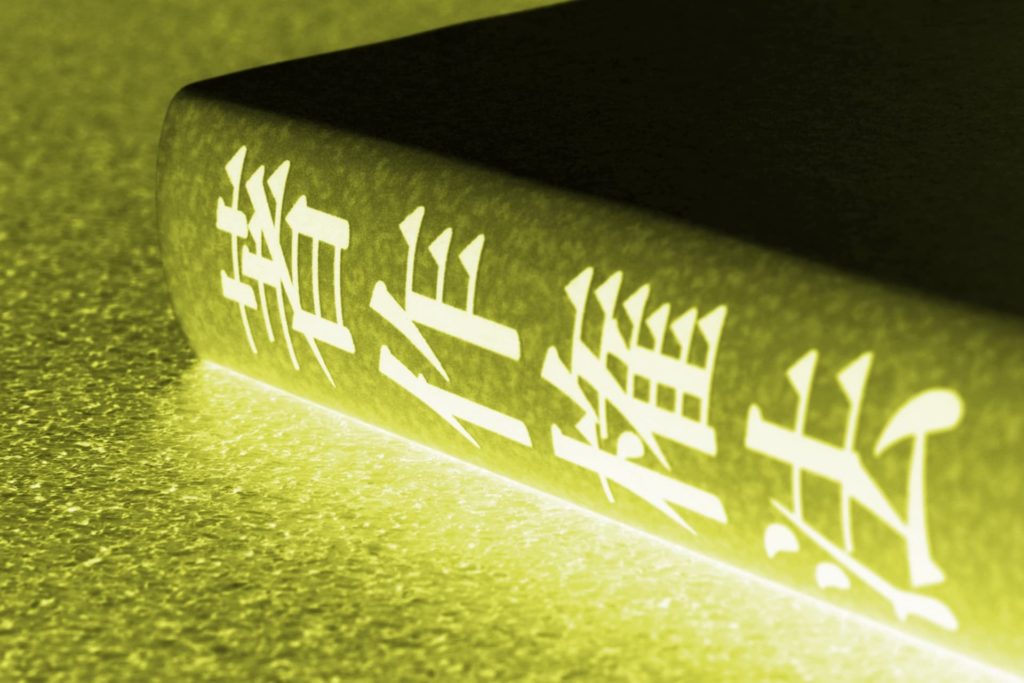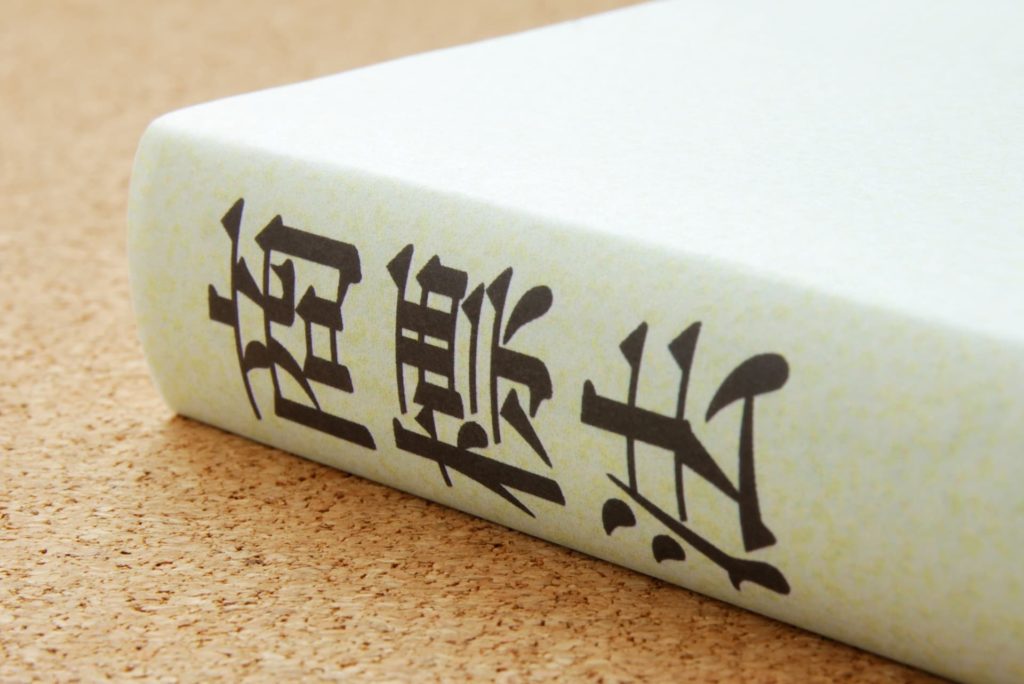生成AIの普及と規制の必要性―世論調査結果から読み解く
生成AI(Generative AI)が世界中で急速に普及している中、日本国内でもその影響に関する議論が盛んに行われています。公益財団法人「新聞通信調査会」が発表した最新の世論調査によると、著作権侵害やフェイクニュースの危険性が懸念され、多くの日本人が生成AIに対する著作権法の規制強化を支持しています。
-
公益財団法人「新聞通信調査会」は12日、メディアに関する全国世論調査の結果を公表した。世界的に急速に普及する生成人工知能(AI)について「著作権侵害などの悪影響を排除するため、政府は規制を強化すべきだ」と答えた人が59.7%に上り、「規制を最小限にとどめるべきだ」の19.1%を大きく上回った。生成AIの利用者は14.1%で、18~19歳では48.6%が「使っている」とした。
生成AI「規制を」6割 著作権侵害や偽情報懸念(共同通信)
本記事では、この調査結果をもとに、生成AIに関する社会的な意見やメディアの信頼度、フェイクニュースのリスクについて詳しく解説していきます。
59.7%が「生成AIの規制強化」を支持
世論調査の結果、59.7%の人が「著作権侵害などの悪影響を排除するため、政府は生成AIの規制を強化すべきだ」と考えていることが明らかになりました。
生成AIの技術は、特に著作物の無断使用やコピーに関連した法的な問題を引き起こす可能性が高いとされており、このようなリスクに対して多くの人々が懸念を抱いていることがわかります。
一方で、「規制を最小限にとどめるべきだ」と考えている人は19.1%と少数派に留まりました。この結果からも、AI技術の急速な発展に対しては、その管理と監視が重要視されていることが伺えます。
若年層での生成AI利用率が高い理由
生成AIの利用率についても調査が行われましたが、18~19歳の若年層では、48.6%という高い割合で生成AIを使用していることが判明しました。全体の14.1%と比較すると極めて高い数字と言えます。
若年層において生成AIの利用が高い理由には、以下のような要因が考えられます。
-
・テクノロジーへの親和性:デジタルネイティブ世代は、AI技術や新しいツールに対する抵抗感が低く、積極的に利用する傾向があります。
・教育環境の変化:AIツールを活用した学習や創作が普及しており、教育現場でも生成AIが利用されているケースが増えています。
これに対して、世代が上がるほど生成AIの利用率は低くなる傾向にあり、特に高齢者層ではその使用に対する懸念が強いようです。
この辺りは、一般的な実感に近い値であるように感じます。
現行法におけるAI生成コンテンツに対する規制と、今後の流れ
このような社会情勢を踏まえ、文化審議会は現在のAIと著作権に関する考え方を取りまとめ、これに対するパブリックコメントを募集しました。
こういった議論の流れが今後の法規制を予測する上で参考になりますが、ここでは、この素案の解釈をベースに、いわゆるRAGモデル(Retrieval Augmented Generation)などの手法を使って著作物を再生成する場合の著作権侵害の有無について、現行法がどのような立場なのかを説明します。
なお、RAGとは、すでに収集済の信頼できるデータを検索して情報を抽出し、それに基づいて大規模言語モデル(LLM)に回答させる方法のことです。
著作物の複製の問題
RAG(検索拡張生成)等の手法では、インターネット上に掲載された著作物を含むデータを元にベクトル変換を行い、生成AIによる回答を生成します。この過程におけるデータの複製や改変行為が著作物の「複製」や「翻案」に該当する可能性があります。特に、学習対象のコンテンツに創作的表現が含まれている場合には、複製に伴う著作権侵害のリスクが高まります。
非享受目的利用(日本法第30条の4)の適用範囲
日本の著作権法第30条の4では、複製が「非享受目的」であれば、著作物の複製が許される可能性があります。ただし、生成されたコンテンツが著作物の創作的表現を含むかどうかが重要な判断基準です。具体的には、RAGによって生成された回答が、元の著作物の表現を直接的に出力しない場合には、法30条の4が適用される可能性がありますが、著作物の表現が含まれる場合には適用されない可能性があります。
軽微利用(日本法第47条の5)の適用範囲
RAGのような技術で既存の著作物を利用する際、法第47条の5によって軽微な利用が許容される場合があります。しかし、この「軽微利用」とは、利用される部分が著作物全体の一部であり、その使用が限定的である場合に限られます。また、著作物の創作的表現の提供を主たる目的とする場合には、この権利制限は適用されません。したがって、RAG等によって再生成されたコンテンツが、既存の著作物を大量に利用している場合は、軽微利用の範囲を超えるため、原則として著作権者の許諾が必要となります。
今後の規制強化の方向性
このような現状の法規制を踏まえ、今後どのような規制がされるのかはまだ明らかではありませんが、著作権法の改正だけでは対応が難しい問題もあります。例えば、新聞社の記事の書きぶりだけを学習しつつ、特定の創作的表現に依拠しないように、フェイクニュースを大量に生成する、という行為は著作権法の規定によって規制すべきなのか難しいところです。
他方、特定のクリエイターのタッチや作風を真似してコンテンツを生成することは当該特定のクリエイターの著作権を侵害する可能性が高いですが、タッチのみを真似するというのは現在の著作権法があくまでも具体的な表現物を保護対象としているので、どのような形で権利侵害を認定するのか難しいところです。
著作権侵害の概念や、侵害があった場合の権利主張を容易にするような制度の新設、損害立証の負担軽減など、様々な規制が望まれるところですが、現時点ではまだ改正の方向性は見えていません。
生成AIがもたらすフェイクニュースのリスク
生成AIの普及に伴い、フェイクニュースのリスクも大きな問題として浮上しています。調査結果によれば、生成AIがニュース記事を作成することに対して、48.9%の人が「フェイクニュースがまぎれ込む危険がある」と懸念しており、44.5%が「記事の責任の所在があいまいになる」と指摘しています。
フェイクニュースの拡散を防ぐための対策
生成AIがニュース記事を自動生成する場合、その内容に対する監督や編集が十分に行われない可能性があり、これがフェイクニュースの拡散につながるリスクがあります。これに対抗するためには、以下のような対策が考えられます。
-
・AIによる記事生成の透明性向上:AIが生成した記事には、それがAIによるものであることを明確に表示し、読者がその出所を把握できるようにする
・ファクトチェックの強化:生成された記事が正確であるかを確認するためのファクトチェックシステムを強化する
・責任の明確化:AIによって生成されたコンテンツの責任の所在を明確にする
フェイクニュースに対する一般市民の不安感
さらに、非常に多くの人々が生成AIによって作成されたニュースに対する信頼性に懸念を抱いていることが明らかになりました。この結果は、生成AIが普及するにつれて、情報の正確性を確保するための取り組みがますます重要になることを示しています。
メディア別の信頼度評価
調査では、100点満点で各メディアの信頼度を評価してもらった結果も公表されました。最も信頼されているメディアはNHKテレビで66.7点という結果になりました。
これに対し、インターネットメディアの信頼度は48.5点と低く、オンラインでの情報収集に対する信頼性の低さが浮き彫りとなっています。インターネットは手軽に情報を取得できる一方で、フェイクニュースや不正確な情報が氾濫しやすい環境です。そのため、インターネットメディアが信頼を得るためには、以下の課題に取り組む必要があります。
-
・情報源の明確化:記事がどのような情報源に基づいて書かれているかを明示し、信頼性を高める
・内容の透明性向上:読者が情報を検証できるよう、透明性の高いコンテンツを提供する
・誤報の迅速な訂正:誤った情報が拡散されてしまった場合には、迅速に訂正をしてソーシャルインパクトを最小限に抑える
まとめ―生成AI時代に求められる規制と信頼の確保
生成AIの普及は、ニュース作成や情報提供のあり方に大きな変革をもたらしています。しかし、著作権侵害やフェイクニュースのリスクが増大する中で、政府による規制の強化や、メディアの信頼性向上に向けた対策が求められています。今後、AI技術の進化とともに、社会全体で情報の信頼性をいかに確保していくかが、重要な課題となるでしょう。