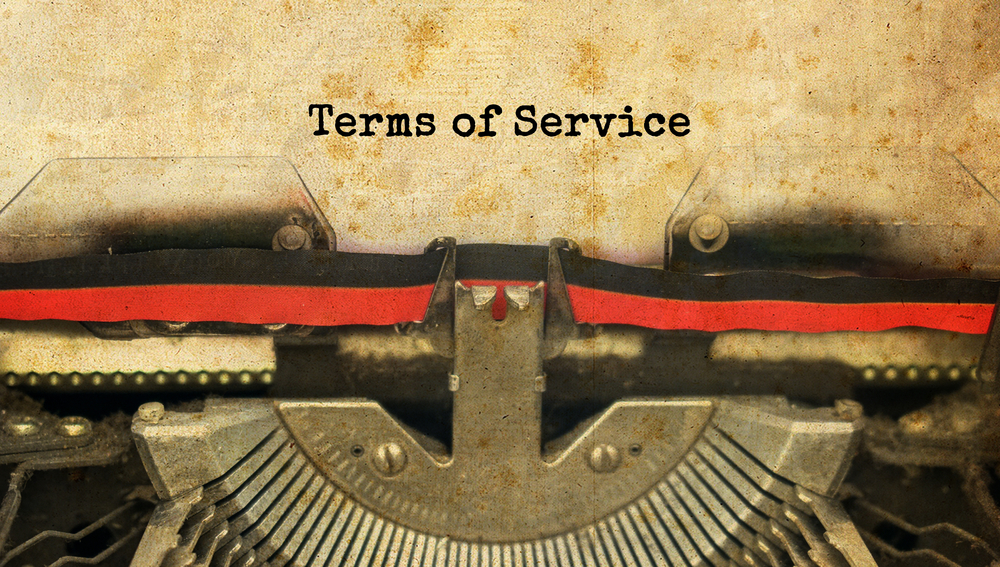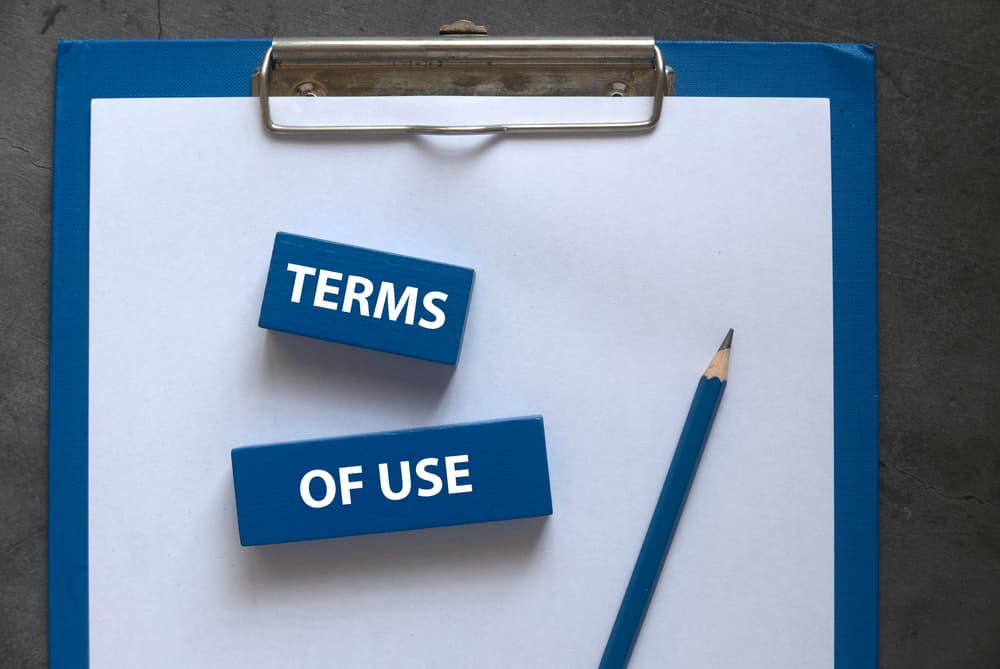はじめに
事業を始める際、必要となる「利用規約」。
自分で作ろうとすると、類似サービスの利用規約を参考にして作成するケースが多いでしょう。
しかし、類似サービスであっても、自社サービスと完全に一致しているわけではありません。
もしかしたら、利用規約が自社サービスとは合致しない内容になっている可能性もあります。
とはいえ、ゼロから自分で利用規約を作成するのは至難の業。そのようなときは弁護士に利用規約の作成代行を依頼することを検討してみましょう。
今回は、弁護士に利用規約の作成代行を依頼するメリット・デメリット、そして相談前の準備や弁護士選びのポイントについて解説していきます。
1 弁護士に利用規約の作成を依頼するべきケースとは

実のところ、利用規約を作成するために必要な資格は存在しません。そのため、本来は個人でも作れてしまうものですが、どのようなときに弁護士へ依頼するべきなのでしょうか。
以下、いくつか例を挙げていきます。
- 新たに立ち上げる事業が画期的で世の中には存在しない
- 関係する法律や権利が多く、個人では作成しにくい
- 内容によってはサービス利用者(利用希望者)から反発を招く可能性が高い
- 自分で作成する時間や余裕がなく、また、法律知識にも不安がある
このようなケースでは、弁護士への依頼を検討してみてください。
利用規約の作成を弁護士に依頼することは、依頼者にとって多くのメリットがありますが、その反面デメリットもあります。次の項目で詳しく解説していきます。
2 利用規約の作成代行を弁護士に依頼するメリットとは?
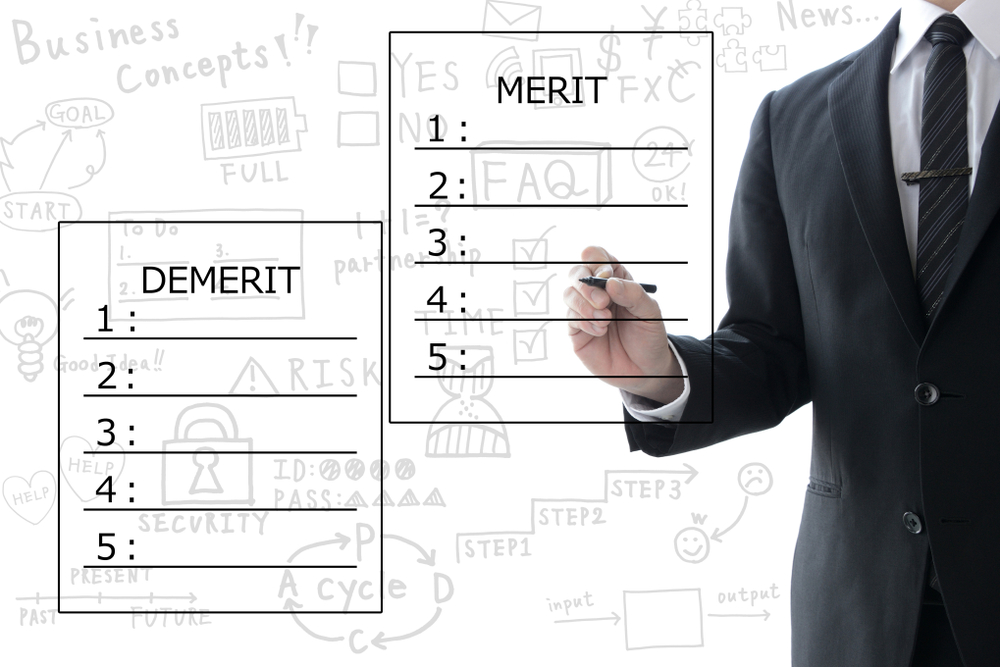
弁護士に利用規約の作成代行を依頼するメリットとしては、主に以下の4つが考えられます。
- 自社のサービスに完全にマッチした内容になる
- ユーザーと事業者の利益バランスに配慮できる
- 専門家が作成するため、法律違反の懸念を持たなくて済む
- サービス内容を踏まえて適切な法律アドバイスもしてもらえる
(1)自社のサービスに完全にマッチした内容になる
弁護士に依頼した場合、当然のことではありますが、サービス内容と合致した利用規約をオーダーメイドすることになります。
もし、個人で利用規約を作成する場合、既に掲載されている類似サービスの利用規約を参考にして作るケースが多いと思いますが、類似サービスであっても、完全にサービス内容が自社のサービスと一致するわけではありません。
そのため、安易に流用してしまうと、自社サービスと合致しない、ちぐはぐな利用規約になってしまう可能性があります。
また、安易にコピー&ペースト(コピペ)してしまうと、後々トラブルに発展してしまうかもしれません。
たとえば、時計修理サービス事業者が利用規約やサイト構成などを真似されたとして同業者を訴えた事例では、裁判所により、利用規約を対象とした著作権侵害が認められています。
このようなトラブルを避けるためにも、利用規約は自社サービスに即したオリジナルのものを作成するべきなのです。
弁護士であれば、ゼロからオーダーメイドで利用規約を作ってくれるので、依頼してみてください。
(2)ユーザーと事業者の利益バランスに配慮できる
利用規約は、事業者がユーザーに対して示したルールであり、作成するときは、事業者側が有利になるような視点を持って内容を決めていきます。
ただし、ユーザーに対して過度に不利益な内容にしていると、トラブルに発展してしまうことがあるため、ユーザーと事業者の利益バランスを考慮しなくてはなりません。
トラブルになりやすい項目の1つとして、「免責条項」が挙げられます。
「免責条項」とは、何かトラブルが発生した際の賠償責任について、事業者側が責任を免除される範囲を定める項目です。
もしも、会社の利益を優先するあまり、利用規約において、
「いかなるトラブルであっても、会社は一切責任を負わない」
という内容にしていると、会社側に非があるトラブルであってもユーザー側にすべての責任を押し付けてしまうことになるため、ユーザーから反発される可能性が高いです。
そのため、利用規約を作るときは、ユーザーと事業者の利益バランスに配慮しながら作成する必要があるのです。
この点、第三者的な立場である弁護士であれば、両者の利益バランスを見極めながら利用規約の内容を定めてくれます。
(3)専門家が作成するため、法律違反の懸念を持たなくて済む
利用規約には、さまざまな法律が関わっています。
関係する法律は、サービス内容によっても多少左右されますが、複数の法律に配慮しながら利用規約を作成していくことに変わりはありません。
①関連する法律
一般的に、利用規約には以下のような法律が関係することが多いです。もっとも、ビジネスモデルによっては、その他の法律が絡んでくることもあるので注意が必要です。
- 個人情報保護法
- 特定商取引法
- 消費者契約法
- 著作権法
- 資金決済法
利用規約を作成するときは、これらの法律を理解し、自社のサービス内容を踏まえながら利用規約に落とし込んでいく必要があるのです。
それぞれの法律は非常に複雑で理解しにくく、また、理解したと思っても解釈を誤っている可能性があります。
そのため、法律の専門家に依頼した方が確実です。
②法改正への配慮
法律が改正されたときは、利用規約の内容を変更・修正しなくてはなりません。
事業を運営していると、法改正だけでなく、サービス内容の変更などさまざまな場面で利用規約を変更・修正することがありますが、この変更を行うためには、あらかじめ利用規約に変更に関するルールを設けておく必要があります。
また、変更・修正するときは、法改正の内容を十分に理解したうえで、利用規約の内容や事業のサービス内容について、以下のようなポイントを確認し対応していくことになります。
- 改正された法律に適合しているか
- 適合していないのはどこか
- どのように修正をすればいいか
これらのポイントは、弁護士であればスムーズに理解し対応してくれるはずなので、利用規約の作成だけでなく、法改正に伴う修正なども依頼してみてください。
(4)サービス内容を踏まえて適切な法律アドバイスもしてもらえる
提供予定のサービス内容を弁護士に説明すると、思わぬところで問題が発覚することがあります。
たとえば、ユーザーが出品した商品を、別のユーザーが購入するフリーマーケットアプリを開発している場合、その商品代金を誰がどのように預かり、ユーザーに渡すのかが問題になります。
もしも、以下のような流れでお金を預かる「エスクローサービス」を行うのであれば、「資金移動業者」として登録を受けなければなりません。
- 運営会社が一時的に、購入者から代金を預かる
- 購入者が入金したことを出品者へ伝える
- 出品者が商品を発送する
- 購入者が商品を受け取ったら、預かっていた代金を出品者に渡す
↓
↓
↓
しかし、資金移動業者となると、最低1,000万円を保全する義務が発生します。
保全する方法として、供託などがありますが、スタートアップやベンチャー企業には負担となってしまいます。
この負担を回避するためには、資金移動業者の登録を受けずにエスクローサービスを導入する方法を考える必要がありますが、弁護士であれば、そうした懸念点を伝えてくれるはずです。
このように、サービス内容によっては法律が絡む問題が隠れていることがありますが、弁護士に依頼すれば、後々起こりうるトラブルに配慮した提案や利用規約の作成をしてもらうことができます。
ただし、追加で料金が発生する可能性もあるため、法律相談や体制づくりのサポートなどにかかる料金を契約時に確認しておいてください。
3 利用規約の作成代行を弁護士に依頼するデメリットとは?

弁護士への利用規約の作成依頼には、メリットだけでなくデメリットも存在します。
- 費用
- タイムスケジュール
2点を解説していきます。
(1)費用が発生する
弁護士へ利用規約の作成を依頼すると、当然のことですが、費用が発生します。
先ほどから解説してきた通り、利用規約を作成するときは、サービス内容に関係するさまざまな法律を考慮する必要があるため、簡単な作業ではありません。
そのため、弁護士費用が発生することになりますが、利用規約における曖昧な定めが内容原因となって後々トラブルに発展するよりは、あらかじめ隙のない利用規約を作成してもらった方がいいはずです。
費用相場などについては、後ほど解説します。
(2)タイムスケジュールをしっかりと組んでおく必要がある
弁護士に利用規約の作成を依頼する場合は、完成までのスケジュールに余裕をもっておく必要があります。
逆に言えば、完成までの日数があまりない状況で利用規約の作成を依頼しようとしても、対応してもらえないかもしれません。
もともと、弁護士は事業者・個人などから、多種多様な依頼を受けています。
利用規約は、ビジネスモデルを理解したうえで複数の法律を考慮しながら作成するため、他の業務と並行しながら作業すると、どうしても時間がかかってしまうのです。
もしかしたら、急な作成依頼にも対応してくれる弁護士もいるかもしれませんが、その分、追加料金がかかってしまう可能性があります。
このように、追加料金や作成不可といった事態に直面しないためにも、十分に時間的余裕のあるスケジュールをあらかじめ組んでおくことが大切です。
4 相談前に用意・確認しておきたいもの

実際に、弁護士へ相談に行く前に、以下の点をあらかじめ確認・準備しておくことで、相談をスムーズに進めることができます。
- 自社サービスの詳細な内容
- 禁止事項として設けたい内容
- 有料の場合の支払い手段
- ほかに弁護士に依頼したい業務の有無
特に①~③は、弁護士が利用規約を作成する際に必要となる情報でもあるため、面談前に準備しておくことで、面談当日に弁護士がゼロから聴き取る必要がなくなり、また、言い忘れなどを防ぐことができ、スムーズに話を進められます。
(1)自社サービスの詳細な内容
先ほどから解説してきた通り、利用規約を作成してもらうためには、詳細なサービス内容を弁護士に伝え、理解してもらう必要があります。
そのため、漏れや抜けがなく説明できるよう、自社サービスについての資料を作成しておきましょう。
また、文字や図説だけでは伝わりづらいポイントをチェックしておき、口頭で説明できるようにしておいてください。
(2)禁止事項として設けたい内容
たとえば、フリマアプリの場合、
- 偽ブランド品の販売禁止
- 値段交渉の禁止
- 指定している決済サービス以外の利用禁止
- 手渡しの禁止
など、さまざまな禁止事項を設けておく必要があります。
ゲームアプリの場合は「現実の通貨を使用したアイテムの売買を禁止する」など、サービスごとに必要とされる禁止事項は異なっているため、あらかじめまとめておいてください。
(3)有料の場合の支払い手段
お金を取り扱うサービスの場合、支払方法やお金の流れなどを明確にしておく必要があります。
銀行振り込みなのかカード決済なのか、商品の代金をどのように扱うのかなど、お金に関するルールをあらかじめ決めておきましょう。
先ほど解説した「資金移動業者」のように、考えていたルールが問題となることもあり得るため、弁護士へ相談する前に、お金に関するルールをある程度決めておいてください。
(4)ほかに弁護士に依頼したい業務の有無
利用規約以外にも、サービス・事業の立ち上げ、事業譲渡などの際には、法律的な問題が関わってきます。たとえば、以下のようなものは、専門家でないとわかりづらく、個人で作成・実施すると、内容が法律に違反してしまう懸念があるので、注意が必要です。
- プライバシーポリシー
- 特定商取引法に基づく表示
- サービスの適法性(リーガルチェック)
- 契約書面
- 投資契約
- 業務提携契約
- 株式発行
このように、個人や会社ではカバーしきれない、法律が絡むものを作成・実施する予定がある場合は、弁護士への依頼を検討してみてください。
5 弁護士選びのポイント

弁護士選びにも注意が必要です。
最適な弁護士に相談・依頼ができるよう、まずは法律事務所のHPなどを確認してみてください。
その際に、特に確認するべきポイントは以下の2つです。
- 費用感
- 専門性
また、問い合わせをするときは、電話よりもメールでの問い合わせをおすすめします。
電話の場合、言い忘れや言葉の誤りなどで、コミュニケーションがうまくいかない可能性がありますが、メールを使えば、送信前に内容を確認でき、正確に内容を伝えることができます。
ただし、早急に返事がほしいなどの場合は、メール送信後に電話をかけた方がよいので、状況に応じて最適な手段を選んでみてください。
(1)費用感
まず、費用について確認が必要です。
ほとんどの法律事務所はHPに料金表を掲載しているので、チェックしてみてください。
なお、利用規約の作成代行の場合、「プライバシーポリシー」や「特定商取引法に基づく表記」などをまとめて作成してもらうケースがほとんどです。
そのため、料金表も3点の作成代行をまとめて表示していることがあります。
作成代行にかかる費用の相場は、以下の通りです。
- 「利用規約」のみ=15~20万円
- 「利用規約」「プライバシーポリシー」「特定商取引法に基づく表記」まとめて=25~30万円
また、利用規約は一度作成してもらって終わりではありません。
サービス内容の変更や法改正に伴う記載変更など、継続的に修正作業が発生します。
その度に法律的な問題がないか、弁護士に利用規約をチェックしてもらい、問題があった場合は修正対応を行ってもらうことになりますが、その場合は、別途費用を払わなくてはなりません。
このように、継続的に弁護士に対応してもらう必要がある場合は、単発で高額な費用を支払うよりも、継続して月額を払う形で顧問契約を締結しておくことで、事業スタート時や拡大時に起こりがちな法的トラブルが起きた場合にも迅速に顧問弁護士に相談しながら対応することが可能です。
(2)専門性
次に大切なのは、専門性です。
たとえば、刑事弁護専門の法律事務所に、利用規約の作成代行を依頼しても、ミスマッチであることがわかります。
一般的に、法律事務所はそれぞれに得意な分野をもっていることが多いため、課金ゲームのアプリをリリース予定の場合、暗号資産や前払式支払手段を規制する資金決済法に詳しい弁護士に利用規約の作成を依頼した方が、刑事弁護専門の弁護士に依頼するよりも、専門性が高くスムーズに対応してもらうことができると期待できます。
また、そうした専門性の高い法律事務所であれば、その分野に関するさまざまなノウハウを蓄積しているはずです。
専門性が高い法律事務所は、HPで得意分野をアピールしていることがほとんどなので、インターネットで検索してみてください。
6 小括

利用規約を作成する際には、さまざまな法律を検討する必要があり、多大な時間と労力を割かなければなりません。
自分で作成することも可能ではありますが、誤った理解に基づいて作成してしまうと、法律に違反した内容になってしまう可能性もあります。
確実な利用規約を作成するためには、弁護士などの専門家に依頼することを検討しましょう。
7 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下のようになります。
- 利用規約には様々な法律が絡むため、一般人には作成が難しい
- 弁護士へ利用規約の作成代行を依頼すると、①自社のサービスに完全にマッチした内容になる、②ユーザーと事業者の利益バランスに配慮できる、③専門家が作成するため、法律違反の懸念を持たなくて済む、④サービス内容を踏まえて適切な法律アドバイスもしてもらえる、などのメリットがある
- 弁護士へ利用規約の作成代行を依頼する場合のデメリットとしては、①費用が発生する、②タイムスケジュールをしっかりと組んでおく必要がある、などが挙げられる
- 弁護士への相談前に、①自社サービスの詳細な内容、②禁止事項として設けたい内容、③有料の場合の支払い手段、④ほかに弁護士に依頼したい業務の有無などをまとめておくとよい
- 弁護士選びのポイントは、「費用感」と「専門性」