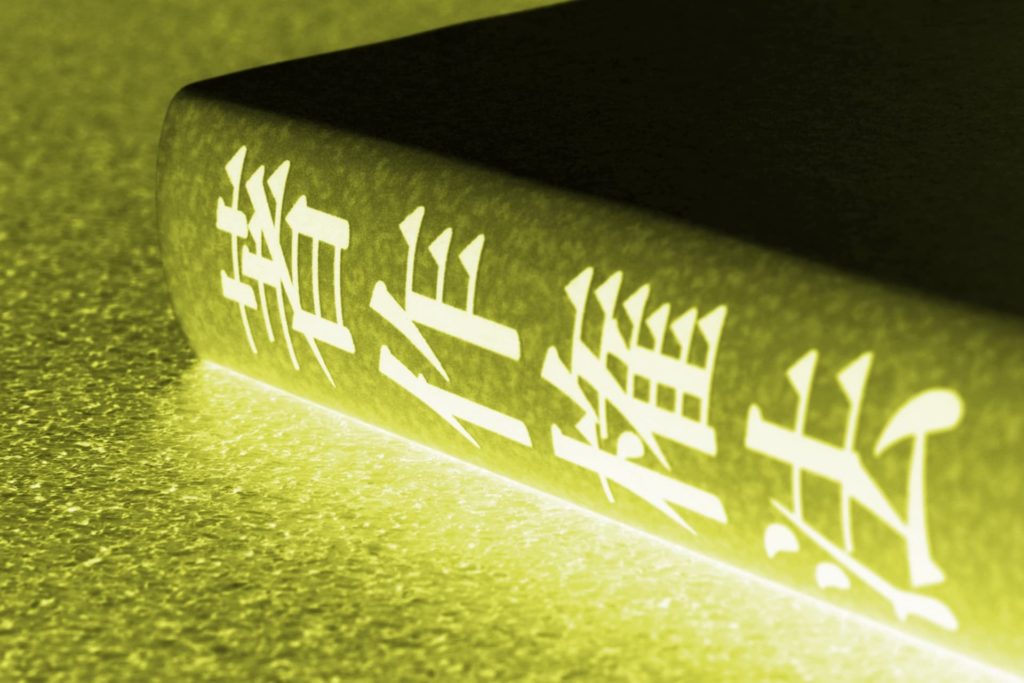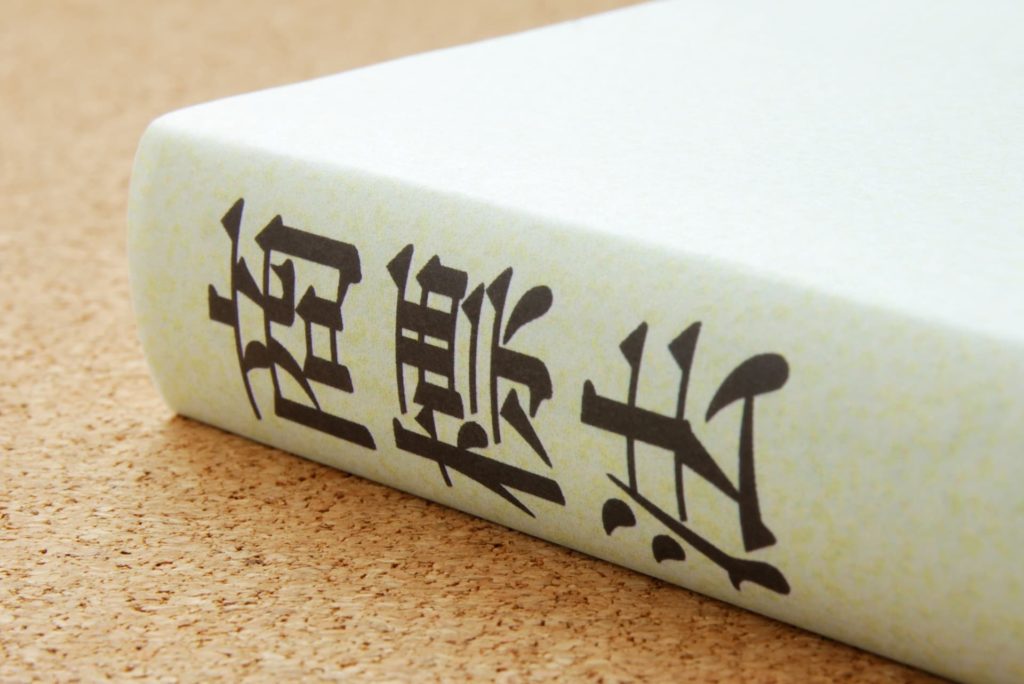はじめに
自社の商品やサービスに社外のクリエイターが作成したイラストや動画などの著作物を利用しようとしたとき、どのような手段を思い浮かべるでしょうか。
まず真っ先に思い浮かぶのは著作権を譲渡してもらうことではないでしょうか。
もっとも、クリエイターが「譲渡したくない」と、話がまとまらないことももありますよね……
そんなときは、「ライセンス契約」を締結してみましょう。
譲渡は無理でもライセンスであればOKをだしてくれる可能性が高まります。
この記事では
- ライセンス契約とはどのようなものか
- 著作権譲渡とライセンス契約の違いは?
- ライセンス契約を結ぶときのポイント
などについて、詳しく解説していきます。
1 ライセンス契約とは
著作権を持っている者(著作権者)が著作物の利用を他者に許諾する契約を「ライセンス契約」と言います。
著作権を持ち、ライセンスを許諾する側(著作権者)を「ライセンサー」、許諾を貰って著作物を利用する側を「ライセンシー」と呼びます。
ライセンシーは期間や用途など、決められた条件の範囲内で著作物を利用することができ、その対価としてライセンサーに「使用料(ロイヤリティー)」を支払います。
もっとも、ライセンス契約と著作権の譲渡では何が違うのでしょうか。どうしてクリエイターは譲渡では納得してくれないのに、ライセンス契約であれば納得してくれる可能性があるのでしょうか。
次の項目では、そんなライセンス契約と著作権譲渡契約の違いを確認していきましょう。
2 ライセンス契約と著作権譲渡契約の違いは?
(1)譲渡とは権利を手放すこと
「著作権を譲渡する」とは、著作権を手放すことをいいます。
他方、他者に著作物の利用を許諾するライセンス契約の場合は、著作権を手放すことなく、単に著作物を利用することを許すことを意味しています。
そのため、著作権を譲渡してしまうと、譲渡したクリエイターはその著作物を利用することができなくなりますが、ライセンス契約の締結であれば、クリエイターはそのまま、その著作物を利用できるわけです。
(2)ライセンス契約は複数の人と締結できる
著作権をあの人にも、この人にも譲渡するということはできません。
なぜなら、一人目に著作権全てを譲渡した時点で、著作権を手放しており、二人目に渡すことができる権利がないからです。
もちろん、著作権の一部に限って譲渡すれば、複数の人に譲渡することも不可能ではありませんが、著作権の一部の権利に限った譲渡はあまり一般的ではありません。
他方、ライセンス契約であれば、ライセンサーが著作権を持ち続けるため、以下の図のように複数の者に利用を許諾することも可能です。

たとえば、あるクリエイターが作った動画について考えてみましょう。作成した動画について、A社には日本国内での上映を許諾する、B社には日本国内での動画の複製(DVDなど)、販売、インターネット配信を許諾する、C社には、アメリカでの動画の上映、複製、販売、インターネット配信を許諾するといったことが可能になるわけです。
(3)譲渡してもらうべきかライセンスしてもらうべきか
事業者として、著作権を譲渡してもらうべきか、ライセンスしてもらうべきかは、「著作物をどのように利用したいか」を基準に考えてみてください。
当然、著作権を譲渡してもらうとなれば、ライセンス契約における使用料よりも高い対価を支払う必要があります。
たとえば、企業のPR動画のように、長期間あちこちに露出させるものであれば、条件をつけられてしまうと利用しにくくなってしまいます。このような場合には、多少高くついたとしても、譲渡してもらったほうがいいでしょう。
他方、期間限定のキャンペーン動画で、キャンペーンサイトにしかその動画を載せないのであれば、わざわざ高いお金を払って譲渡してもらっても、その後の使い道がありません。このような場合には、譲渡ではなく、ライセンス契約を締結したほうがいいでしょう。
もっとも、これらは、事業者側の事情であり、クリエイター側にも譲渡しない・譲渡を認める事情があるでしょう。
そのため、著作物を利用したい場合には、自身の事情のみを相手に押し付けることなく、きちんと話し合いを行って、事業者・クリエイターの双方が納得できる形で契約を締結するようにしましょう。
なお、ライセンス契約ではなく、著作権を譲渡してもらいたい場合には、「【雛形付き】著作権譲渡契約書の作成で気を付けたい11のポイント!」の記事で詳しく解説をしていますので、参考にしてみてください。
では、譲渡契約ではなく、ライセンス契約を締結する際には、何に気を付けるべきなのでしょうか。
3 ライセンス契約で注意したいポイント3つ
それでは、実際にライセンス契約を結ぶ際にはどのようなポイントに注意しておけばいいのでしょうか。
気を付けるべき項目は以下の3つです。
- 誰とライセンス契約を締結するか
- ライセンスの条件
- 表明保証
その他、一般的な契約書の書き方の注意事項は【雛形付き】契約書作成時に知りたい書き方・作り方のポイントを解説
の記事内で詳細がわかります。
4 誰とライセンス契約を締結するか
単純に「著作物を生み出した著作者と利用したい人が締結すればいいのでは?」と考える人もいるかもしれませんが、著作権は譲渡可能です。
そのため、必ず著作者=著作権者となるわけではありません。
また、著作権が譲渡されている場合以外にも他にも誰とライセンス契約を締結しなければいけないか、迷う場合がいくつかあります。
以下の3つのパターンを見てみましょう。
(1)原作がある場合
原作がある著作物を利用したい場合は、原作者ともライセンス契約を締結する必要があります。
たとえば、原作として小説や漫画(原著作物)があり、アニメ化やドラマ化など「二次的著作物」が作成されている作品の場合、この二次的著作物の利用の許諾だけでなく、原著作物の権利を持つ著作権者からも許諾を得なければなりません。
そのため、二次的著作物の著作権者とのライセンス契約と、原作の著作権者とライセンス契約が必要になるわけです。
(2)共同で作成された著作物の場合
①共同著作物は全員の合意がなければ利用許諾ができない
著作物を作成している人は、ひとりとは限りません。複数人で生み出した著作物は以下の条件を満たした場合「共同著作物」となります。
- 2人以上の者
- 共同で創作
- 各人が作った部分をバラバラにして個別に利用できない
共同著作物は、創作した人全員で著作権を共有します。
共同著作物は、著作権を共有する全員の合意がなければ利用許諾を出すことができません。たとえ一部の人から利用許諾を得ていても、全員の合意がない状態だと、その許諾は無効となってしまいます。
そのため、共同著作物を利用するには、非常に手間がかかります。
②映画・動画などは関わった全員が著作者になるわけではない
たとえば、映画、動画、ゲームなどは、制作、監督、演出、撮影、美術など多くの制作者が関わって作品が完成しますが、関係者全員を著作者にすると膨大な人数になってしまいます。
そのため、これらは、全員が著作者になるわけではなく、「一貫したイメージを持って、作成の全体に参加した者のみ」が著作者となります。
以上のことから、演出、撮影、美術など、部分的にしか携わっていた者は、著作者となることができません。製作会社、監督などが著作者になることができますが、多くの場合は、製作開始前に契約書で制作会社が著作権を持つことを定める場合が多いです。
そのため、映画、動画、ゲームなどの著作物を利用したい場合は、制作会社と調整しライセンス契約を締結することが多くなるでしょう。
(3)職務著作の場合
「職務著作」とは、一定の条件のもとで、従業員が作成した著作物の著作者が事業者になることをいいます。下記の条件が職務著作の条件です。
- 法人等の発意にもとづくこと
- 法人等の業務に従事する者が職務上作成するものであること
- 法人等の名義の下に公表するものであること
- 作成時における契約、就業規則その他に別段の定めがないこと
これら4つの条件を満たした場合には、たとえ従業員が著作物を生み出しても事業者が著作者となり、条件を満たさない場合には著作物を生み出した従業員が著作者となります。
そのため、特に従業員が業務を通して作成した著作物に関して、誰とライセンス契約を締結するべきなのかは、非常に重要な問題です。
条件を満たしていないにもかかわらず、事業者が著作者、著作権者であると勘違いしているケースもあるため、注意が必要です。
※職務著作について詳しく知りたい方は【従業員が生み出したものは会社のもの?職務著作の4つの要件を解説!】をご覧ください。
5 ライセンスの条件
ライセンス契約を締結する場合、単に利用を許諾するのみだけではなく、著作物を利用するにあたって条件をつけることが多いです。
契約書で合意した条件を守らなかった場合は契約違反となり、損害賠償を請求される可能性があります。
そのため、契約締結前に、ライセンサーは本当にその条件で著作物を利用させてよいか、ライセンシーは設定された条件の範囲内でやりたかったことができるかを確認しましょう。
そのうえで、契約締結後も、条件に違反しないよう注意しなければいけません。
著作権のライセンス契約における主な条件として、下記3つについて説明します。
- 著作物を使用できる地域や使用方法の限定
- 独占か、非独占か
- サブライセンス
(1)著作物を使用できる地域や使用方法の限定
この限定はライセンシーに対して設定されるものです。
著作物を利用できる条件や範囲は確認しておきましょう。
以下のような項目は気を付けるべきポイントです。
- 使用できる地域・期間の限定
- 使用できる範囲の限定
- 公表前の事前確認
- 著作物の改変
①使用できる地域・期間の限定
たとえば、契約書において以下のように著作物を利用できる地域や期間を限定した場合、その条件を守る必要があります。
【地域の限定の例】
- 日本国内
- 関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)
- 東京都
【期間の限定の例】
- 令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日まで
なお、契約書において利用許諾の期間が明記されていなくとも、契約期間という形で区切られている場合があります。いつまでも使い続けられると勘違いしていると、契約違反となってしまうこともあるため、ご注意ください。
②使用できる範囲の限定
ライセンサーがライセンシーに対して著作物を利用できる範囲を絞り、その範囲内の利用許諾しかださない場合があります。
たとえば、ライセンサーが事業者に対して動画をDVDで販売することを許諾する一方で、別会社に予告編の動画の作成、無償配布用のポスター・チラシなどの作成・頒布をお願いすることが決まったとします。
この事例では、事業者ができるのは動画をDVD化して複製することと、その販売のみです。DVDが売れるように動画の一場面をポスター・チラシにしたくても、著作物である動画を利用できる範囲を越えているためできないことになります。
このように、ライセンシーが求めている使い方と、ライセンサーが許諾した利用範囲が異なる場合があります。
このような場合、ライセンシーは利用範囲を越えた使い方に関して、ライセンサーから別途利用許諾を得る必要が発生してしまいます。
そのため、ライセンシーとしては今どのように使いたいかだけでなく将来的にどのように利用したいかを見越して許諾を得ておくことが大事です。再交渉の必要がなくなりスムーズに事業が行えるからです。
③公表前の事前確認
著作物を使った商品などを作成する際、公表前にライセンサーの事前確認(監修)があるかどうかを確認しておきましょう。場合によっては、公表直前だけでなく、デザイン段階から完成までの間、工程ごとのチェックや修正、再確認などを要求されることもあります。
そのため、ライセンシーは、事前確認が要求される場合は、その手間と時間がかかることを前提としたスケジュールを組まなければいけないことに注意してください。
④著作物の改変
契約次第では、著作物の改変を一切許してくれない場合もあります。なぜなら、ライセンサーが、元の著作物のブランドイメージが損なわれてしまうことを防ぎたいと考える場合があるからです。
改変が一切禁止されていると、たとえば、イラストの著作物であれば、そのサイズ変更もNGとなってしまいます。
あらかじめ著作物を利用する中で改変が予定されている場合には、著作物の改変の可否・程度が契約書でどうなっているか確認し、もし改変が禁止されているのであれば、契約締結前に交渉が必要となります。
(2)独占か、非独占か
独占・非独占は、著作物を利用するライセンシーに対する条件ではなく、著作物の利用を許諾するライセンサーに対する条件です。
ライセンスの独占・非独占とは以下のことをいいます。
- 独占⇒1社だけにライセンスを認める場合
- 非独占⇒複数の事業者にライセンスを認める場合
独占的なライセンス契約を締結することで、ライセンサーは、複数の者にライセンスを設定することができなくなり、結果として、ライセンシーは著作物を独占的に利用できるようになります。
たとえば、ある動画のDVD販売のライセンスがA社、B社両方に許諾されたとします。この場合、A社、B社の販売地域が重なっているとお互いの市場が競合してしまいます。
このような事態が起こるのを防ぐために、独占的なライセンス契約は有効です。
もっとも、本来であれば、ライセンサーは複数の事業者などにライセンスを設定し、それぞれから使用料を得ることができたはずです。
そのため、独占的なライセンス契約を締結する場合、非独占と比べて、ライセンシーが払わなければいけない使用料が高くなることが多いという点には注意が必要です。
(3)サブライセンス
「サブライセンス」とは、ライセンスの許諾を受けたライセンシーが、第三者(サブライセンシー)へさらにそのライセンスの使用について再許諾をすることです。
たとえば、下記のケースでサブライセンスが使われます。
いずれの場合も、サブライセンスの範囲やロイヤリティーについては事前にライセンサーと契約書で定めておく必要があります。
・ライセンシーがサブライセンシーとなる委託製造業者を指定し、ライセンサーに事前に許諾を得た場合
・海外企業がライセンスを持つ著作物で、日本国内の管理企業(代理店)が決まっている場合は、その代理店からのサブライセンスという形で許諾を受ける場合
・グループ全体で著作物を使うために、ホールディングスが代表でライセンス契約を結び、各グループ企業がそこからサブライセンスを受ける場合
もっとも、ライセンサーがサブライセンシーまで管理することは難しいといえます。そのため、サブライセンスが許可されることは多くありません。契約書で許されていないにもかかわらず勝手にサブライセンスを設定すれば、契約違反になるので注意しましょう。
6 表明保証
著作権のライセンス契約上での「表明保証」とは、契約を締結する際に、ライセンサー側がライセンシーに対し、契約内容について事実であることを保証する条項です。
たとえば、ライセンサーは以下の事項についてライセンシーに対して表明保証することが多いです。
- ライセンス契約を締結できる権利がある(著作権者である)こと
- 著作物が第三者の知的財産権を侵害していないこと
著作権というものは、特許権や商標権のように審査を通過して始めて権利が発生するものと違い、著作物を生み出すと自然と発生する権利です。
そのため、誰が権利者なのか、誰かの権利を侵害していないかをライセンシーは確認する術がなく、その事情を最もよく知っているのはライセンサーとなります。
以上のことから、ライセンシーにとって、安心して著作物を利用するためには、ライセンサーに表明保証してもらうのが一番となるわけです。
7 小括

社外のクリエイターが作成したイラストや動画などの著作物を利用するためには、著作権譲渡契約だけでなく、ライセンス契約を締結するという選択肢があります。
ライセンス契約は、ライセンシーは利用許諾を得た範囲内であれば自由に使うことができますし、ライセンサーもこれまでどおり著作物を利用することができる便利なものです。
もっとも、契約内容を間違えると思い通りに著作物を利用できないといったトラブルが起きやすいです。
そのため、契約締結時には、内容に問題がないかきちんと確認する必要があります。
8 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下の通りです。
- 「ライセンス契約」とは、著作権を持っている著作物の利用を他者に許諾する契約のことをいう
- ライセンスを許諾する側を「ライセンサー」、許可をもらって著作物を利用する側を「ライセンシー」という
- ライセンス契約において「誰とライセンス契約を結ぶか」「ライセンスの条件はなにか」「表明保証」は注意したい3ポイント
- 誰が著作権者になのかをはっきりさせてからライセンス契約を結ぶ
- ライセンサーもライセンシーもライセンス契約においてどのような条件があるかを確認すべきである
- ライセンシーに著作物の安全を表明するのが表明保証。著作権侵害がないこと、確実に著作権がライセンサーに存在することなどを保証するもの