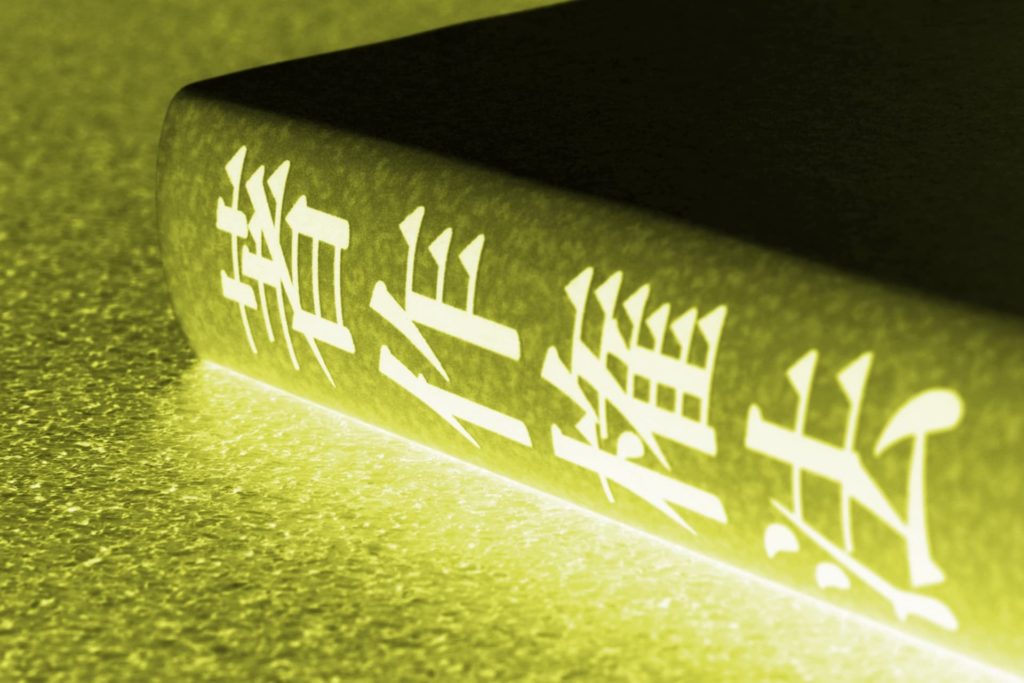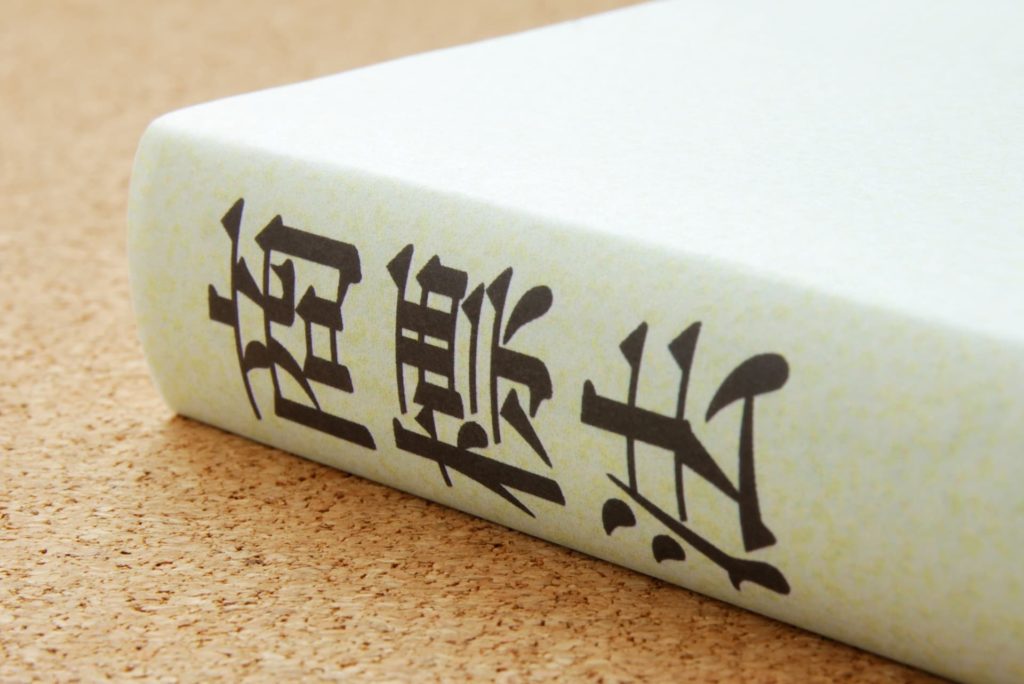はじめに
著作権を侵害されたので、侵害している相手にコンテンツ(イラスト、写真etc)の削除依頼をしたのに、何も対応してくれない……
さらに内容証明を送って、対応してくれない場合は「法的手段をとる」と再三にわたって警告したのに、無視されてしまった……
こんな場合に、ふと思うのが著作権侵害に対して刑事告訴できないか?ということではないでしょうか。
もっとも、刑事告訴をしたとしても民事での解決とは異なり、発生した被害や損害を回復できるわけではありません。
また、手続きのやり方も異なります。
この記事では
- 著作権侵害をされた場合の民事・刑事のそれぞれでできることは何か
- 相手方へ刑事罰を求める場合の方法
- 刑事告訴の手順
- 刑事告訴があった著作権侵害の事例
について弁護士が解説していきます。
1 著作権を侵害された場合何ができるのか
著作権侵害に対して行うことができる法的措置としては大きく分けて、民事・刑事の2種類があります。
(1)民事と刑事の違い
まずは、両者の違いを確認しておきましょう。
①民事とは
「民事」とは、人vs人、法人vs法人、人vs法人の金銭や契約などのトラブルを解決する手続きのことをいいます。発生したトラブルに対して話し合いや民事裁判を行い、自身の権利を守ったり、被害や損害を回復したりすることができます。
②刑事とは
「刑事」とは、国が法律に違反した者に対して、刑罰を科すことをいいます。
国vs違反者となるため、たとえ罰金を支払うことが確定したとしても、罰金は国が回収します。そのため、被害者が被害や損害を回復するためには刑事ではなく、民事で行わなければいけません。
(2)著作権侵害に対して民事でできること
著作権侵害に対して、民事でできることは、以下の4つです。
- 差止請求
- 損害賠償請求
- 不当利得の返還請求
- 名誉回復措置
民事では「2損害賠償」や「3不当利得の返還請求」のように発生した被害や損害をお金で賠償してもらうだけでなく、「1差止請求」をして現に行っている侵害行為の停止の対応やこれから被害が発生することを防ぐ対応をしてもらったり、「4名誉回復措置」として謝罪広告の掲載といった対応をしてもらったりということもできます。
※著作権侵害に対して民事でできることにを詳しく知りたい方はは「著作権を侵害してしまった・されたら?損害賠償の金額と注意点5つ!」をご参照ください。
(3)刑事上のペナルティー(刑事罰)
他方、著作権法には、著作権侵害に対する刑事上のペナルティー(罰則)も定められています。そして、著作権という権利は、複数の権利をまとめた「権利の束」であるため、侵害している権利に応じたペナルティーを科せられることになります。
例えば、著作権・出版権・著作隣接権を侵害した場合には、
- 最大10年の懲役
- 最大1000万円の罰金のいずれか、またはその両方
を科せられる可能性があります。
違法なプログラムの複製物を使用した場合や著作者人格権を侵害をした場合などには、
- 最大5年の懲役
- 最大500万円の罰金
のいずれか、またはその両方を科せられる可能性があります。
加えて、業務で従業員が著作権の侵害を行った場合には、侵害した従業員に加えて、その法人に対しても、
- 最大3億円
の罰金を科せられる可能性があります。
このように、民事と刑事で著作権を侵害している者に請求できる内容や科せられるペナルティが異なります。時間をかけて生み出した著作物を勝手に使用されてしまった場合など、民事だけでなく、刑事でも責任追及したい方も多くいらっしゃることでしょう。では、民事上の責任追及とは別に、刑事上のペナルティー(刑事罰)を負わせるためには、何をしなければいけないのでしょうか。
2 刑事罰を負わせるためには何をしなければいけないのか
著作権侵害に対して刑事罰を負わせるためには、被害者が積極的に行動しなければいけません。
(1)待っていても警察が動いてくれるわけではない
著作権侵害は、原則として「親告罪」となっています。
「親告罪」とは、被害者が告訴しなければ、起訴することができない罪のことをいいます。起訴されなければ、刑事裁判が開かれることもありません。刑事裁判が開かれないということは、刑事としてのペナルティー(刑事罰)も負わないということになります。
起訴するかどうかは、警察や検察などの捜査機関の捜査結果次第のため、著作権侵害があった場合は、まずは被害者自らが捜査機関に告訴して、捜査機関を動かさなければいけません。
つまり、被害者が黙っていても侵害があれば勝手に捜査機関がそれを見つけて動いてくれるわけではないのです。
(2)告訴?告発?被害届?
「告訴」とよく似た言葉に、「告発」と「被害届」があります。
どれも同じでは?と思っている方もいらっしゃるでしょう。
これらは、
- 警察や検察などの捜査機関に提出すること
- 提出された書面を受理するかしないかは捜査機関が判断すること
- 捜査開始のきっかけになること
という点で共通していますが、全く異なるもののため注意が必要です。
①告訴とは
「告訴(刑事告訴)」とは、被害者(その家族や遺族を含む)が警察や検察などの捜査機関に犯罪の被害を受けたことを知らせ、加害者への処罰を求める意思を表示することをいいます。
②告発とは
「告発」とは、告訴と同じく、捜査機関に犯罪の被害を受けたことを知らせ、加害者への処罰を求める意思を表示することをいいます。告訴との違いは、誰でも行うことができるという点です。つまり、告発を使えば、被害者でなくとも、処罰を求めることができます。
③被害届とは
「被害届」とは、「犯罪に巻き込まれた」ということを警察に知らせるものです。あくまでも被害があった事実を伝えるものであり、加害者への処罰を求める意思までは含まれていません。
そして、被害届をだしたとしても、必ず捜査が開始されるというわけではありません。告訴や告発のように、書類や証拠を検察に事件を送って(送検)、起訴に値するかどうか判断されることが義務付けられていない点に注意が必要です。
(3)著作権侵害に対しては告訴を
親告罪で起訴するためには、告訴がなされていることが条件となっています。
また、親告罪については、告訴のみが認められ、告発はできないことになっています。
そのため、原則として親告罪とされている著作権侵害については、被害者の告訴が必要になります。
著作権侵害のうち例外的に非親告罪となっている行為の例としては以下が挙げられます。
- 技術的保護手段(コピーガードなどの)の回避プログラムの提供
- 技術的回避手段の回避行為
- 著作者の死亡後の著作者人格権侵害行為
- 引用の際の出所明示義務違反
- 利益を得るために海賊版などをネット配信する行為
これらの行為を発見した際は、被害者でなくとも告発ができるというわけです。
では、著作権侵害に対して、刑事上のペナルティーを科すためには、刑事告訴が必要だとして、それはどのような手順で行えばいいのでしょうか。
3 刑事告訴の手順
刑事告訴は処罰を求めるための手続きになります。
誰が、どのような手順で進めていけばいいのか確認していきましょう。
(1)刑事告訴ができるのは誰か
刑事告訴ができるのは、原則として被害にあった本人やその家族や遺族です。著作権侵害の被害者であれば、著作物を生み出した著作者または著作物に対して権利を持つ著作権者などが該当するでしょう。
また、被害にあった者の依頼で、弁護士などの専門家が代わりに手続きを進めることもできます。なお、警察に対する告訴手続きは行政書士の職務、検察に対する告訴手続きは司法書士の職務とされていますが、弁護士であれば、警察・検察にかかわらず告訴手続きを進めることができるため、依頼する際には、弁護士に依頼したほうがいいでしょう。
(2)刑事告訴の流れ
刑事告訴は、
- 告訴状の作成
- 警察署や検察庁に提出
という流れになっています。
①告訴状の作成
告訴状に記載すべき内容は以下の通りです。
- 作成年月日
- 提出先(管轄の警察署長名)
- 告訴人(法人の場合は法人名、代表者名および肩書、氏名自著、法人代表印、個人の場合は住所と氏名)
- 被告訴人の住所、氏名等(不明の場合、加害者について判明している情報の詳細)
- 法律上どのような罪に当たるのか
- 被害にあった日時、状況、場所など
- トラブルの経緯と、それによる不利益の内容
- どのような証拠があるか
- その他被害状況を示す写真など関連資料
特に「法律上どのような罪に当たるのか」は、犯罪の成立要件(構成要件)として法律で定められている条件の全てに該当していることを示さなければいけません。
たとえば、著作権侵害の場合には
- 著作物であること
- 著作権があること
- 著作権が及ぶ範囲で利用されていること(侵害されていること)
- 著作物を利用する権限がないこと
などを示さないといけません。
もっとも、一つでも条件を満たしていないと、犯罪には当たらないとして、捜査機関で受理してもらえない可能性が高くなります。
そのため、書面の作成については、弁護士などの専門家に依頼したほうがいいでしょう。
②告訴状の提出先
告訴状の提出先は、警察署や検察庁の窓口です。わざわざ検察庁まで行くのは大変なため、数の多い警察署への提出のほうがいいでしょう。
また、警察署には、本来、管轄というものがありますが、告訴や告発については、管轄外のものであるかどうかを問わず、受理しなければいけないとされています。
そのため、管轄がどこかということは気にせず、自身が提出しやすい警察署を選択してかまいません。
(3)告訴状を提出すれば必ず動いてくれるのか
捜査機関は告訴状を提出されたら、原則として受理しなければなりません。
もっとも、原則と説明したとおり、どんな場合でも必ず受理してくれるわけではありません。
なかでも、記載内容に不備があることを理由に受理されないケースが多くみられます。
下記に当てはまってしまった場合は、記載内容を見直してみてください。
- 記載事実が不明確である
- 記載事実が特定されないもの
- 記載内容から犯罪が成立しないことが明白である
- すでに公訴できる期間(公訴時効)を過ぎている
特に「加害者がわからない」「法的に犯罪と見なせる要素がない(有罪となる可能性がない)」と判断されると、受理は難しくなります。
なるべく受理してもらうためにも、情報を整理したり証拠を収集したりするとともに弁護士などの専門家に依頼し、告訴状を作成するという手段を取るといいでしょう。
このように、告訴状の作成のハードルは、意外と高いです。
では、著作権侵害をされてしまった場合、刑事告訴はどのタイミングで行うべきなのでしょうか。実際に刑事告訴がなされた事例をもとに確認していきましょう。
4 いきなり刑事告訴をしてもいいのか?『ハイスコアガール』事件に学ぶ
(1)『ハイスコアガール』の著作権侵害と刑事告訴
事業者の著作権侵害で刑事告訴まで至った例として、「『ハイスコアガール』事件」(2014年)を例に
- 事件の概要
- 侵害から解決までの経緯
- 事例からみる解決方法
を見てみましょう。
①事件の概要
『ドラゴンクエスト』や『ファイナルファンタジー』などの人気ゲームソフトを手掛けるスクウェア・エニックスが出版する漫画『ハイスコアガール』で、著作権を持たない他社のゲームキャラクターを無断使用していたことが発覚しました。
このうち1社のSNKプレイモア(現SNK)がスクエニに対し、著作権侵害として刑事告訴に踏み切った事件です。
②侵害から解決までの経緯
民事と刑事も区別して経緯を説明します。
-
Ⅰ 著作権侵害の発覚(2013年)
漫画のアニメ化の企画段階で、制作会社がゲーム会社に許諾の確認をしたことで著作権侵害が発覚しました。
↓
Ⅱ 刑事告訴(2014年5月:刑事)
SNKプレイモアがスクエニに刑事告訴を行いました。刑事告訴に至ったのは、SNKプレイモアがスクエニに電子書籍・単行本・月刊誌などの販売を即時停止するよう、再三にわたって申し入れていたにもかかわらず、何の誠意ある対応もしてもらえなかったことを理由としています。
↓
Ⅲ スクエニ本社の家宅捜索(2014年8月:刑事)
スクエニ本社が、大阪府警から著作権法違反で家宅捜索を受ける
↓
Ⅳ 著作権を侵害していないことの確認を求める訴訟(2014年10月:民事)
スクエニは、刑事告訴されたことを受けて、民事で著作権を侵害していないことの確認を求める(債務不存在確認訴訟)を提起しました。こちらは、刑事事件そのものに対する対応ではなく、著作権侵害に基づく損害賠償請求を支払わなくてよくするために行ったものと考えられます。
↓
Ⅴ 漫画作者とスクエニ社員が書類送検(2014年11月:刑事)
「書類送検」とは、犯罪を行った疑いのある者を逮捕などの身体拘束を行わずに、警察から検察へ事件を送検することをいいます。告訴の場合、送検は義務となっているため、これは、告訴した時点で必ず発生するものです。今回は、大阪府警から大阪地検特捜部に送検されました。
↓
Ⅵ 出版差止を求める訴訟(2015年3月:民事)
SNKプレイモアは、債務不存在確認訴訟が提起されたことを受けて、漫画なとの出版物の出版差止を求める著作権侵害行為差止請求訴訟を提起しました。
↓
Ⅶ 和解と不起訴(2015年8月:民事・刑事)
スクエニ、SNKプレイモアおよび同社の大株主のLedo Millennium社との間で和解が成立し、これまでに出されていた刑事告訴、民事訴訟を取り下げることを合意しました。これを受けて、大阪地検特捜部は不起訴とすることを決めました。不起訴となった結果、刑事裁判となることはなくなり、刑事上のペナルティー(刑事罰)を漫画作者やスクエニが負うことはなくなりました。
③事例から見る解決方法
この事例ではまず、著作権侵害を受けた側であるSNKプレイモアが、侵害した側のスクエニに対して、いきなり刑事告訴をしたわけではありません。スクエニが、再三の出版差止の請求に対して適切な対応をしてくれなかったことが理由です。
このことからも、著作権侵害に対する対応順としては、
- 裁判外での解決
- 裁判での解決
がよいでしょう。
また、民事と刑事とどちらで解決を図るかはケースバイケースです。
民事請求で相手側企業の対応が適切ではなかった場合、今回の事例のように刑事告訴をすると対応が変わる場合もあります。
(2)刑事告訴の期限
もっとも、刑事告訴はいつでもできるわけではありません。
被害にあった者が犯人を知ってから6ヶ月を経過してしまうと、告訴をすることができなくなります。
そのため、注意したいのは、被害にあって「まずは金銭的な被害回復を」と民事請求を優先している間に、刑事告訴ができる期限を過ぎてしまう場合があることです。期限に注意しましょう。
(3)対応の相談は専門家へ
このように、民事請求と刑事告訴は対応すべき内容やタイミングが異なります。著作権侵害の規模や中身によってもどちらが先が有効かは正解がありません。
このため、著作権侵害を認識した時点で、早めに弁護士に相談をした方がいいでしょう。
5 小括
民事と刑事は異なるものです。著作権侵害に対して「罰を与えたい」のか「被害を回復したいのか」で、刑事を選択すべきか民事を選択すべきかが変わります。
また、警察などに書面を提出する際も、一歩間違えると望んでいた結果を得られないことが多々あります。
弁護士などの専門家を入れて対応方法を十分に検討するといいでしょう。
6 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下の通りです。
- 著作権侵害を受けたら、民事と刑事でできることが異なる
- 民事は金銭的賠償、刑事は「他人に刑事罰を与える」ものである
- 著作権侵害に対して民事でできることは、①差止請求、②損害賠償請求、③不当利得の返還請求、④名誉回復措置の4つがある
- 著作権は権利の束のため、権利に応じて刑事上のペナルティ(刑事罰)が異なる
- 著作権侵害は原則として親告罪のため、被害者からの告訴がなければ、起訴されない
- 著作権侵害に対する対応順は、①裁判外での解決、②裁判での解決がよい