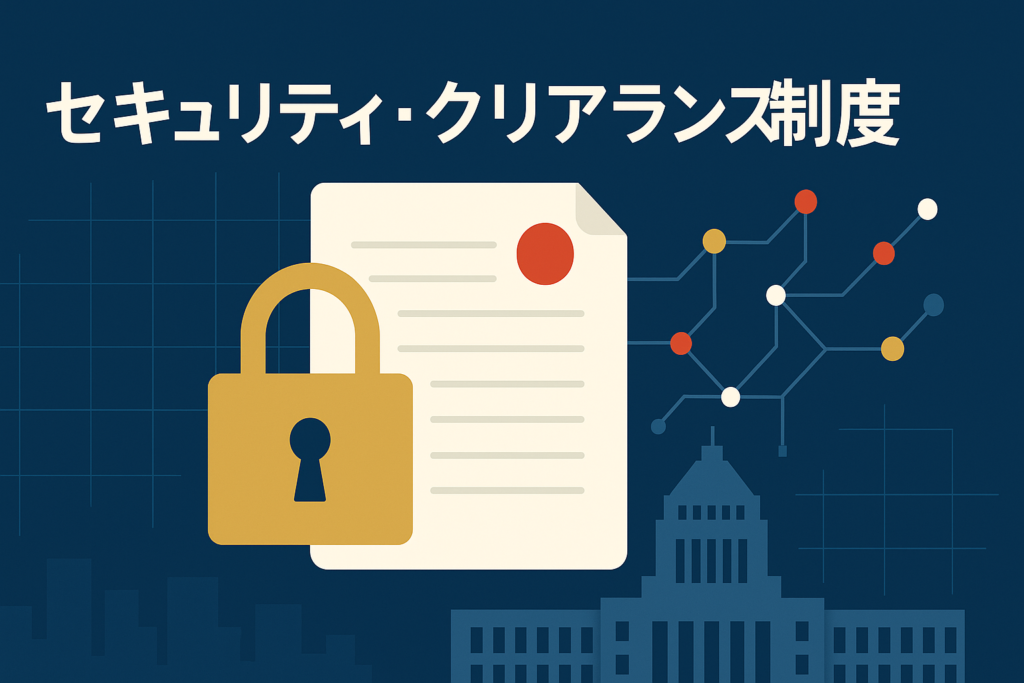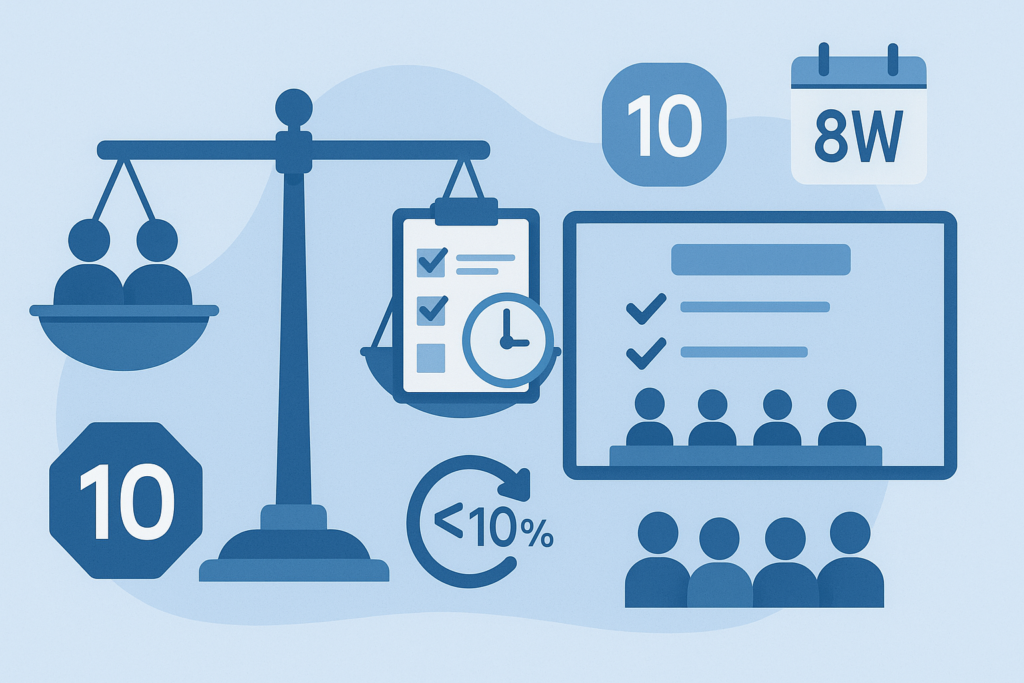はじめに
米国のフードデリバリーサービス「ウーバー・イーツ」(Uber Eats)がサービスエリアを広げています。都市部では、同社のロゴが入ったバッグを背負った配達パートナーの姿を見かけることも多くなりました。
新型コロナウイルス感染症の拡大で、極力自粛することが推奨されるなか、ウーバー・イーツのような料理のデリバリーサービスがいっそう注目を集めるとともに、その需要も飛躍的に高まりました。
また、コロナ禍で仕事が減ったことにより、余った時間を利用して単発の仕事を請け負う「ギグワーク」を希望する人が増加しました。このことが、配達パートナーの拡充にも繋がっているものとみられます。
特に、コロナ禍のような状況では、フードデリバリーサービスの役割りが重要になってきますが、フードデリバリーサービスとは、そもそもどのようなビジネスモデルになっているのでしょうか。
今回は、ウーバー・イーツを例に取り、そのビジネスモデルと注意すべき法律について弁護士が解説します。
1 ウーバー・イーツのサービスの流れ

「ウーバー・イーツ」(Uber Eats)は、米国発祥のライドシェアサービス「ウーバー」(Uber)が手掛ける、飲食宅配代行サービスです。2020年8月時点で、日本国内32の都市でサービスを利用することが可能です。
ウーバー・イーツは、以下のような流れでサービスが提供されます。
このように、ウーバー・イーツを利用すると、
- ユーザーから注文を受ける
- 飲食店に発注する
- リクエストを受け取った配達パートナーが飲食店からピックアップする
- ユーザーに届ける
↓
↓
↓
といった流れで、ウーバー・イーツを介して、ユーザーに品物が届けられることになります。
ウーバー・イーツには、飲食店(加盟店)から一定の手数料が支払われ、配達パートナーには、ウーバー・イーツから一定の報酬が支払われるという仕組みを採っています。
2 ウーバー・イーツのメリット・デメリット
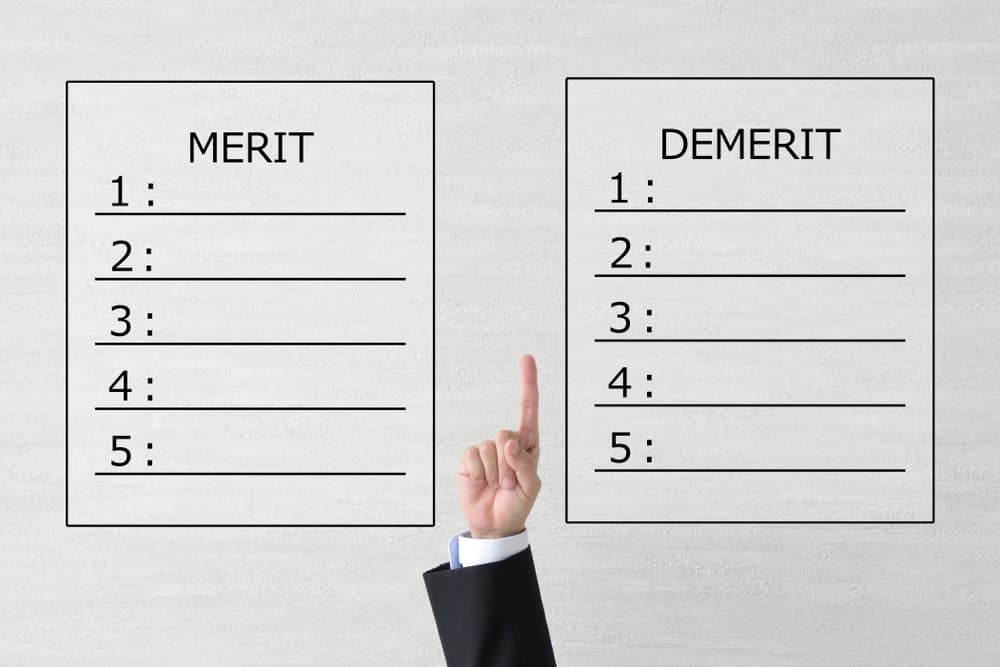
ウーバー・イーツには、飲食店(加盟店)、ユーザー(顧客)、配達スタッフのそれぞれにおいて、以下のようなメリット・デメリットがあります。
(1)飲食店(加盟店)
ウーバーイーツでは、初期費用や月額の固定費用がかからないため、飲食店(加盟店)は、コストをかけずにすぐにデリバリーサービスを始めることができるというメリットがあります。
また、それまではお店を知らなかった人に、ウーバーイーツをきっかけとして、お店の存在を知ってもらえる可能性もあり、顧客の獲得に繋がる可能性があります。
もっとも、加盟店はウーバー・イーツに対し、ウーバー・イーツを利用して売り上げた総額の35%にあたる金額を手数料として支払わなければなりません。
そのため、飲食店は、その点を踏まえた価格を設定する必要があります。
また、ユーザーから注文を受けた料理は、配達パートナーが配達することになるため、場合によっては、料理が冷めていたり、崩れているような状態でユーザーに届けられることも想定されます。
このような場合に、ユーザーとの間でトラブルになったり、信用力を低下させる要因にもなるおそれがあります。
(2)ユーザー(顧客)
何よりも、アプリ一つで注文した料理を自宅などに届けてくれる気軽さは、ユーザーにとって大きなメリットといえます。
また、これまでなかなか足を運ぶことがなかった飲食店の料理を自宅やオフィス等で気軽に楽しむことができます。
今回のコロナ禍のような状況では、なるべく外出を控えたいというユーザーが多くなりますが、そのようなユーザーの需要にもマッチしています。
もっとも、注文価格に配達料や包装料が含まれているため、店舗で飲食するよりも割高になるというデメリットがあります。
また、場合によっては、届いた時点で料理が冷めていたり、盛り付けが崩れていることも大いに想定できるところです。
(3)配達パートナー
空いた時間に単発の仕事をこなす「ギグワーク」が浸透してきたことにより、働く場が拡大しました。ニーズの高まりを追い風に、都市部などでも「配達パートナー」と呼ばれるスタッフを見かけることが増えてきました。働く時間や件数を自分で選べるほか、週単位で配送料を受け取れることもメリットの一つといえます。
もっとも、配達パートナー同士で、注文を獲得するために競争が生まれてしまうこと、自転車やスマホなどにかかる初期費用は自己負担であること、配送中に事故やけがを負ったような場合の補償がまだまだ十分ではないといったことがデメリットとして挙げられます。
3 「出前館」との比較

国内には、これまでにも、飲食店の料理の配達を請け負うサービスとして「出前館」(1999年設立)がありました。
出前館は、以下のような流れでサービスが提供されます。
このように、出前館を利用すると、
- ユーザーから注文を受ける
- 出前館が飲食店と配達拠点に注文情報を送る
- 配達代行スタッフが飲食店からピックアップする
- 配達代行スタッフがユーザーに届ける
↓
↓
↓
といった流れで、出前館を介して、ユーザーに品物が届けられることになります。
一見すると、ウーバー・イーツが提供するサービスと同じようにも思えます。
もっとも、出前館とウーバー・イーツでは、主に配達をするスタッフに違いがあります。出前館において、料理を配達するデリバリークルーは出前館から雇用されているのに対し、ウーバー・イーツで料理を配達する配達パートナーは、ウーバー・イーツから雇用されているわけではなく、あくまで個人事業主です。
なお、出前館では2020年5月より、配達パートナーを募集し始めたため、今後は、従来通り出前館からデリバリークルーとして雇用されるか、もしくは、ウーバー・イーツのように、配達パートナーとして業務委託を受けるか、2つの方法から選択することが可能になります。
4 ウーバー・イーツで問題となる法律
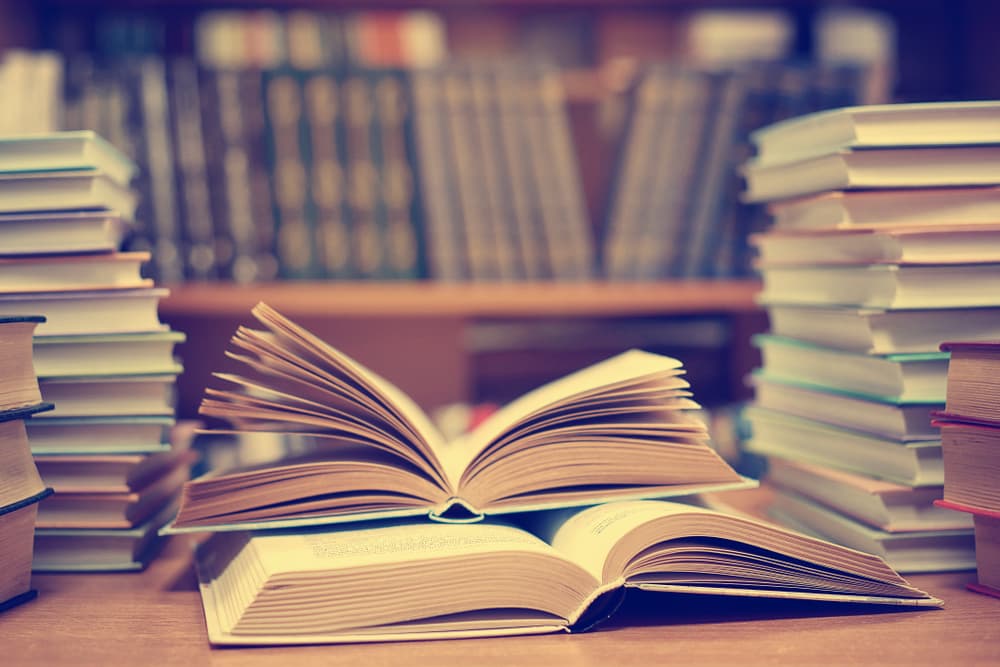
ウーバー・イーツのようなビジネスモデルを採った場合、どのような法律による規制が関係してくるのでしょうか。
このようなサービスに関係する主な法律は、以下の4つです。
- 貨物自動車運送事業法
- 食品衛生法
- 郵便法
- 労働基準法・労災保険法
(1)貨物自動車運送事業法
「貨物自動車運送事業法」は、貨物自動車を使った運送事業に関し、さまざまなルールが定められた法律です。
貨物自動車運送事業は、大別して、一般貨物自動車運送事業と特定貨物自動車運送事業、そして貨物軽自動車運送事業の3つに分かれます。
このうち、一般貨物自動車運送事業を行う場合には、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
ウーバー・イーツにおいて、配達パートナーは、主に、自転車や原動機付自転車を用いて、料理をユーザーの元に届けます。
そこで、ウーバー・イーツが一般貨物自動車運送事業にあたるかどうかが問題となります。
「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、三輪以上の自動車を使って貨物を運送する事業を指します。
この点、ウーバー・イーツの配達パートナーが使う自転車や原動機付自転車は、三輪以上の自動車にあたりません。
仮に、三輪以上の自動車を使って料理を配送するサービスであれば、国の許可を受ける必要がありますが、自転車や原動機付自転車であれば許可は必要ありません。
このように、ウーバー・イーツは、三輪以上の自動車を配達手段としないかぎり、一般貨物自動車運送事業にあたらないため、貨物自動車運送事業法との関係で問題となることはありません。
(2)食品衛生法
「食品衛生法」は、食品の安全性を確保するなどして、国民の健康を保護することを目的とした法律です。
仮に、ウーバー・イーツを使って届けられた料理により、食中毒などの健康被害が起きた場合、責任の所在はどこにあるのでしょうか。
食品衛生法上、飲食店は、食品の調理や販売、提供、運搬などについて、自らの責任でそれらの安全性を確保するために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
ウーバー・イーツにおいて、実際に料理を運ぶのは、配達パートナーですが、配達パートナーは飲食店より配送の委託を受けているに過ぎません。
料理の品質などに係る責任は、あくまで飲食店側にあり、食中毒などの健康被害が起きた場合には、原則として、飲食店が責任を負わなければならない可能性が高いといえます。
(3)郵便法
「郵便法」は、多くの人にできるだけ安価で郵便サービスを提供するために、さまざまなルールを定めた法律です。
郵便法では、日本郵便社以外の者が郵便の業務を行ってはならないとされています。
そのため、信書(特定の受取人に対し、差出人の意思や事実を表示・通知する文書)を送達するようなことを、日本郵便社以外の者が事業として行うこともできません。
この点、ウーバー・イーツにおける配達パートナーは、主に、飲食店の料理をユーザーに届けることを内容としていますが、この点が郵便法との関係で問題となるのでしょうか。
上で見たように、郵便法との関係で問題となるのは、あくまで、日本郵便社以外の者が信書を送達するなどの郵便業務を行った場合です。
そのため、飲食店の料理をユーザーに届ける配達パートナーが、食品衛生法との関係で問題となることはありません。
(4)労働基準法・労災保険法
「労働基準法(労基法)」は、労働者において最低限の生活が保障されるよう、労働者と使用者が守るべきルールを定めた法律です。
労基法では、労働条件の決定や男女同一賃金の原則、強制労働の禁止に関する規定が定められています。
そこで、ウーバー・イーツと配達パートナーの関係において、労基法が適用されるかどうかが問題となります。
この点、労基法は、使用者による恣意的な扱いから、労働者を保護するための法律です。そのため、原則として、雇用関係に見られるように、使用者と労働者との間に一定の従属性が認められるような場合、労基法が適用されることになります。
この点、ウーバー・イーツにおける配達パートナーは「個人事業主」であるため、ウーバー・イーツとの間に雇用関係はなく、何らかの従属性も認められません。
そのため、配達パートナーは労働基準法の適用対象から外れることになります。
また、配達パートナーは、個人事業主であるため、労災保険法の適用を受けません。
「労災保険法」とは、通勤途中などのように業務に起因して障害を負ったり、死亡したような場合に、必要な保険給付を行うなどして、労働者を保護することを目的とした法律です。
配達パートナーは、労災保険法の適用を受けないため、仮に、配達途中で交通事故に遭って怪我をしたとしても、そこに対して補償を受けることはできません。
なお、2019年10月より、ウーバー・イーツでは、一定の補償制度が追加されています。
具体的には、配達パートナーが配達のリクエストを受けてから配達が完了するまでの間に発生した事故に対して適用され、25万円を上限に治療費が補償されるなど、一定の範囲で配達パートナーに生じた損害が補償されることになっています。
5 罰則
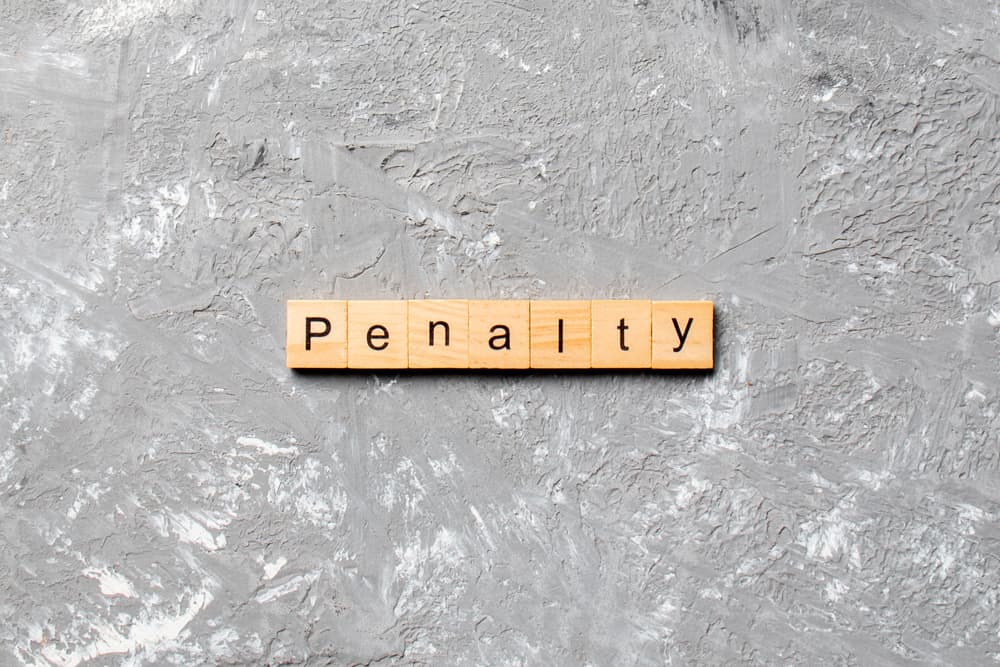
ウーバー・イーツに見るビジネスモデルは、以上に見てきたような法律が問題となりうるため、事業を始めようとする際には、十分に確認しておくことが大切です。
以下のように、罰則を科される可能性もあるため、注意が必要です。
(1)貨物自動車運送事業法
ウーバー・イーツにおける配達パートナーは、主に、自転車または原動機付自転車を使って配達を行っているため、この限りでは、問題となることはありません。
ですが、三輪以上の自動車を使って料理を配達する場合は、先に見たように、「一般貨物自動車運送事業」にあたるため、国土交通大臣の許可が必要です。
にもかかわらず、無許可で一般貨物自動車運送事業を経営した場合は、
- 最大3年の懲役
- 最大300万円の罰金
のいずれか、または両方を科される可能性があります。
また、法人である場合には、違反行為者とは別に、法人に対しても、
- 最大300万円の罰金
が科される可能性があります。
(2)郵便法
仮に、ウーバー・イーツが、料理以外にも、信書の送達といった郵便業務にまでサービスの範囲を拡大した場合、罰則を科される可能性があります。
先に見たように、郵便業務を行うことができるのは、原則として日本郵政のみです。
にもかかわらず、これに違反した場合、
- 最大3年の懲役
- 最大300万円の罰金
のいずれかを科される可能性があります。
また、法人である場合には、違反行為者とは別に、法人に対しても、
- 最大300万円の罰金
が科される可能性があります。
6 小括

今般の新型コロナウイルス感染症の流行は、ウーバー・イーツのようなサービスがいかに重要かということを示した形になりました。
ウーバー・イーツに倣って、同じようなビジネスモデルで事業を展開する場合、確認すべきいくつかの法律があります。
自社が構築したビジネスモデルと照らし合わせ、法的に問題ないかをきちんと確認したうえで、適切にサービスを運営していきましょう。
7 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下の通りです。
- ウーバー・イーツは、「ギグワーク」の希望者が増えたことなどで需要を伸ばしている
- 「出前館」と「ウーバー・イーツ」との大きな違いは、主に、配達スタッフとの関係である
- ウーバー・イーツの配達スタッフは、「個人事業主」として配達を請け負っている
- ウーバー・イーツとの関係で問題となりうる法律には、①貨物自動車運送事業法、②食品衛生法、③郵便法、④労基法・労災保険法がある
- 無許可で一般貨物自動車運送を経営した場合、①最大3年の懲役、②最大300万円の罰金のいずれか、または両方を科される可能性がある
- 郵便法に違反した場合、①最大3年の懲役、②最大300万円の罰金のいずれかを科される可能性がある