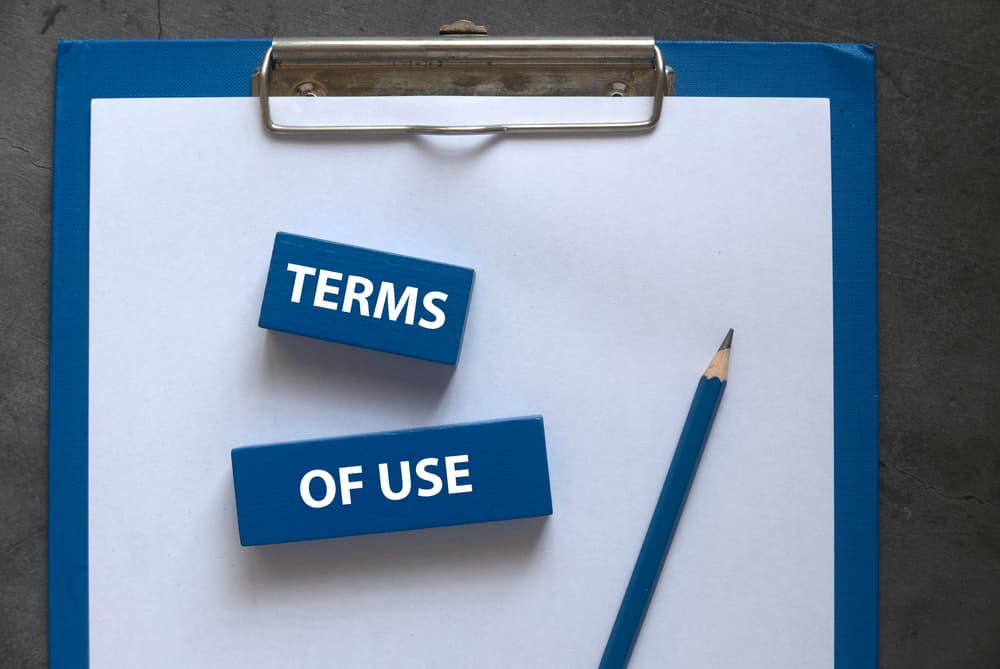はじめに
Webサービスなどを運営する場合には、必ずといっていいほど「利用規約」が必要になります。サービスを利用しようとするユーザーが利用規約に同意することで、利用規約で定められている内容が運営者とユーザーとの間のルールになるわけです。
もっとも、利用規約において、運営者に一方的に有利であったり、ユーザーの利益を一方的に害するような条項が盛り込まれている場合、その条項については、ユーザーの同意がなかったものとみなされる可能性があります。
言い換えれば、そのような条項は、ユーザーとの間でルールとして機能しなくなるということです。
そのため、利用規約を作成する際には、事業者・ユーザー間のバランスも念頭に置いておかなければなりません。
そこで今回は、利用規約に対する同意の有効性を中心に、弁護士がわかりやすく解説します。
1 ユーザーの同意がなかったものとみなされるケース

インターネット上でよく見かける「利用規約」ですが、2020年3月以前には、この利用規約を直接規制する法律はありませんでした。
一般的に、利用規約は、ユーザーがその内容に同意することで、一定の拘束力が生じますが、民法が改正されたことにより、一定の内容が含まれている利用規約については、その部分につきユーザーの同意がなかったものとして扱われるようになりました。
具体的には、改正民法により増設された「定型約款」というルールが、このことについて定めています。
2 定型約款とは

「定型約款」とは、以下の条件を満たすものをいいます。
- 特定の者が不特定多数の者を相手方とする取引である
- 内容の全部または一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なものである(定型取引)
言い換えれば、定型取引において、契約の内容とするために、その特定の者が準備した条項の総体を「定型約款」といいます。
この点、アプリやWebサービスなどによく見られる利用規約は、不特定多数の者を相手方とする定型取引といえるため、そのほとんどが定型約款にあたります。
このように、多くの利用規約は定型約款にあたることになりますが、定型約款では、
-
ⅰ)不利益条項
ⅱ)不意打ち条項
という2つの条項を入れることが禁止されています。
利用規約において、これらの条項が入っていると、その条項については、ユーザーの同意がなかったものとみなされます。
ⅰ)不利益条項が入っているケース
「不利益条項」とは、以下のような内容を含む条項をいいます。
- ユーザーの権利を制限するもの
- ユーザーの義務を加重するもの
これらの条項は、ユーザーの利益を一方的に害する内容であるため、不利益条項にあたります。仮に、これらの条項を設けていたとしても、その条項についてはユーザーの同意がなかったものとみなされます。
たとえば、解約時に請求する違約金の額が不当に高額であったり、責任の所在を問わずユーザーが事業者に損害賠償請求をすることを許さないといった内容を含む条項は、不利益条項となる可能性があります。
ⅱ)不意打ち条項
「不意打ち条項」とは、利用者にとって、通常では予見できない内容などが含まれた条項のことをいいます。
たとえば、サービスとは無関係の商品を抱き合わせで購入させられるような内容を含む条項は、不意打ち条項にあたります。
利用規約において、不意打ち条項が盛り込まれている場合には、その条項についてはユーザーの同意がなかったものとみなされます。
以上のように、改正民法により増設された「定型約款」のルールは、不当な条項からユーザーを保護することを目的としています。多くの利用規約が定型約款にあたると考えられるため、事業者が遵守すべきルールということになります。
※定型約款について詳しく知りたい方は、「民法改正で利用規約・約款の何が変わる?定型約款3つのルールを解説」をご覧ください。
3 ユーザーの同意が無効となるケース

改正民法が定める「定型約款」のほかにも、別の法律を根拠として、ユーザーの同意が無効となる場合があります。
たとえば、サイト運営者が責任を負いたくないがために、利用規約において、「一切責任を負わない」といった内容の条項を設けているとしましょう。
このような条項を含む利用規約について、ユーザーが同意をすると、サイト運営者は本当に一切の責任を免除されることになるのでしょうか。
(1)ユーザーの保護
ユーザーと事業者とを比較すると、情報の質や量、交渉力などにおいて大きな格差があることが一般的です。そのため、ユーザーが一方的に不利益を受けることがないよう、ユーザーを保護することが必要になってきます。
このような趣旨を踏まえた法律が「消費者契約法」という法律です。
利用規約は、ユーザーと事業者が締結する契約ともいえるため、消費者契約法が適用されることになります。
消費者契約法上、次のような条項は、ユーザーの利益を一方的に害するものとして、無効となります。
- 解除権を放棄させる条項
- 損害賠償責任を免除する条項
- 損害賠償額を予定する条項
①解除権を放棄させる条項
事業者の債務不履行に起因して発生したユーザーの解除権を放棄させ、また、ユーザーに解除権が発生しているかどうかの決定権を事業者に与えることを内容とする条項は無効です。
②損害賠償責任を免除する条項
事業者による債務不履行や不法行為に起因して発生したユーザーの損害を賠償する責任の全部・一部を免除すること、また、責任の限度の決定権を事業者に与えることを内容とする条項は無効です。
③損害賠償額を予定する条項
解除に伴う損害賠償額を予定したり、違約金を定める条項であって、これらの金額が平均的な額を超える場合には、その超える部分については無効となります。
また、ユーザーが支払期日までに支払わない場合の損害賠償額を予定したり、違約金を定める条項であって、これらの金額が通常考えられる額を超える場合には、その超える部分については無効となります。
このように、利用規約には消費者契約法が適用されるため、ユーザーの利益を一方的に害するような条項、事業者に一方的に有利となるような条項は無効となる可能性があります。
(2)事例紹介
ここで、利用規約の条項が消費者契約法との関係で問題となった実際の事例について、見ていきたいと思います。
-
【ファーストサーバ事件】
2012年6月、ファーストサーバ(レンタルサーバ事業者)が提供するサービスにおいて発生した障害により、大量の顧客データが消失し、多くの利用者が損害を被りました
この事例において、ファーストサーバは利用規約の中で、以下のような免責規定を設けていました。
- 当社はお客様に対し、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の種別を問わず、当社の故意または重過失による場合にのみ損害賠償責任を負うものとします
- 利用契約に関する損害賠償額は、当該損害の原因となる事由が生じた月を含めた過去12ヶ月間を最大期間とし、当該期間における本サービスの利用料金として現に当社に支払った額を上限とします
これによれば、ファーストサーバは、自社に故意または重過失がある場合にかぎり、損害賠償責任を負うことになっており、実際に支払う賠償額は、過去12ヶ月分を上限として利用者がそれまでに支払った額となっています。
「故意または重過失がある場合」に限定していることや、損害賠償額に上限を設けていることからも、同社の免責規定は、損害賠償責任を一部免除することを内容としているといえます。
そのため、ファーストサーバが提供するサービスが、一般消費者を対象としているものであれば、この免責規定は、消費者契約法により無効になる可能性があります。
ですが、ファーストサーバが提供するサービスは、事業者を対象としているものと考えられ、この場合において、上のような免責規定が有効かどうかは、裁判上も明確な考え方が確立されていないのが現状です。
4 利用規約の変更

Webサイトを開設して利用規約を置いた後も、法令が変わったり、経営環境や社会情勢が変化するなどして、利用規約を変更する必要が生じることがあります。
変更後の利用規約をユーザーに有効に適用するための方法の一つに、再度同意を得るという方法があります。
たとえば、
- チェックボックスにより同意を得る
- 同意の機能をもたせる他のボタンを設ける
- みなし同意
ここで注意しなければならないのが「③みなし同意」による方法です。
「みなし同意」とは、ユーザーにおいて一定の条件を満たすと、利用規約に同意したものとみなすことをいいます。
具体的には、「・・・を満たした場合に、利用規約に同意したものとみなす。」といった内容で定められることが一般的です。
このように、みなし同意は、利用規約の内容を表示しないかわりに、上記のような文言を置き、ユーザーから同意を得たものとみなす方法ですが、このような方法は、不適切な同意取得にあたる可能性が高いと考えられています。
ここでいう「不適切な同意取得」とは、以下のような場合をいいます。
-
ⅰ)サービスを利用する際に利用規約への同意が求められていない
ⅱ)見つけにくい場所に利用規約が載せられている
みなし同意による方法は、みなし同意の文言があるのみで、利用規約そのものへの同意は求められていません(上記ⅰ))。
また、利用規約の内容を表示しないことは、利用規約が見つけにくい場所に載せられていることよりも不適切であるといえます(上記ⅱ))。
以上から、みなし同意による方法は、不適切な同意取得にあたる可能性が高く、その場合、変更後の利用規約をユーザーに適用できなくなります。
※変更後の利用規約の同意の取り方について、詳しく知りたい方は、「利用規約・プライバシーポリシーの適切な同意の取り方を弁護士が解説」をご覧ください。
5 小括

利用規約は、ユーザーが同意してはじめて、事業者とユーザーの契約内容として意味をなします。ですが、事業者に一方的に有利となる条項やユーザーの利益を一方的に害するような条項は、たとえ、ユーザーから同意を得ている場合であっても、同意がなかったものとみなされたり、同意自体が無効になる可能性があります。
利用規約を作成する際には、どのような場合にユーザーの同意がなかったものとみなされるのか、という観点からも、きちんと精査することが大切です。
6 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下のとおりです。
- 「定型取引」とは、①特定の者が不特定多数の者を相手方とする取引で、②内容の全部または一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なものをいう
- 「定型約款」とは、定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者が準備した条項の総体のことをいう
- 利用規約に不利益条項や不意打ち条項が設けられている場合、それらの条項についてはユーザーが同意しなかったものとみなされる
- サイト運営者の損害賠償責任の全部または一部を免除したり、損害賠償責任の有無・限度を事業者自らが決めることとするような条項は無効になる