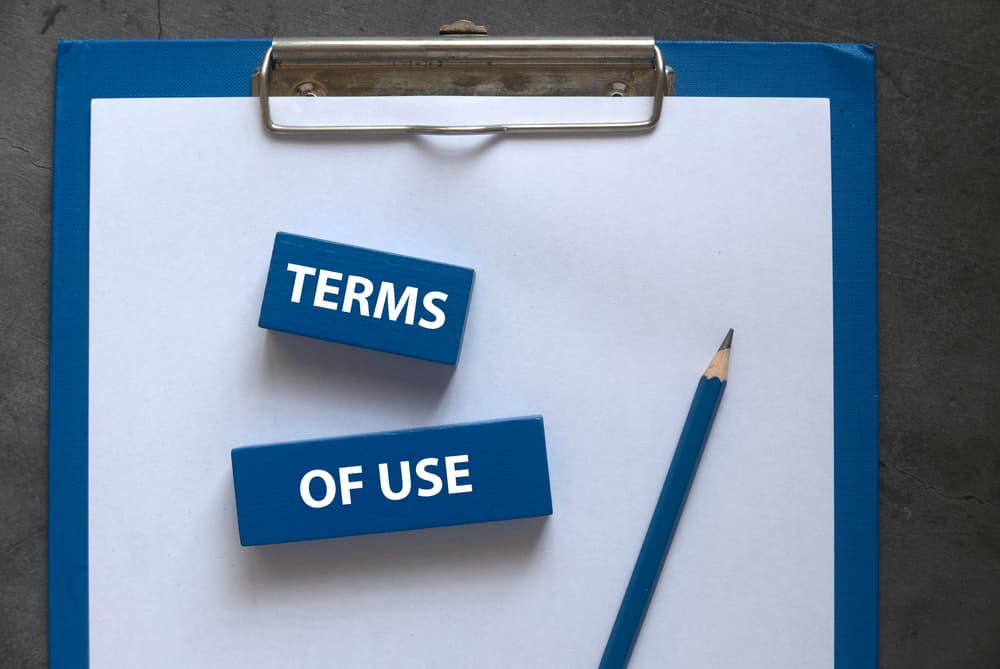はじめに
サービスを提供する場合に必ずといっていいほど設けられるのが「利用規約」です。
「利用規約に同意する」という文言を見たことがある人は多いと思います。
禁止事項や免責事項など、さまざまなルールを利用規約に定めておくことで、ユーザーとのトラブルを回避することができるのです。
もっとも、利用規約の効力をユーザーに及ぼすためには、利用規約についてユーザーから同意を得ることが必要になります。
ご存知のとおり、利用規約を端から端まで精読してサービスを利用し始める人はほとんどいないといっていいでしょう。
とはいえ、ユーザーから有効に同意を得るためには、事業者にも注意すべき点があります。
今回は、利用規約の同意について、事業者が注意すべき点などを中心にわかりやすく解説します。
1 利用規約の同意

利用規約について同意を得たということは、利用規約のルールに則ってサービスを利用することについてユーザーが承諾したということを意味します。
利用規約に同意してもらうことで、事業者は、利用規約で定めるルールをユーザーに適用することが可能になるのです。
そこで、どのような方法でユーザーから同意をもらえばいいのか、という点が問題となりますが、この点については、特に法律上決められたルールはありません。
よく見受けられるのは、以下のような方法です。
- チェックボックスを使う
- 他のボタンに同意機能を与える
- みなし同意を利用する
(1)チェックボックスを使う
「利用規約に同意する」という文言の横にチェックボックスを設け、ユーザーがチェックを入れたことをもって、利用規約に同意したと扱う方法です。
(2)他のボタンに同意機能を与える
サービス利用を申込む際に、「利用規約に同意して申し込む」という表示を見たことがあるという人は多いと思います。
申込ボタンに利用規約の同意機能を与えることで、申込みと利用規約の同意を一度で行うことができ、ユーザーの手間を省くことができます。
(3)みなし同意を利用する
「みなし同意」とは、一定の条件を満たしたユーザーについて、利用規約に同意したものとみなすことをいいます。
たとえば、「サービスの利用開始により利用規約に同意したものとみなす」といった文言を付しておくことで、サービスの利用を開始したユーザーは利用規約に同意したものとみなされることになります。
この場合、利用規約に「〇〇を満たした場合には、利用規約に同意したものとみなす。」といった文言を明記しておくことが必要です。
2 利用規約の同意を得る際の注意点

利用規約のルールをユーザーに適用するためには、同意の取り方が適切であることに加え、利用規約が適切に開示されていることが必要になります。
- 利用規約の内容を適切に開示していること
- 利用規約に従ってサービスを利用することへの同意があること
(1)利用規約の内容を適切に開示していること
利用規約を精読するユーザーが少ないとはいえ、ユーザーによる同意の対象はあくまで「利用規約」に記載されている内容です。
利用規約の内容に同意してもらうことではじめてユーザーに利用規約のルールを適用することができるのです。
そのため、一見してわかりにくい場所に利用規約を掲示しているような場合には、同意の有効性に問題が生じるおそれがあります。
大事なことは、ユーザーが簡単に利用規約を確認できるような状態にしておくということです。
たとえば、サービスに係るwebサイトのわかりやすい場所に掲示しておくことで、ユーザーもすぐに利用規約を確認することができます。
(2)利用規約に従ってサービスを利用することへの同意があること
サービスを利用するにあたり、開示されている利用規約に従う旨の同意があることが必要です。
たとえば、サービスを申し込むにあたって、利用規約への同意が前提となることを適切に表示していないような場合、ユーザーにおいて利用規約に従ってサービスを利用するという意思が認められないおそれがあります。
その場合、ユーザーは利用規約による拘束を受けないことになってしまいます。
このように、利用規約の同意に関しては、同意の取り方だけでなく、利用規約の開示方法も問題となることに注意が必要です。
3 ユーザーの同意が無効になる場合

これまで見てきた点をきちんと守れば、基本的には、適切にユーザーから同意を得ることができます。
ですが、以下で見るように、ユーザーの同意が無効になるケースもあるため注意が必要です。
(1)「不利益条項」と「不意打ち条項」
2020年4月から施行された改正民法により「定型約款」の規定が創設されました。
利用規約の大半は、この定型約款にあたることになりますが、定型約款では、ユーザーの権利を制限したり、ユーザーの義務を加重する条項(不利益条項)を入れることは禁止されています。
利用規約において不利益条項が盛り込まれている場合、同条項についてはユーザーの同意がなかったものとみなされます。
不利益条項の例としては、不当に高額な違約金を定めた条項などが挙げられます。
また、定型約款にあたる利用規約には、ユーザーが通常予見できないようなことを内容とする条項(不意打ち条項)を入れることも禁止されています。
この場合も、不利益条項と同様、ユーザーの同意がなかったものとみなされます。
不意打ち条項の例としては、長期間にわたる継続的契約で中途解約を制限する条項などが挙げられます。
(2)消費者契約法による無効
利用規約において、以下のような条項が定められている場合、その条項は消費者契約法により無効となります。
- 解除権を放棄させる条項
- 事業者の損害賠償責任を免除する条項
- 損害賠償額を予定する条項
事業者の債務不履行が原因となってユーザーに発生した解除権を放棄させるような条項は無効となります。
また、事業者による債務不履行や不法行為が原因となって、事業者に生じた損害賠償責任の全部・一部を免除するような条項も同様に無効となります。
さらに、解除に伴う損害賠償額や違約金の額を予定する条項で、これらの金額が平均的な額を超える場合には、その超える部分については無効となります。
これらは、いずれもユーザーの利益を一方的に害するものであって、たとえこれらの条項が盛り込まれた利用規約にユーザーが同意した場合であっても、その部分に対する同意については無効となります。
4 まとめ
ユーザーに正しくサービスを利用してもらうためにも、利用規約は必要不可欠です。
もっとも、自由にルールを設定できるというわけではなく、改正民法や消費者契約法のルールに則る必要があります。
利用規約について適切に同意を得るためには、利用規約の開示方法や適切な同意の取り方などを、ユーザー側の視点から検討することも大切です。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。