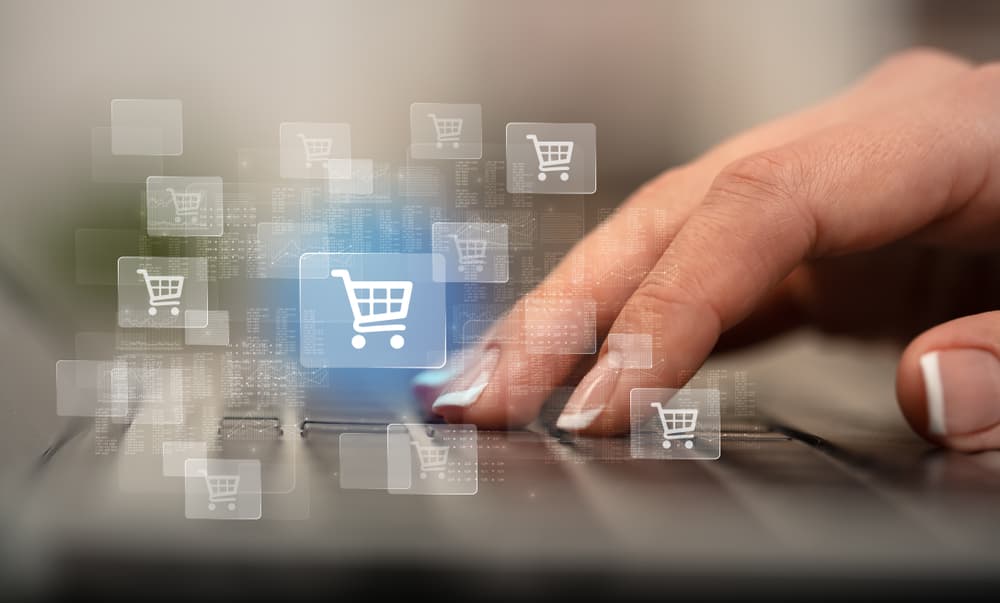はじめに
多くの販売店で在庫切れとなっている商品が、フリマサイトで大量に出品されていることがあります。
その場合、定価より高額で出品されていることが少なくありません。
特に、新型コロナウイルスの感染が拡大したことにより、マスクや消毒液、トイレットペーパーなどが多くの店舗で在庫切れとなったことは、記憶に新しいところです。
これは、いわゆる「転売ヤー」と呼ばれる高値転売によって利ざやを稼ぐ人による商品の買い占めも一つの要因となっています。
また、人気漫画である鬼滅の刃の最新刊の初版が定価の数倍の値段で出品されるという事態も起こっています。
転売ヤーによるこのような行為は、法律で許される行為なのでしょうか。
この記事では
- 転売ヤーのどのような行為が問題となっているのか
- 転売ヤーに関係する規制や罰則
などについて解説します。
1.転売ヤーとは
「転売ヤー」は、インターネットスラングで、「転売」と「バイヤー」を組み合わせた造語です。
定価または安価で大量に仕入れた商品や限定販売の商品、一般市場で品薄になっている商品などを「メルカリ」や「ヤフオク」などのオークション・フリマサイトで、高値で販売する手法を使う人々を指して使われる言葉です。
2.メルカリなどを使った販売手法とは
転売ヤーが利益を上げる手法として、主に下記のようなものがあります。
- 限定販売品を高値で売る
- 一時的に需要が高まり、品薄になっている商品を高値で売る
(1)限定販売品を高値で売る
限定販売品などを入手するために長い行列ができることがありますが、この中には、熱心なファンのほかに、高値転売を目的としている転売ヤーが含まれていることがあります。
たとえば、人気キャラクターグッズの記念バージョンや、服飾品やスポーツグッズの特別モデルなど、数量限定の商品が挙げられます。
限定販売品は、数に限りがあるため、一度売り切れになってしまうと、入手することは困難になります。
その商品をどうしても手に入れたいと考えている人は、販売価格より高値であっても、手に入れたいと考えるのが自然でしょう。
転売ヤーは、そのような一般消費者の心理状態を利用して、限定販売品を高値で売ります。
(2)一時的に需要が高まり、品薄になっている商品を高値で売る
普段は一般の小売店で品切れしないような商品でも、一時的な人気の上昇や災害・感染症の流行などで需要が高まる商品に目を付け、その商品を大量に仕入れて高値転売をするケースもあります。
たとえば、2020年5月には、人気コミック『鬼滅の刃』(集英社)の単行本がメルカリなどで定価よりも高い値段で大量に出品されるという現象が起きましたが、これらの行為は転売ヤーによるものとされています。
また、新型コロナウイルスの感染が流行し始めたことをきっかけとして、マスクの需要が短期間で飛躍的に高まり、多くのドラッグストアなどでは、マスクが品薄状態となりました。、フリマサイトなどでは、大量のマスクが高値で出品されるという事態にまでなりました。これを受けて、政府は、マスクの転売を禁止する法令を公布・施行しています。
このほか、大型台風による被害が広範囲に及んだ際には、ブルーシートや防災用品などが品薄状態に陥りました。
この際にも、フリマサイトなどでは、ブルーシートや防災用品などが高値で出品されるという事態が相次ぎました。
このように、転売ヤーが採る手法は、「限定」や「品薄」などによって需要が高まっている商品を転売目的で入手し、それを高値で販売し利益を上げるところに特徴があります。
もっとも、転売行為自体は、法律に違反する行為ではありません。
それでは、転売ヤーによる転売行為には、どのような問題があるのでしょうか。
3.何が問題となるのか
メルカリのガイドにおいて、転売などの目的で商品を購入し、著しく高額な価格で売却する行為や通常の経済的価値と著しく乖離した価格で商品を出品する行為は「不適切と判断される行為」として禁止されています。
このような行為を許してしまうと、以下のような弊害が生じることになるからです。
- 不当な高額取引の横行
- 転売目的の買い占め
- 偽物(詐欺)の横行
- 無許可販売
(1)不当な高額取引の横行
一般の小売価格よりも不当に高い価格設定をした商品が大量に流通してしまうと、適正価格で健全な取引ができる市場が奪われてしまいます。
にもかかわらず、このような行為が許されるとなると、利益を得ようとする人々が高額取引を行うようになる可能性があり、ひいては、メーカー、小売店、消費者などが損失を被る可能性があります。
(2)転売目的の買い占め
高値転売をする目的で、市中の小売店などで販売している商品を買い占める可能性があります。
転売目的で商品などが買い占められてしまうと、商品を必要とする人が商品を購入できなくなってしまい、最悪の場合、転売ヤーに高い金額を支払って商品を手に入れるしかなくなってしまいます。
(3)偽物(詐欺)の横行
高値で転売できることがわかると、偽物をつかませて利益を上げようとする人々が出てくる可能性があります。
偽物であることを伏せて高値で売りつける行為は、詐欺行為にあたり、実際に、このような手法により、お金をだまし取られる被害も出ています。
(4)無許可販売
一度購入した商品は、基本的に「古物」にあたるため、この商品を転売するには、原則として、古物商の許可を受ける必要があります。
このことは、転売ヤーであっても同じです。
もっとも、古物商の許可を受けることは簡単ではないため、許可を受けずに販売する「無許可販売」が横行する可能性があります。
例外的に許可が不要となる場合もありますが、許可が必要であるにもかかわらず、
この点は、後ほど詳しく解説します。
4.転売ヤーを取り締まる法律

「転売」という言葉に、いいイメージを持っている方は少ないかもしれません。中古チケットなどを転売したとして逮捕されるといったニュースは後を絶ちません。
それでは、転売ヤーを取り締まる法律はあるのでしょうか。
以下では、転売行為に関わる法律を見てみましょう。
転売行為に関係する法律は、
- 特定商取引法
- 古物営業法
の2つです。
5 特定商取引法
「特定商取引法」とは、消費者トラブルが発生しやすい特定の取引を対象として、消費者保護や安全取引を目的とした一定のルールを定めた法律です。
たとえば、転売ヤーが取引を行うツールの一つにネットオークションがあります。ネットオークションによる取引については、消費者庁が「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」を出しており、営利の意思を持って反復継続して販売を行う場合は、法人であると個人であるとを問わず、「販売業者」に該当し、特定商取引法の規制対象になるとされています。
転売目的で商品などを入手する場合には「営利の意思」があると判断される可能性が高いため、転売ヤーが販売業者として、特定商取引法の規制対象となる可能性は高いといえます。
また、ガイドラインによれば、以下のようなケースは、原則として、営利の意思を持って反復継続して取引を行う販売業者にあたるとしています。
- 大量の新規出品をしている場合
- 落札額の合計が一定金額を超えている場合
(1)大量の新規出品をしている場合
大量の商品を新規出品している場合には、原則として、販売業者にあたります。
具体的には、
- 過去1ケ月に200点以上、または一時点において100点以上の商品
を出品している場合には、販売業者にあたると判断される可能性が高いです。
もっとも、これらの数字を下回っているからといって、直ちに販売業者にあたらないということにはなりません。
出品している複数の商品のメーカーや型番などがすべて同じであれば、販売業者にあたると判断される可能性は高いです。
このように、販売業者の該当性は、数字だけで形式的に判断されるわけでなく、商品の種類といった実質面も考慮されます。
この点、メーカーや型番などが同一の商品を多数出品している転売ヤーも少なくありません。このような転売ヤーは、販売業者にあたると判断される可能性が高いということがいえます。
なお、トレーディングカードや中古音楽CD、アイドル写真などのように、趣味の範囲で収集した物を処分・交換する目的で出品する場合は、販売業者にはあたりません。
(2)落札額の合計が一定金額を超えている場合
出品された商品の落札額の合計が、
- 過去1ケ月に100万円以上である場合or
- 過去1年間に1000万円以上である場合
には、販売業者にあたると判断される可能性が高いです。
もっとも、自動車や絵画、骨董品などのように、1点につき100万円を超える商品もあります。
このような場合には、同時に出品している他の物品の種類や数量などを考慮したうえで、販売業者の該当性が判断されます。
以上の観点から、販売業者にあたる場合には、特定商取引法の規制対象となり、事業者には以下の義務が課されることになります。
- 商品広告をする際の表示義務(販売価格や支払時期・方法など)
- 誇大広告の禁止
これらに違反すると、行政処分に加え、罰則が科される可能性があります。
6 古物営業法
「古物営業法」とは、盗品などを対象とした取引の防止を目的として、古物営業に関する業務について一定のルールを定めた法律です。
ここでいう「古物」には、中古品のように一度使用された物のみならず、未使用の物で使用のために取引されるなども含まれます。
そのため、メーカーから出荷され一度使用された商品はもちろんのこと、未使用であっても使うために取引された商品は、古物にあたります。
そして、古物を対象とした売買などを業として行う場合には、古物営業の許可を受けなければなりません。
転売ヤーの場合、転売目的で一般の小売店などから仕入れる商品は、「使用のために取引される商品」に当たるといえ、「古物」にあたります。
そのため、これらの行為を業として行っている場合には、古物営業の許可を受ける必要があります。
にもかかわらず、許可を取らずに営業を行った場合には、次の項目で見るように、罰則が科される可能性があります。
※詳しくは「古物営業法とは?古物取引で知っておくべき9つのルールについて解説」の記事でも説明しています。
7.罰則
転売ヤーが、特定商取引法と古物営業法の規制対象となる可能性があることは、既に見てきたとおりです。
これらの法律では、いずれも違反者に対する罰則が設けられています。
(1)特定商取引法に違反した場合
転売ヤーが特定商取引法上の販売業者にあたる場合、以下の義務が課されます。
- 商品広告をする際の表示義務(販売価格や支払時期・方法など)
- 誇大広告の禁止
にもかかわらず、たとえば、誇大広告を行った場合には、
- 最大100万円の罰金
が科される可能性があります。
また、法人である場合には、違反行為者とは別に、法人に対して、
- 最大100万円の罰金
が科される可能性があります。
(2)古物営業法に違反した場合
古物営業法上の許可が必要となる転売ヤーが無許可で古物営業を行うと、
- 最大3年の懲役
- 最大100万円の罰金
のいずれかを科される可能性があります。
また、法人である場合には、違反行為者とは別に、法人に対して、
- 最大100万円の罰金
が科される可能性があります。
8.転売ヤーへの対策は
フリマサイトなどでは、その多くが利用規約などにより、悪質な転売行為を禁止しています。
そのため、悪質な転売行為を行っていると思われるアカウントを運営事業者へこまめに通報することが転売ヤーに対する一番有効な対策でしょう。
最近はメーカーや販売店でも商品の大量購入などに一定の対策を取るようになってきています。転売された商品よりも正規の小売店などで商品を買い求めるようにすることも転売ヤーに対する対策として有効といえるでしょう。
9 小括
元来、「不用品を捨てるぐらいなら、売ってお金に変えたい」といった需要から始まったフリマアプリやオークションサイトですが、現在では、「転売ヤー」のように営利目的で利用されることもあります。
「転売ヤー」による取引は、個人間で行われる単発の取引とは目的や態様において異なるため、特商法や古物営業法の規制対象となる可能性があることには注意が必要です。
10 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下の通りです。
- 「転売ヤー」とは、インターネットスラングで、「転売」と「バイヤー」を組み合わせた造語のことをいう
- 転売ヤーの手法として、①限定商品を高値で売る、②一時的に需要が高まり、品薄になっている商品を高値で売るという2つの方法がある
- 転売ヤーの問題点として、①不当な高額取引の横行、②転売目的の買占め、③偽物(詐欺)の横行、④無許可販売の4つがある
- 転売ヤーに関わる法律には、「特定商取引法」と「古物営業法」がある
- 中古品などの「古物」を販売する業者は、国から許可を取らなくてはならない
- 特商法で禁止されている誇大広告を行うと、最大100万円の罰金が科される可能性がある
- 必要となる古物営業法上の許可を受けることなく古物営業を行った場合、①最大3年の懲役、②最大100万円の罰金のいずれかを科される可能性がある
- 転売ヤー対策として、こまめに運営業者へ通報することが挙げられる