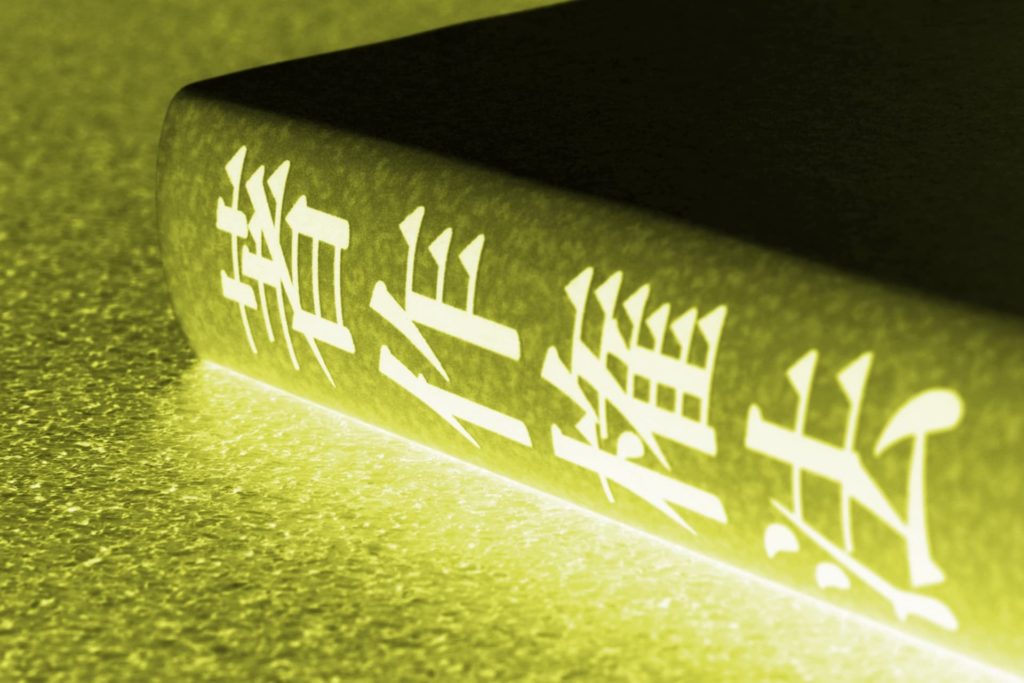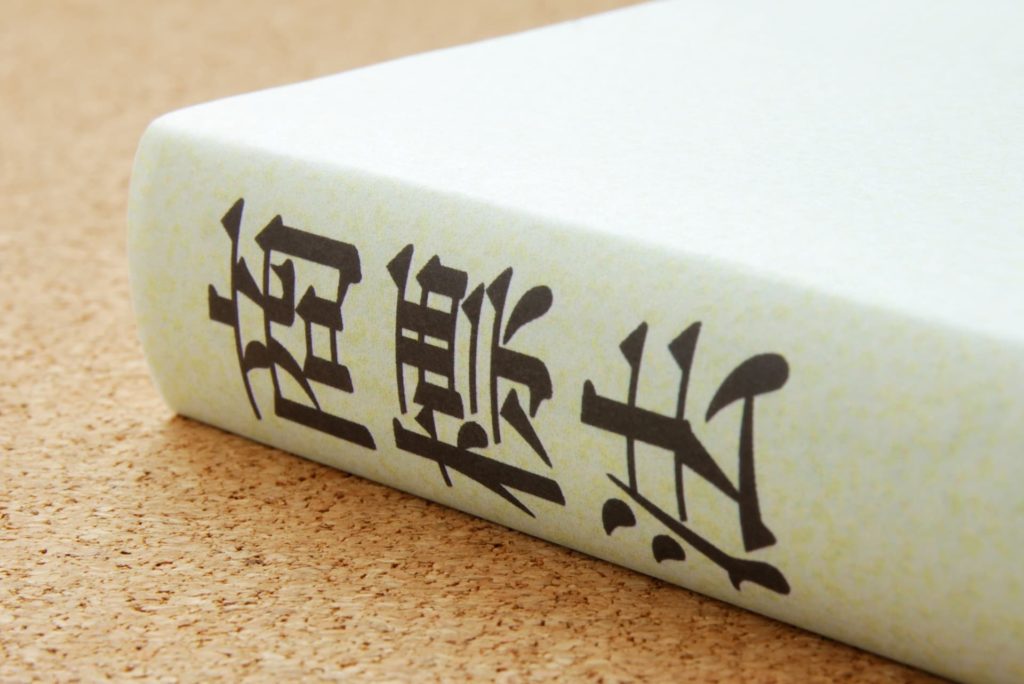はじめに
自社の特許を侵害された場合、原則として侵害者に対し損害賠償を請求することができます。
侵害者が気付かずに侵害しているケースもあるため、侵害の事実が発覚した際には、冷静に対応することが必要です。
もっとも、どの程度の損害賠償額を請求できるのか、また、どのように対応を進めていくべきかなど、事業者にとっては気になる点もあると思います。
今回は、自社の特許を侵害された場合の損害賠償額の考え方と対応方法などについてわかりやすく解説します。
1 特許侵害に対する損害賠償の考え方

特許法は、特許侵害による損害の額を3つの類型に分け、推定規定などを設けています。
- 侵害した物を譲渡したとき
- 侵害者がその行為により利益を得ているとき
- 特許権のライセンス料
2 侵害した物を譲渡したとき

侵害者が侵害した物を譲渡した場合の損害額について、特許法は以下のように定めています。
-
【特許法102条1項】
特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。
一 特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額に、自己の特許権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額
二 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額
わかりづらいかもしれませんが、この規定では、損害額を以下の計算式により算出する旨が定められています。
-
損害額 = 侵害者が譲渡した物の数量 × 特許権者の単位あたりの利益の額
この類型では、「侵害の行為がなければ販売することができた」という関係が、侵害された物と特許権者の商品との間に存在していることが必要になります。
また、譲渡数量について、その全部または一部を特許権者が販売することができないとする事情がある場合には、その事情に相当する数量に応じた額を控除しなければなりません。
3 侵害者がその行為により利益を得ているとき

侵害者が侵害行為により利益を得ている場合の損害額について、特許法は以下のように定めています。
-
【特許法102条2項】
特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
この規定では、損害額を以下の計算式により算出する旨が定められています。
-
損害額 = 侵害者がその侵害の行為により受けた利益額
この規定により推定を受ける「損害の額」は、特許権者が特許権に係る製品などを製造・販売することで得られたであろう逸失利益のことをいうと考えられています。
そのため、特許権者が特許権に係る製品などの製造・販売を行っていない場合には、この規定は適用されないため注意が必要です。
4 特許権のライセンス料

特許権者は、特許権の侵害者に対し、特許のライセンス料に相当する額を自身が受けた損害額として賠償を請求することができます。
-
【特許法102条3項】
特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
この規定では、損害額を以下の計算式により算出する旨が定められています。
-
損害額 = 特許発明実施料に相当する額
ここでいう「特許発明実施料」は、さまざまな事情を考慮したうえで決定されることとされています。
具体的には、特許発明の内容や侵害対象の販売価格、侵害を受けた特許権と同様の実施許諾例などを考慮したうえで、決定されることになります。
5 特許侵害された場合の対応

特許権を侵害された場合、まずは、社内で特許権侵害の有無を確認することが必要です。
この点は、特許公報の「特許請求の範囲」の各請求項に記載されている発明を構成要件に分け、対象となっている製品が、その分けられた構成要件を満たしているかという手法により判断することが一般的です。
特許権を侵害されているということがわかった場合、次に、特許権者は、どのような方法で侵害者の責任を追及するかを決定する必要があります。
特許権侵害を受けた場合に侵害者に求めうることとしては、損害賠償請求のほか、以下のようなことが挙げられます。
- 製品の製造・販売の差止め
- 刑事告訴
もっとも、侵害者に刑事責任を負わせるためには、侵害行為につき侵害者に「故意」があったといえなければなりません。
現実的に、故意をもって他社の特許権を侵害するといった事例は少ないといえます。
そのため、多くの場合は、以下のいずれかの対応で進めていくことになります。
- 製品の製造・販売の差止めを申し立てる
- 特許権をライセンスし、ライセンス料を支払ってもらう
- 損害賠償を請求する
6 まとめ
特許を侵害された場合の損害額は、被侵害者側で立証することが難しいため、特許法により推定規定が設けられています。
そのため、侵害者において反証に成功しないかぎり、推定を受けた損害の額がそのまま損害額として認められることになります。
自社の特許が侵害されていると疑われる場合には、自社にとってどのような対応で進めていくことが望ましいかを慎重に判断することが大切です。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。