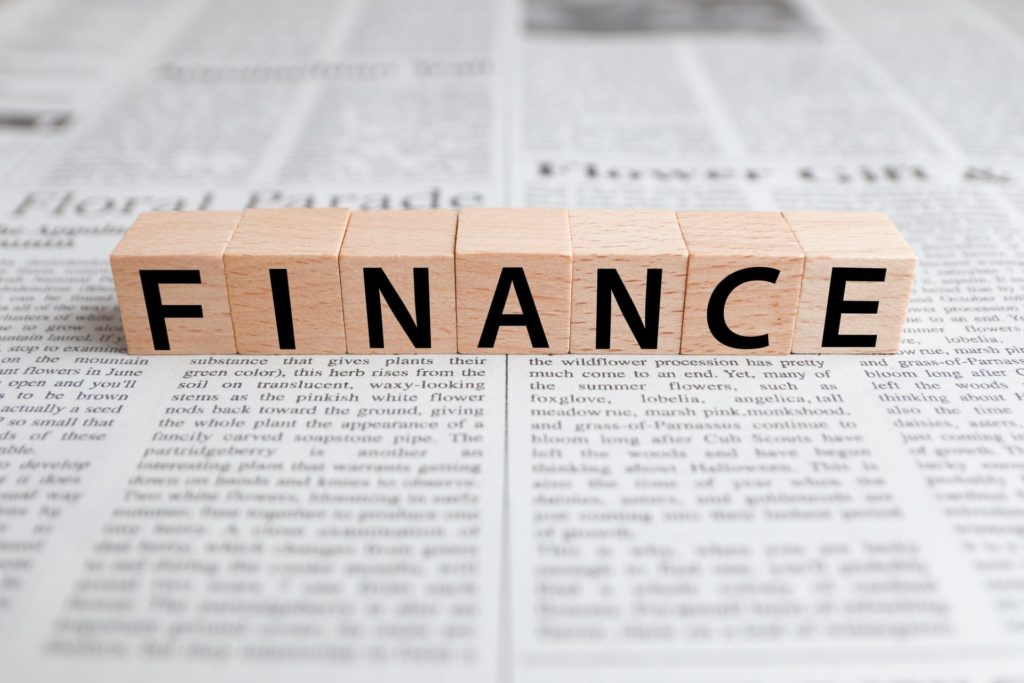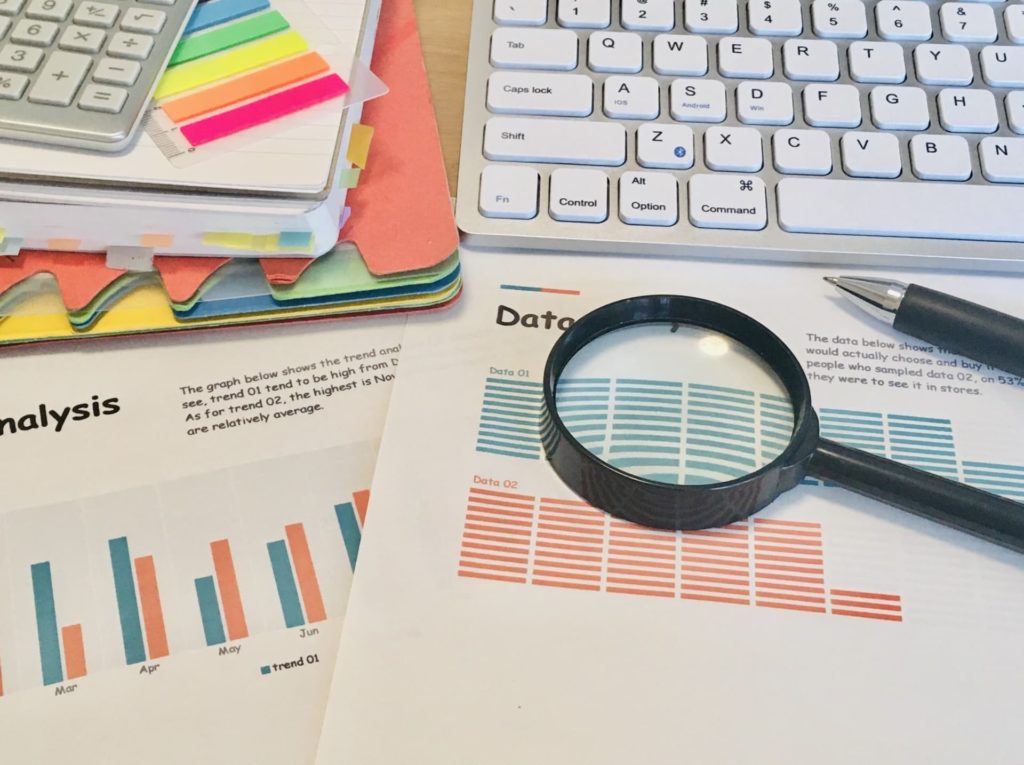はじめに
近年、「ソーシャルレンディング」を利用する事業者が増えています。
インターネットを通じて投資家から融資を募ることができるため、特に、スタートアップ企業やベンチャー企業などのように、銀行の融資基準を満たすことができない事業者を対象に、今後も利用者が増えるものと予測されます。
ソーシャルレンディングでは、ボロワー(融資を受ける側)とレンダー(融資を行う側)、そして、その場を提供するプラットフォーマーの三者が当事者となって金銭のやり取りが行われます。
それぞれにおいて注意すべき法規制は存在しますが、特に、プラットフォーマーとしてソーシャルレンディングの場を提供する場合には、多数の法規制を押さえておくことが必要です。
法律周りを押さえずに事業を始めてしまうと、罰則を科される可能性もあるため注意するようにしましょう。
今回は、「ソーシャルレンディング」について、その概要と注意すべき法規制などを弁護士がわかりやすく解説します。
1 ソーシャルレンディングとは
「ソーシャルレンディング」とは、Social(社会の)とLending(融資)を組み合わせた造語で、お金を借りたい事業者(ボロワー)とお金を貸したい個人投資家(レンダー)を、インターネットを通じて結びつけるサービスのことをいいます。
具体的には、以下のような仕組みになっています。

①投資
プラットフォーマーは、複数の個人投資家からお金を集めます。
個人投資家は、ボロワーに対して直接お金を融資するわけではなく、プラットフォーマーが運営するファンドに投資します。
②融資
プラットフォーマーは、個人投資家から集めたお金を元手に融資を実行します。
プラットフォーマーからボロワーへの融資はあくまで「貸付け」であるため、ボロワーには返済義務が発生します。
③返済
ボロワーは、プラットフォーマーから借りたお金を返済します。
具体的には、借りたお金に一定の利息を上乗せして返済することになります。
④分配
プラットフォーマーは、返済として受け取った元利金からレンダーに分配を行います。
プラットフォーマーは、このうち利息分をレンダーと分け合うことで利益を得ることができます。
2 ソーシャルレンディング事業者が押さえておくべき法規制
ソーシャルレンディング事業者(プラットフォーマー)が押さえておかなければならないのは、以下に挙げた4つの法規制です。
- 貸金業法
- 利息制限法
- 金融商品取引法
- 犯罪収益移転防止法(犯収法)
(1)貸金業法
「貸金業」とは、金銭の貸付けや貸借の媒介を業として行うことをいいます。
貸金業を営む場合には、内閣総理大臣・都道府県知事への登録が必要となります。
この点、ソーシャルレンディング事業者は、希望するボロワーを対象として、金銭の貸付けを継続的に行うことを事業内容としています。
そのため、貸金業法上の「貸金業者」として登録を受けることが必要です。
(2)利息制限法
「利息制限法」とは、金銭の貸し借りにおける利息のルールを定めた法律です。
具体的には、貸し付けの金銭(元本)の額に応じて、利息の上限が決められています。
- 元本の額が10万円未満:年20%
- 元本の額が10万円以上100万円未満:年18%
- 元本の額が100万円以上:年15%
ソーシャルレンディングの場合、ボロワーから支払われる利息をレンダーとプラットフォーマーで分けあう仕組みになっています。
そのため、ボロワーから支払われる利息についても、利息制限法が適用されます。
利息制限法が定める利率を超えた利息は、その超過分にかぎり無効として扱われるため注意するようにしましょう。
(3)金融商品取引法
「金融商品取引法」とは、投資家の保護や経済の円滑化を目的として、金融商品に係る取引を規制する法律です。
同法は、一定の要件を満たす事業を「金融商品取引業」として定め、同業を行う場合には内閣総理大臣への登録が必要とされています。
ソーシャルレンディング事業者との関係で問題となるのは、「第2種金融商品取引業」です。
「第2種金融商品取引業」は、ファンドや信託受益権を販売する場合に登録が必要となる事業です。
ソーシャルレンディングのように、投資案件を募集したり取り扱ったりする場合には「第2種金融商品取引業」の登録が必要になります。
業務の性質上、登録要件は厳しくなっており、登録を受けるためのハードルは高いといえるでしょう。
(4)犯罪収益移転防止法(犯収法)
「犯罪収益移転防止法(犯収法)」とは、犯罪によって得られた利益の移転を防止するための法律です。
同法は、一定の事業者を「特定事業者」として指定し、さまざまなルールを設けています。
この点、貸金業者や金融商品取引業者は「特定事業者」に指定されているため、ソーシャルレンディング事業者は「特定事業者」にあたることになります。
特定事業者は、取引時において利用者と本人の同一性を確認すること(本人確認義務)や取引記録を作成・保存することが義務付けられます。
3 まとめ
ソーシャルレンディング事業を行う場合には、一定の事業者として登録が必要になるなど、関係する法規制は複雑になっています。
アバウトに事を進めてしまうと、罰則を受ける可能性もあるため、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。