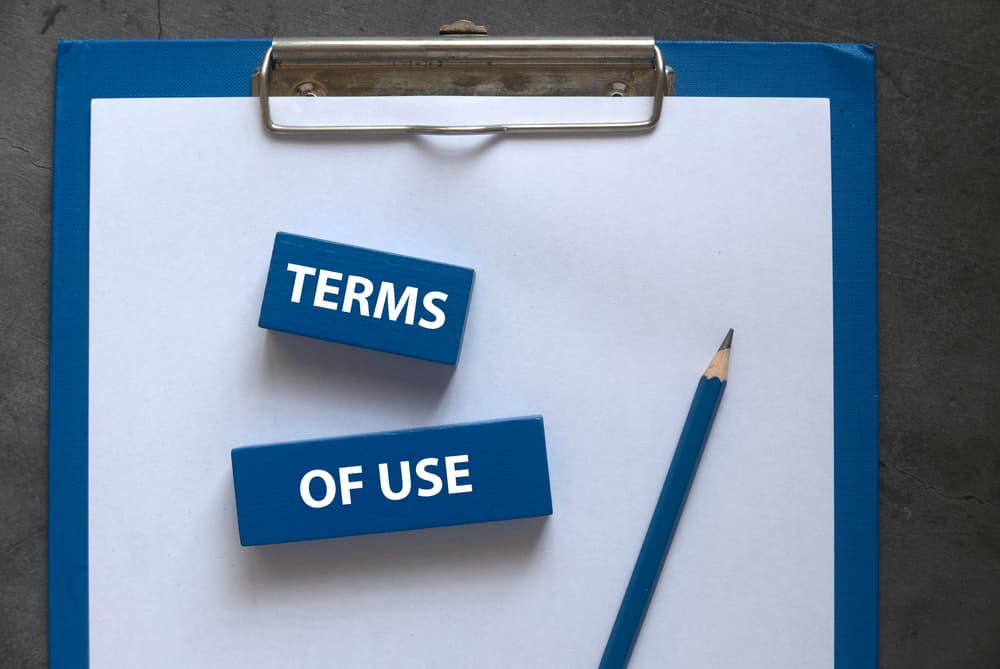はじめに
利用規約は、状況の変化などに応じてその内容も随時変更していかなければなりません。
とはいえ、ユーザーが多数に上る場合、個別に「同意」を取らないと、利用規約を変更することはできないのでしょうか。
そうだとすると、事業者だけでなくユーザーに対しても一定の負担を強いることとなり、変更が頻繁に生じるようなサービスにいたっては、ユーザーがサービスを利用しなくなるおそれもあります。
このような場合に、ユーザーから個別に同意を取ることなく、利用規約を変更できる方法があることをご存知でしょうか。
そこで今回は、利用規約を変更する場合の手続きを中心に、弁護士がわかりやすく解説します。
1 利用規約を変更する2つの方法

「利用規約」は、サービスを提供する際には欠くことのできないものですが、サイトに表示するなどして、ユーザーから同意をもらう仕組みを作ったらそれでおしまい、というわけではありません。サービス開始後においても、サービスの内容が変わったり、法律の改正、社会状況の変化などに応じて利用規約の内容を適切に変更する必要があります。
利用規約を変更する場合、
- 変更の周知
- 変更につきユーザーの同意を取る
という2つの方法があります。
(1)変更の周知
利用規約は、その内容につきユーザーから同意を得ることによって、一定の拘束力を生じることが原則です。そのため、利用規約を変更する場合においても、個別にユーザーから同意を得なければならないのが同様に原則となります。
ですが、利用規約の変更が頻繁に生じたりすると、その都度、ユーザーから同意を得なければならず、ユーザーにとって負担となってしまいます。
また、ユーザーが不特定多数である場合には、事業者にとっても大変な負担となります。
そこで、例外的に、一定の条件を満たす場合には、変更の周知のみで、ユーザーの同意を得ることなく利用規約を変更することができます。
ここでいう「条件」とは、次の3つのことをいいます。
- 利用規約が定型約款にあたること
- 変更がユーザーの一般の利益に適合すること
- 変更が契約の目的に反せず合理的なものであること
+
or
①利用規約が定型約款にあたること
2020年4月に民法が改正され、「定型約款」という規定が新たに創設されました。
「定型約款」とは、以下の2つの条件を満たすものをいいます。
- 特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であること
- 取引内容の全部・一部が画一的であることが双方にとって合理的なもの
たとえば、保険約款や預金規定、電気供給約款などが定型約款にあたります。
この点、Webサービスなどでサイトに置かれている利用規約のほとんどは、上記2つの条件を満たすため、「定型約款」にあたります。
②変更がユーザーの一般の利益に適合すること
利用規約の変更が、すべてのユーザーにとって利益となる変更である場合には、ユーザーから個別に同意を得なくとも、変更を周知することで利用規約を変更できます。
たとえば、料金の変更を伴わずにサービスを拡大する旨の変更は、一般的にすべてのユーザーの利益に適合しているといえます。
③変更が契約の目的に反せず合理的なものであること
利用規約の変更が、ユーザーにとって不利益となる場合でも、一定の条件を満たせば、変更を周知することで利用規約を変更できます。
具体的には、利用規約の変更が契約の目的に反していないことに加え、その変更が合理的なものであることが求められます。
ここでいう「変更が合理的」なものであるかどうかは、諸要素から判断されることになります。
具体的には、以下の4要素を基に、変更の合理性の有無が判断されます。
- 変更の必要性の有無
- 変更内容の相当性の有無
- 「変更することがある」旨の定めの有無とその内容
- その他の変更に関する事情
もっとも、利用規約の変更に賛同しないユーザーも少なからず存在するものと想定されるため、その点に配慮することも忘れてはなりません。
このように、利用規約が定型約款にあたることを前提とすると、②もしくは③の条件を満たすことにより、事業者は、個別にユーザーから同意を得ずに、変更を周知する方法で利用規約を変更することが可能です。
(2)変更につきユーザーの同意を取る
一般的に、契約の内容を変更する場合、契約の当事者双方がその変更内容について理解したうえで同意することが必要です。
この点、ユーザーが利用規約にいったん同意すると、利用規約の内容はそのまま事業者とユーザーの契約内容になります。
そのため、仮に(1)による方法を採れる場合であっても、個別にユーザーから同意を取る方法により、利用規約を変更しても問題ありません。
(1)で見た条件を満たさないことにより、変更を周知する方法を採ることができない場合は、原則に立ち返って、変更についてユーザーの同意を取らないかぎり、利用規約を変更することはできないということになります。
なお、この場合は、適切な方法によりユーザーから同意を取ることが重要になってきます。
たとえば、ユーザーがWebサイトで「同意」ボタンを押す、チェックボックスにチェックを入れるといった方法が挙げられます。
※利用規約の同意の取り方について、詳しく知りたい方は、「利用規約・プライバシーポリシーの適切な同意の取り方を弁護士が解説」をご覧ください。
2 変更を周知する場合の注意点

変更を周知する方法で、利用規約を変更する場合には、以下の事項をインターネットなどの適切な方法により周知しなければなりません。
- 利用規約を変更する旨
- 変更後の利用規約の内容
- 効力発生時期
このように、変更をする旨を周知するだけでは足りず、変更後の具体的な内容とその変更がいつから効力を生じるか(効力発生時期)を併せて周知する必要があります。
また、利用規約の変更がユーザーにとって不利益なものである場合(上記1(1)③)には、注意が必要です。
この場合、上で示した3つの事項を少なくとも効力発生時期が到来するまでに周知しなければ、利用規約の変更は効力を生じません。
3 変更につきユーザーの同意を取るときの注意点

ユーザーから同意を取る方法で、利用規約を変更する場合、原則として、初めにユーザーから同意を取ったときと同様の手続きを踏む必要があります。
この場合に注意しなければならないのは、同意の取り方です。
単に、自社サイトなどに変更後の利用規約を掲載しているだけでは、ユーザーから同意を得たとはいえません。
この点、経済産業省が公表している準則によれば、以下のルールを守ることが必要になると考えられます。
- ユーザーが事前かつ容易に確認できるように、ウェブサイトなどで適切に利用規約が開示されている
- ユーザーが利用規約に同意していることが認定できる
たとえば、変更後の利用規約をサイト内の適切な場所に掲載し、同意する旨のチェックボックスを組み込む方法は、多くの事業者が採っている方法です。
このように、変更につきユーザーの同意を取る場合には、主に、その取り方に注意する必要があります。
もっとも、頻繁な変更が予定されているようなサービスでは、変更するたびにユーザーから同意を得ることが必要になるため、面倒に思うユーザーがサービスから離れる可能性があります。
このような懸念がある場合には、「黙示の同意」を得る方法もあります。
「黙示の同意」とは、利用規約を変更する旨を十分に告知したうえで、ユーザーが引き続きサービスを利用している場合に、ユーザーにおいて変更後の利用規約に同意したものとみなすことをいいます。
具体的には、利用規約において、黙示の同意条項を設けることになります。
そうすると、黙示の同意条項で対応するのが一番楽ではないかと考える方もいるかもしれませんが、そうではありません。
黙示の同意条項についても、場合によっては、その効力を否定される場合があります。
黙示の同意は、ユーザーによる明示の同意でない以上、少なからず、ユーザーにおいて利用規約の変更があることを認識していることに加え、変更される内容が適切に開示されていることが必要です。
以上のように、利用規約は、その変更を周知することで個別にユーザーから同意を取る必要はなくなります。
また、変更を周知する場合に必要な条件を満たさなくとも、個別に同意を取ることによって、利用規約を変更することができます。
※経済産業省が公表する準則について、詳しく知りたい方は、「電子商取引及び情報材取引等に関する準則」をご覧ください。
4 小括
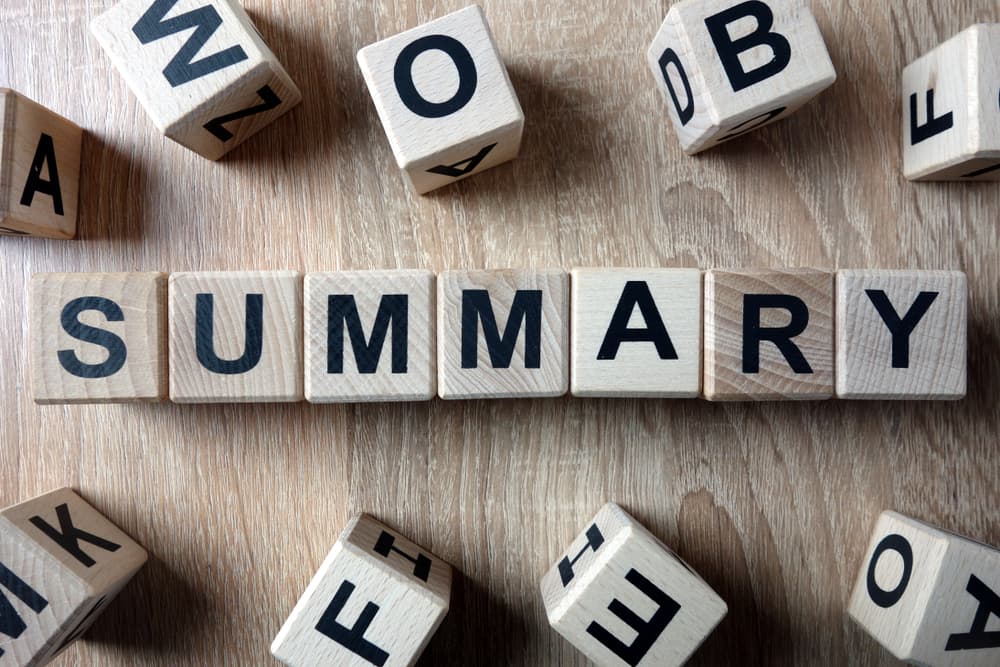
利用規約は、サービス内容の変更や法改正、社会状況の変化などに応じて、その内容を適宜変えていかなければいけません。
また、利用規約を変更するだけでなく、変更の内容やユーザーへの周知方法、同意の取り方など、注意しなければならない点も数多くあります。
快適にサービスを利用してもらうためにも、利用規約を変更する場合には、ルールを遵守することが事業者には求められます。
5 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下の通りです。
- 利用規約を変更する場合には、①変更について周知する、②変更についてユーザーの同意を取る、のいずれかの手続きを取る必要がある
- 変更の周知のみで、利用規約を変更するためには、①利用規約が定型約款にあたることに加え、②変更がユーザーの一般の利益に適合すること、もしくは、③変更が契約の目的に反せず合理的なものであることが条件となる
- 変更について周知するときは、①利用規約を変更する旨、②変更後の利用規約の内容、③効力発生時期を周知しなければならない
- 変更についてユーザーの同意を取る場合、経産省が公表する準則によれば、①利用規約が適切にユーザーに開示されている、②ユーザーが変更後の利用規約に同意していることが認定できる、という2つのルールが存在する