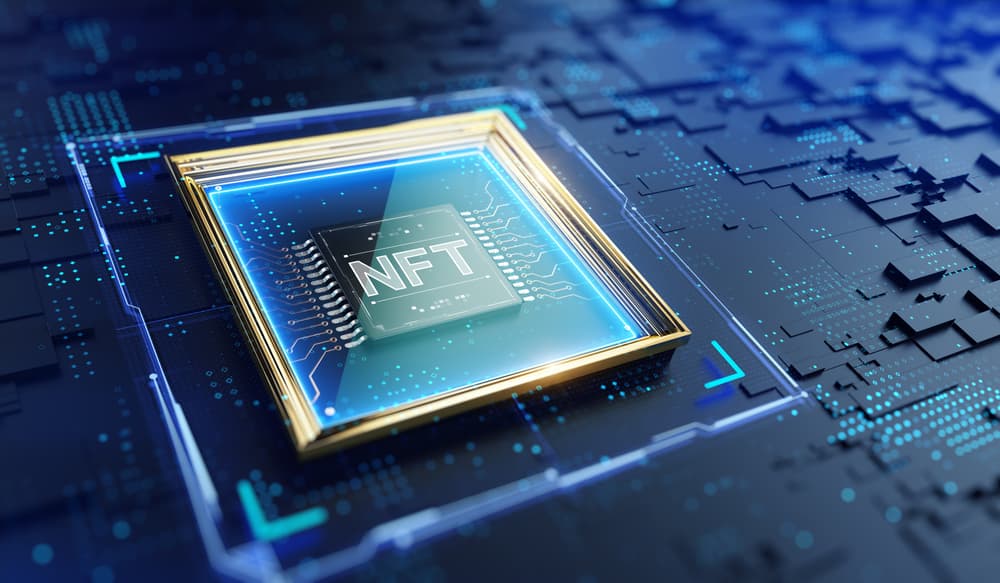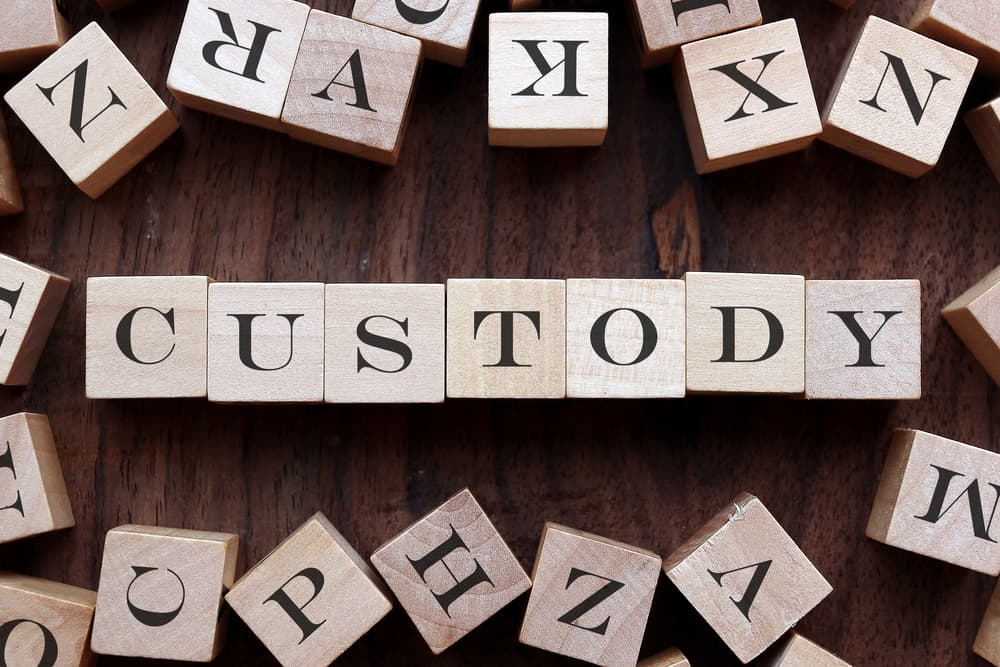はじめに
仮想通貨が身近な存在となった今、新たに独自の仮想通貨を作成・販売してビジネスを始めたいと考えているものの、仮想通貨を販売するにあたって、どのような法律規制・ルールがあるのかわからない方が多いのではないでしょうか。
2017年に改正資金決済法が施行され、仮想通貨に関する新たなルールが設けられたため、規制内容をきちんと押さえておかないと思わぬペナルティを科される可能性があります。
そこで今回は、仮想通貨を「販売」するときの規制について、2つのポイントを解説していきます。
1 仮想通貨を「販売」するときの規制

日本で新しく仮想通貨を「販売」したいと考えた場合、大きく分けて以下の2つの規制があります。
- 仮想通貨交換業の登録をうけること
- 金融庁の認可を得ること
以下で順番にみていきましょう。
2 規制①:仮想通貨交換業の登録をうけること

2017年の改正資金決済法の施行により、日本居住者に対して仮想通貨を売ったり買ったり交換したりする場合には、「仮想通貨交換業者」として国から登録をうけることが義務付けられました。そのため、事業者が独自の仮想通貨を売り出す場合にも、「仮想通貨交換業」の登録をうけなければなりません。以下で詳しくみていきましょう。
(1)仮想通貨交換業とは?
「仮想通貨交換業」とは、ビットコインなどの仮想通貨を売ったり買ったり、交換したりするサービスのことをいいます。そして、仮想通貨交換業を行っている事業者のことを「仮想通貨交換業者」といいます。具体的には、仮想通貨ユーザーが利用している取引所などで行われている行為が「仮想通貨交換業」、その取引所を運営しているbitflyerなどが「仮想通貨交換業者」です。
なお、改正資金決済法では、仮想通貨交換業の要件を以下のように定めています。
- 仮想通貨の
- 「売買」または仮想通貨同士の交換をすることorこれらの行為の媒介・取次・代理をすること
- 「2」の行為に関して、利用者の金銭or仮想通貨の管理をすること
- これらの行為を「事業」として行うこと
+
これらの要件のうち、2~3のいずれかに該当し、かつ、これを「事業」として行う場合に、仮想通貨交換業の登録を受ける必要があります。なお、3については2の行為が前提となるため、実質的には「2に該当する行為を事業として行っているかどうか」という点を判断することになります。
事業者が、「自分たちで新しく独自の仮想通貨を作って売りたい!」と考えた場合、少なくとも上の要件の1・2・4をみたすことになります。そのため、国から仮想通貨交換業者として登録をうけ、お墨付きをもらうことが必須となるのです。
仮に、登録をうけないまま独自の仮想通貨を売った(仮想通貨交換業を行った)場合、
- 最大3年の懲役
- 最大300万円の罰金
のどちらかもしくは両方を科される可能性があります。
(2)「仮想通貨」にあたるかの検討
事業者が独自の「仮想通貨」を売る場合には、「仮想通貨交換業者」として登録を受ける必要があるのはすでに解説した通りです。
そこでまず、事業者としては、自分たちが売ろうとしているものが本当に「仮想通貨」にあたるのかを検討する必要があります。
「仮想通貨」とは、インターネット上でやりとりされる通貨のことをいいます。通貨といっても、私たちが普段使っているお金のような実体をもたず、すべてデータとして管理されます。また、日本銀行のような、公的な発行機関もありません。
2017年に施行された改正資金決済法で、仮想通貨は「法定通貨(円やドルなど)にはあたらないが、財産的価値をもち、決済手段として利用できるもの」と位置づけられました。
さらに具体的にいうと、仮想通貨は、改正資金決済法上以下の2つに分けられます。
- 1号仮想通貨
- 2号仮想通貨
事業者が、これら2つのうちどちらかにあてはまるものを作って売ろうとする場合は「仮想通貨の売買」にあたるため、仮想通貨交換業の登録をうけなければなりません。
「1号仮想通貨」とは、ざっくりいうと「不特定の人との間で、物を売ったり買ったりするときに決済手段として使えるもので、仮想通貨それ自体も取引の対象となるもの」です。代表的な1号仮想通貨としては、ビットコインやイーサがあり、近年、これらを使って決済できる店舗やサービスが増えてきましたね。
他方で、「2号仮想通貨」とは、「不特定の人との間で、1号仮想通貨と交換することができるもの」をいいます。ビットコインなどの1号通貨にあてはまらない仮想通貨、いわゆる「アルトコイン」(世の中のほとんどの仮想通貨がこれにあたります)は、それ自体は決済手段として利用されることは想定されていません。そのかわりに、「財産的価値の高い1号仮想通貨と交換できること」が要件となっているのです。
これら2つに共通して重要な点は、「不特定性」です。「仮想通貨」として認められるためには、不特定多数の人との間で(=誰とでも)やりとりができる必要があります。そのため、自社のプロジェクトやサービスの中でしか使えないようにトークンを設計した場合は、「仮想通貨」にはあたらず、仮想通貨交換業の登録をうける必要はありません。
「不特定性」の判断基準に関しては、仮想通貨のガイドラインで以下のように述べられています。
- 仮想通貨の発行者と店舗などの間の契約で、代金の支払いのために仮想通貨が使える店舗が限定されていないかどうか
- 発行者が、仮想通貨を使える店舗を管理しているかどうか
- 発行者による制限なく、日本円や外国通貨と交換(=換金)できるかどうか
- 日本円や外国通貨と仮想通貨との交換市場が存在するかどうか
これらの要素を加味した上で、仮想通貨として必要な不特定性の要件をみたすかどうかを判断します。
※仮想通貨とは何かについてさらに詳しく知りたい方は、「仮想通貨の法律規制とは?仮想通貨法6つのポイントを弁護士が解説!」をご覧ください。
なお、仮想通貨にあたらない場合でも、資金決済法上の「前払式支払手段(まえばらいしき・しはらいしゅだん)」として規制対象となる可能性があるため、注意が必要です。
※前払式支払手段について詳しく知りたい方は、「アプリ内課金を導入する際に知りたい!資金決済法4つのポイントとは」や「ポイントサービスを始める方は必読!資金決済法3つのポイントを解説」をご覧ください。
(3)仮想通貨交換業の登録申請方法
自社で発行・販売しようとするものが「仮想通貨」にあたる場合、「仮想通貨交換業」の登録をうける必要があります。
登録申請の流れをおおまかに表したのが下の図です。

【ステップ①】
すでに解説したとおり、まずは自分たちが販売しようとするものが「仮想通貨」にあたるのか→自分たちの行為が「仮想通貨交換業」にあたるのか、を確認します。この時点で、販売するものが「仮想通貨」にあたらない=自分たちの行為が「仮想通貨交換業」にあたらない、と判明した場合には、仮想通貨交換業の登録をする必要はありません。
【ステップ②】
次に、仮想通貨交換業の登録に必要な要件を備えているかを確認します。仮想通貨交換業の登録は申請さえすれば誰でも受けられるわけではなく、細かい要件をすべてクリアする必要があるのです。
具体的な申請要件は以下のとおりです。
- 組織的な要件
- 財産的な要件
- 業務遂行に関する要件(社内体制)
- 法令遵守に関する要件(社内体制)
- 商号についての要件
- 他事業についての要件
これらをみたさない限り、申請しても登録を受けることはできません。
【ステップ③】
上記申請要件をみたしていることを確認したら、登録の申請手続きに入ります。手続きは、
- 事前相談・事前審査
- 本申請
というように、2段階に分かれています。
申請手続きでは、大量の書類の準備や金融庁の担当者との面談に加え、色々な社内規定の策定など、やることがかなりたくさんあります。
さらに、現時点において仮想通貨交換業の登録申請数は100社以上にのぼり、処理が追いついていない状態にあるため、登録が認められるまで8~12ヶ月ほどかかってしまいます。
そのため、登録申請をする場合は時間に余裕をもって事前準備・申請をすることをおすすめします。
【ステップ④】
本申請の内容に問題がなければ、仮想通貨交換業の登録をうけることができます。
以上が仮想通貨交換業の登録申請の流れです。
さらに詳しく知りたい方は、「仮想通貨交換業の登録方法は?申請の要件や4つの手順を弁護士が解説」をご覧ください。
3 規制その②:金融庁の認可を得ること

仮想通貨交換業の登録をうけた事業者であれば、国内で仮想通貨を販売することができます。もっとも、事業者は、仮想通貨であれば何でも売っていいということではありません。この点につき、金融庁のガイドラインでは以下のように述べられています。
取り扱おうとするものが仮想通貨に該当し、または当該仮想通貨の取扱いが仮想通貨交換業に係る取引に形式的に該当するとしても、利用者保護ないし公益性の観点から、仮想通貨交換業者が取り扱うことが必ずしも適切でないものもあり得る。
これを一言でいえば、「日本で仮想通貨を販売する場合には金融庁の認可が必要だ」ということです。
(1)国内で販売してOKな仮想通貨
国内で販売できる仮想通貨は、金融庁の仮想通貨交換業者登録一覧にある「取り扱う仮想通貨一覧」に載っているもののみです。この仮想通貨一覧のことを通称「ホワイトリスト」といいます。
2019年2月18日時点で国内での販売が認可されている仮想通貨は以下のとおりです。
- ビットコイン(BTC)
- イーサリアム(ETH)
- ビットコインキャッシュ(BCH)
- イーサリアムクラシック(ETC)
- ライトコイン(LTC)
- リップル(XRP)
- モナコイン(MONA)
- フィスココイン(FSCC)
- ネクスコイン(NCXC)
- カイカコイン(CICC)
- カウンターパーティー(XCP)
- ザイフ(ZAIF)
- ビットクリスタル(BCY)
- ストレージコインエックス(SJCX)
- ぺぺキャッシュ(PEPECASH)
- ゼン(ZEN)
- ゼム/ネム(XEM/NEM)
- キャッシュ(QASH)
- リスク(LSK)
- ファクトム(FCT)
- コムサ(CMS)
ここに挙げた仮想通貨については、取引所で新たに取り扱う場合であっても認可を得る必要はありません(もっとも、別途届出は必要となります。)。
言い換えれば、「これ以外の仮想通貨を新たに取り扱いたいのであれば、金融庁にお伺いを立てなければならない」ということです。
(2)金融庁から認可をもらうためには?
新しい仮想通貨の取扱いについて金融庁から認可をもらうためには、仮想通貨交換業者は、「仮想通貨の該当性・適切性についての説明」という書面を提出する必要があります。書面には、以下の内容を記載します。
- 取り扱う仮想通貨
- 仮想通貨該当性
- 仮想通貨の適切性に係る見解
まず、認可の対象が「仮想通貨」であることを大前提とした上で、「仮想通貨の適切性」が審査されます。この審査は、ユーザーが不当に損失をうけるものではないかどうかを判断するもので、利用者保護を図る目的です。適切性の判断においては、以下の要素が考慮されます。
- 仮想通貨の仕組み
- 想定される用途
- 流通状況
- 内在するリスク(バグなど)
金融庁から認可をもらうためにいちばん重要なこととされているのが、この「適切性」についてきちんとした説明ができるかどうかという点です。利用者保護を図ることを目的としている以上、国としても慎重に判断することになります。ですので、十分な資料を用意して、金融庁が納得するような説明をする必要があります。
なお、これらのハードル(審査)を乗り越えられそうにない場合、最初は海外の上場しやすい国で上場するという方法も考えられます。海外の取引所で実績を積むことで、その後日本で認可されやすくなるという傾向にあるからです。
4 小括

日本で新たに仮想通貨を販売したい場合には、①仮想通貨交換業の登録をうけること、②金融庁の認可を得ること、の2つの規制があるということについて解説してきました。もっとも、仮想通貨交換業の登録をうけるには時間も手間もかかることに加え、登録要件自体もかなりハードルが高いです(仮想通貨交換業の登録方法は?申請の要件や4つの手順を弁護士が解説参照)。また、前払式支払手段など、その他の規制にあたるかの検討も必要となってきます。
いずれにせよ、国内で仮想通貨を販売したい場合には、きちんとルールを守ったうえで合法的に行う必要があります。
5 まとめ
ここまでの解説をまとめると以下のとおりです。
- 日本で新たに仮想通貨を販売しようとする場合、①仮想通貨交換業の登録をうけること、②金融庁の認可を得ることの2つの規制がある
- 「仮想通貨交換業」とは、ビットコインなどの仮想通貨を売ったり買ったり、交換したりするサービスのことをいい、仮想通貨交換業を行っている事業者のことを「仮想通貨交換業者」という
- 事業者は、仮想通貨交換業の登録を受ける前に、自分たちが販売しようとしてるものが本当に「仮想通貨」にあたるのかを検討する必要がある
- 「仮想通貨」とはインターネット上でやり取りされる通貨のことをいい、実体をもたず、すべてデータとして管理されるもののことをいう
- 「仮想通貨」にあたるかの判断をする上でポイントとなるのが「不特定性」
- 「仮想通貨交換業」の登録申請の流れは、おおまかに①自社で販売しようとしているものが仮想通貨に当たるかの検討、②登録に必要な要件を備えているかの確認、③登録の申請手続き、④仮想通貨交換業の登録完了の4つに分かれる
- 新しい仮想通貨を取り扱う際に金融庁から認可をもらうためには、「仮想通貨の該当性・適切性」という書面を提出する必要がある
- 上記書面の内容として、①取り扱う仮想通貨、②仮想通貨該当性、③仮想通貨の適切性に係る見解、がある