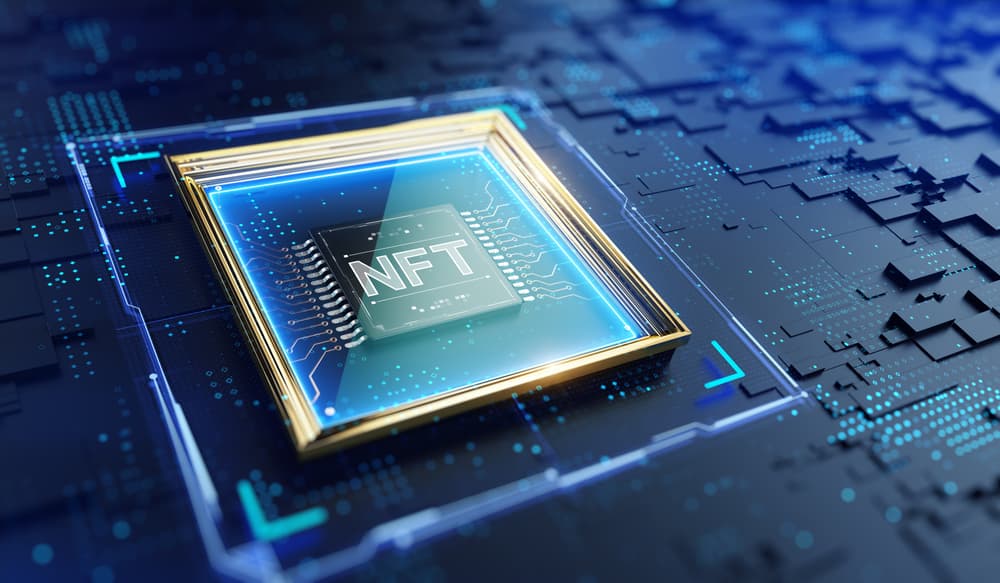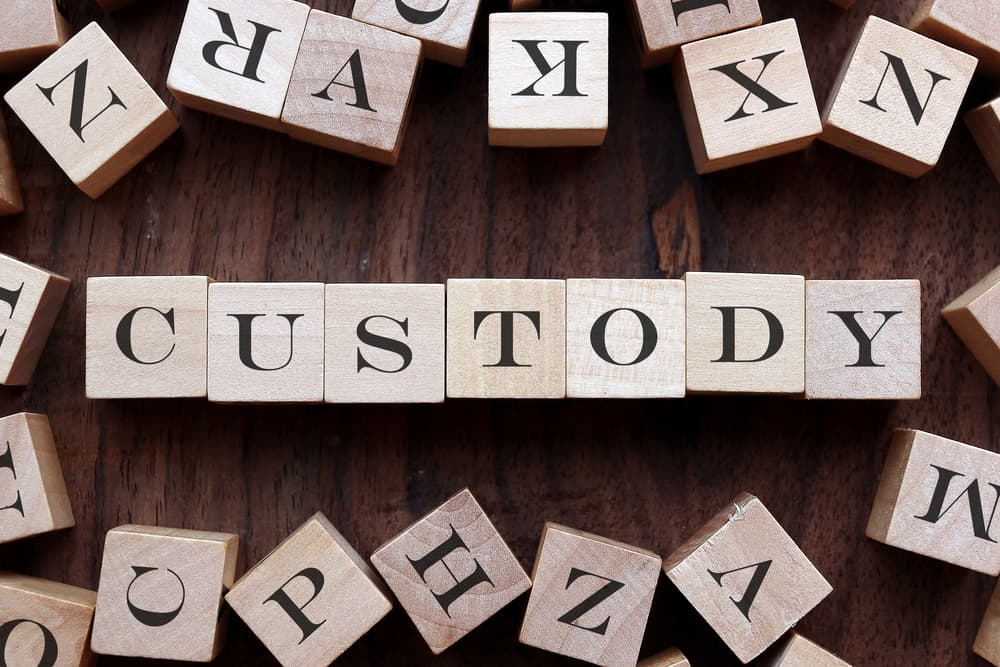はじめに
投機の対象としても注目を集めている暗号資産ですが、一方で、ホットウォレットで管理していた暗号資産が流出するという事例が発生するなど、利用者を保護する必要性が高まっているのも事実です。
利用者保護はもちろんのこと、事業者は、利用者の信頼の確保という観点からも、事業の運営にあたり、さまざまな法規制を遵守する必要があります。
今回は、暗号資産交換業者が遵守すべき法規制を中心に解説します。
1 暗号資産交換業とは
「暗号資産交換業」とは、以下の4つの事業形態のことをいいます。
これらのうち、いずれかにあてはまれば、その事業は暗号資産交換業に該当するということになります。
(1)暗号資産を売買すること、または売買の媒介や取次ぎ、代理を業とすること
暗号資産の売買を内容とする事業は「暗号資産交換業」にあたります。
また、売買の主体でなくとも、売買の媒介や代理を内容とする事業も「暗号資産交換業」にあたります。
(2)暗号資産を交換すること、または交換の媒介や取次ぎ、代理を業とすること
暗号資産の交換を内容とする事業は「暗号資産交換業」にあたります。
また、売買と同様、交換の主体でなくとも、交換の媒介や代理を内容とする事業も「暗号資産交換業」にあたります。
(3)暗号資産の交換等に関して、利用者の金銭を管理すること
上記(1)と(2)を行うにあたり、利用者の金銭管理を内容とする事業は「暗号資産交換業」にあたります。
(4)他人のために暗号資産の管理をすること
暗号資産の売買・交換を行わなくとも、利用者の依頼により利用者指定のアドレスに暗号資産を移転させることを目的として、利用者の暗号資産を管理することを内容とする事業は「暗号資産交換業」にあたります。
これらのうちいずれかにあてはまる事業を行う事業者は、「暗号資産交換業者」ということになります。
2 暗号資産交換業者に対する規制
暗号資産交換業者は、主に、以下の4つの規制を遵守する必要があります。
- 情報の安全管理
- 広告に関する規制
- 利用者保護のための措置
- 利用者財産の管理
3 情報の安全管理
事業者は、暗号資産交換業に係る情報の漏えいや滅失などを防止することを目的として、情報の安全管理のために必要な措置を講じる必要があります。
利用者に関する情報や個人情報については、各種ガイドラインが策定されているため、これらに従って適切に管理することが求められます。
特に、クレジットカード情報を含む個人情報については、情報が漏えいしてしまうと、なりすましなどによる不正使用が発生する可能性が高いため、いっそう厳格に管理することが求められます。
4 広告に関する規制
暗号資産交換業者は、事業に関して広告をする場合は、以下の4つの事項を表示しなければなりません。
- 事業者の商号
- 暗号資産交換業者である旨と登録番号
- 暗号資産が本邦通貨や外国通貨ではないこと
- 暗号資産の性質で利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
「4」については、たとえば、暗号資産の価値変動により利用者に損失が生ずるおそれがある場合にはその旨を表示することが必要だとされています。
また、広告をする場合、これらの事項について明瞭かつ正確に表示する必要があります。
特に、上記「3」と「4」を表示する際の文字・数字は、それ以外の事項の表示に使われている文字・数字のうち最も大きなものと比べ、著しく異ならない大きさで表示することが必要です。
さらに、広告について、虚偽の表示をしたり、暗号資産の性質などについて利用者を誤認させるような表示をしたりすることは禁止されています。
5 利用者保護のための措置
暗号資産交換業者は、利用者との間で暗号資産の交換等を行う場合、事前に書面を交付するなどして、暗号資産の性質を説明しなければなりません。
具体的には、主に、以下の事項を説明する必要があります。
- 暗号資産が本邦通貨や外国通貨ではないこと
- 暗号資産の価値変動により損失が生ずるおそれがあるときは、その旨とその理由
- 暗号資産の概要とその特性
事業者の営業所で利用者と取引をする場合には、これらの事項が利用者の目にとまりやすいように窓口に掲示しなければなりません。
また、事業者の商号・住所や登録番号、取引内容などに係る情報についても、事前に書面を交付するなどの方法で利用者に提供する必要があります。
6 利用者財産の管理
事業者は、利用者の金銭を自社の金銭と分別して管理しなければなりません。
具体的には、利用者の金銭を信託会社などに信託することが必要だとされています。
分別管理については、従来から事業者に義務付けられているものでしたが、改正資金決済法により新たに信託義務が課されることになりました。
また、利用者の暗号資産についても、自社の暗号資産と分別して管理しなければなりません。
この点、暗号資産交換業者に関する内閣府令では、以下のような管理方法が定められています。
-
【事業者が管理する場合】
利用者の暗号資産を移転するために必要な情報を、常時インターネットに接続していない電子機器等に記録して管理する方法
【第三者に管理させる場合】
事業者が管理する場合と同等の利用者の保護が確保されていると合理的に認められる方法
ここでいう「常時インターネットに接続していない電子機器等」は、いわゆるコールドウォレットを指しています。
インターネットに一度でも接続したことがある電子機器等については、「常時インターネットに接続していない電子機器等」にあたらないとされているため、注意が必要です。
7 まとめ
暗号資産交換業者は、業務の性質上、さまざまな規制を課されます。
規制に違反すると、罰則を科される可能性もあるため、事業者は多岐にわたる規制を正確に理解しておく必要があります。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。