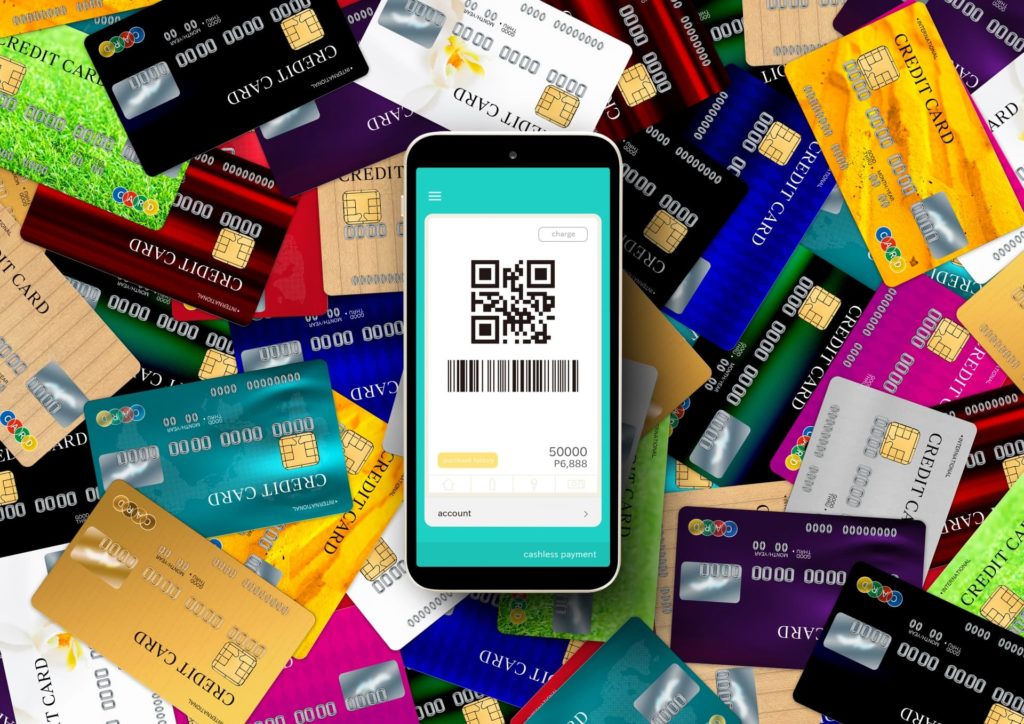はじめに
ベンチャー企業が資金を調達する場合、その方法として、出資や借入れなどが挙げられます。
もっとも、企業の成長フェーズや実績などから、適する方法とそうでない方法があることをご存知でしょうか。
ベンチャー企業において、資金を効果的に調達するためには、それぞれの方法の特徴や他の方法との違い、自社の成長フェーズなどを正確に把握しておくことが必要になってきます。
今回は、ベンチャー企業が資金を調達する場合の方法を中心に解説します。
1 ベンチャー企業における成長フェーズ
ベンチャー企業が資金調達をする場合、その成長フェーズによって向き不向きがあります。
成長フェーズは、一般的に以下の4つに分類することができます。
- 創業前
- 創業初期
- 成長期
- IPO(株式公開)前
このように、成長フェーズは大別して4つに分かれており、各フェーズで実施される資金調達のことを「資金調達ラウンド」と呼ぶこともあります(投資家は「投資ラウンド」と呼びます)。
2 創業前|シードラウンド
創業前に資金調達をする場合、次のような方法が挙げられます。
- 預貯金の切り崩し
- 親族や知人による支援
- エンジェル(個人投資家)による投資
- 融資
このように、創業前における資金調達の方法は複数存在します。
従来、実績のない創業前のフェーズにおいて、融資による資金調達はあまり見受けられませんでした。
ですが、現在では創業支援を目的とした融資制度もあるため、選択肢の一つとして検討することも可能です。
また、クラウドファンディングにより資金調達を実施することも考えられます。
3 創業初期|アーリーラウンド
創業初期に資金調達をする場合、次のような方法が挙げられます。
(1)出資
創業初期に資金調達方法としてよく使われるのが、VCから出資を受けるという方法です。
「VC(ベンチャーキャピタル)」とは、IPOなどによるキャピタルゲインを得るために、企業にエクイティで投資する事業者のことをいいます。
出資は、借入れとは異なり、事業者は返済する義務を負いません。
そのため、定期的なキャッシュアウトフローが発生しないというメリットがあります。
もっとも、出資の比率によっては、会社経営をコントロールされるおそれもあるため、注意が必要です。
また、VCのほかにも、エンジェルやCVCから出資を受ける方法もあります。
ここでいう「CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)」とは、自己資金でファンドを組成し、ベンチャー企業に投資を行う事業者のことをいいます
(2)融資
融資により資金調達をする場合、主な借入先としては、以下の3つが挙げられます。
- 銀行
- 公的機関
- 地方自治体
従来、銀行から融資を受ける際には、経営者保証を求められることが一般的でした。中小企業の場合は特にその傾向が強かったといえます。
ですが、融資額は小さくないことから、経営者が個人保証をするとそこにさまざまなリスクが伴います。
このようなリスクが事業活動の障害ともなっていたため、日本商工会議所や全国銀行協会は2013年に「経営者保証に関するガイドライン」を公表しています。
ガイドラインによれば、融資を受ける主債務者が中小企業である場合において、一定の条件を満たす場合には、経営者保証をつけずに融資を受けられる可能性があります。
銀行のほかにも、公的機関である日本政策金融公庫は、先に見た「創業支援を目的とした融資制度」を設けており、地方自治体によっては、地域活性化を目的として、ベンチャー企業への融資を実施しているところもあります。
※「経営者保証ガイドライン」について詳しく知りたい方は、「「経営者保証に関するガイドライン」の4つのポイントを弁護士が解説」をご覧ください。
4 成長期|シリーズA~Bラウンド
成長期になると、企業の売上げは上昇していきますが、すぐに現金が企業に入ってくるわけではありません。
そのため、成長期にある事業者は、資金が不足することのないよう、資金調達を行う必要があります。
成長期における資金調達方法も、基本的には、創業初期の方法と変わりません。
もっとも、成長期においては、銀行との信頼関係を構築することも大切になってきます。
事業を展開していく過程では、資金が必要になる場面が少なくないため、そのような場合に機動的に資金調達できる体制を整備しておくことが必要です。
たとえば、融資を受けたお金を遅れずにきちんと返済していくことにより、自ずと銀行から信用を得ることができます。
また、メインバンクのみに頼るのではなく、複数の銀行と取引をすることでリスクを分散するという視点も大切です。
銀行のほか、VCなどの投資会社から出資を受ける方法もあります。
5 IPO(株式公開)前|シリーズCラウンド
IPO(株式公開)前のフェーズに入ると、経営状態も安定し、企業としての経済的基盤もある程度確立します。
そのため、これまでのフェーズよりは資金調達のハードルが低くなり、事業者は、調達に要するコストや返済条件などを考慮したうえで、自社に適した方法を選ぶことができます。
もっとも、銀行から多額の融資を受ける場合には、注意が必要です。
比較的簡単に融資を受けられるフェーズですが、仮に業績が低迷した場合、倒産リスクが一気に高まることになります。
そのため、融資により資金調達をする場合は、自社の業種などに応じて、適切に活用することが重要になってきます。
6 まとめ
ベンチャー企業が資金調達を実施する場合には、その方法としていくつかの選択肢があります。
資金調達方法を検討する際は、自社の成長フェーズを把握したうえで、それぞれの方法に存在するリスクなどをきちんと洗い出して精査することが大切です。
弊所は、VCからの資金調達に関する支援業務も行っています。ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。