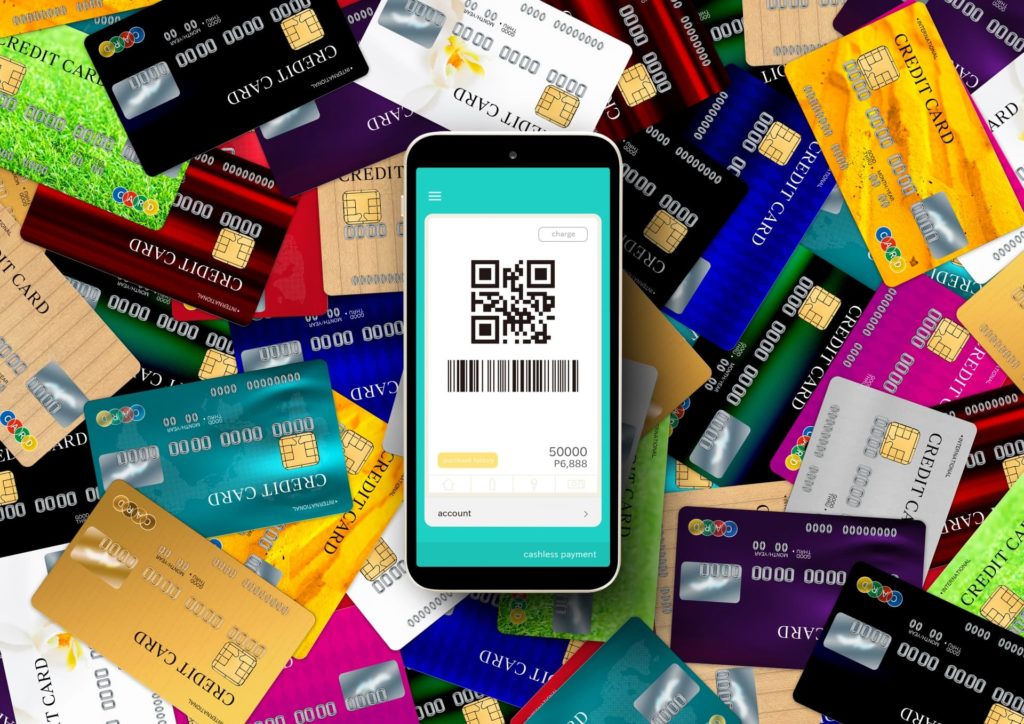はじめに
サービスを開始する際には、法令をチェックするなどして、サービス内容に問題がないか、法令に抵触していないかなどを確認する必要があります。
一般的に、多くのサービスではお金を扱います。
そのため、サービスの仕組みなどによっては、「資金決済法」という法律を確認することが必要になります。
とはいえ、資金決済法が何を規制する法律なのかを知らないと、どのように確認していけば良いかわからないですよね。
そこで今回は、資金決済法がどのような法律なのか、その概要を中心に、弁護士がわかりやすく解説します。
1 資金決済法とは
「資金決済法」とは、金銭の決済に関する事業を対象として、さまざまなルールを定めた法律です。
具体的には、以下の4つの事業を規制しています。
- 前払式支払手段発行業
- 資金移動業
- 暗号資産(仮想通貨)交換業
- 資金清算業
以下では、資金清算を除く3つの事業について、資金決済法がどのような規制内容を設けているかを見ていきたいと思います。
2 各種事業における規制
(1)前払式支払手段発行業
「前払式支払手段」とは、以下の4つの要件をすべて満たすものをいいます。
- 財産的価値が記載・記録されている
- 財産的価値に応じた対価が支払われている
- 財産的価値と結びついて発行されている
- 商品・サービスなどの支払いに使用できる
たとえば、ゲーム内で使用できるコインやポイント、日常的に使用している人も多い交通系電子マネーなどは、前払式支払手段にあたります。
前払式支払手段を発行する事業者は、主に以下のような規制を課されることになります。
①情報の提供義務
前払式支払手段を発行する事業者は、以下の情報を利用者に提供しなければなりません。
- 事業者の名称
- 前払式支払手段の支払可能金額
- 前払式支払手段の使用期間があるときは、その期間・期限
- 利用者からの苦情・相談を受け付ける営業所等の所在地・連絡先
自社のウェブサイトに掲載したり、発行する前払式支払手段の裏面に記載するなど、適切な方法で利用者に提供する必要があります。
そうすることで、前払式支払手段に関してトラブルが生じた場合も、利用者はスムーズに問い合わせ等の対応を行うことができます。
②発行保証金の供託義務
「発行保証金」とは、発行する前払式支払手段の残高に応じて、事業者が保全しておかなければならない資産のことをいいます。
事業者が、倒産などによりサービスを終了した場合に、前払式支払手段を保有している利用者に迅速に払戻しができるように、事業者に義務付けられているものです。
具体的には、毎年3月末もしくは9月末の時点で、前払式支払手段の未使用残高が1,000万円を超えている場合には、その半額(最低保全額:500万円)を法務局などに供託する必要があります。
※前払式支払手段発行者に課される供託義務やその回避スキームについて詳しく知りたい方は、「資金決済法の供託金って?支払義務の回避方法2つを弁護士が徹底解説」をご覧ください。
(2)資金移動業
「資金移動業」とは、銀行等以外の事業者が為替取引(現金以外の方法で金銭を決済する取引)を行うことを業とすることをいいます。
取り扱うことができる送金額に応じて、資金移動業は第1種~第3種の3つの類型に区分されています。
資金移動業を営むためには、資金移動業者として登録を受けることが必要です。
もっとも、一定の財産的基礎があることが必要になるなど、資金移動業の登録要件は厳しいものになっています。
さらに、登録を受けた後も、以下のような規制を課されることになります。
①履行保証金の供託等
送金途中で滞留している資金の全額以上の額(最低履行保証金:1,000万円)を「履行保証金」として保全することが義務付けられます。
保全方法には、供託のほか、銀行との保全契約や信託会社との信託契約による方法があります。
資金移動業者が倒産した場合も、送金すべき資金を全額送金できるように、このような規制が事業者に課されています。
②利用者保護のための措置
資金移動業者は、利用者保護のために、一定の措置を講じることが義務付けられます。
たとえば、利用者において銀行等が行う為替取引と誤認しないような措置をとること、契約内容に関する情報を利用者に対し提供すること、社内規則などに基づき従業者に研修を行うことなどが挙げられます。
※資金移動業の3つの類型について詳しく知りたい方は、「PayPayマネーの残高上限額が変更!背景にある資金移動業の改正」をご覧ください。
(3)暗号資産(仮想通貨)交換業
「暗号資産(仮想通貨)交換業」とは、以下のいずれかを業として行うことをいいます。
- 暗号資産の売買または他の暗号資産との交換
- 「1」の媒介・取次または代理
- 「1」「2」に関して、利用者の金銭を管理すること
- 他人のために暗号資産を管理すること
暗号資産交換業についても、登録要件は厳しい内容になっています。
具体的には、一定の財産的基礎(資本金額が1,000万円以上)があることに加え、一定の体制が整備されていることが必要になります。
また、登録を受けた後も、以下のようにさまざまな規制を課されます。
①行為規制
暗号資産交換業者に課される行為規制としては、たとえば、以下のようなものがあります。
- 情報の安全管理義務
- 利用者の保護等に関する措置
- 利用者財産の管理義務
主に、利用者の情報や財産を管理・保護するために、事業者に課されるのが行為規制です。
※行為規制について詳しく知りたい方は、「仮想通貨交換業の法律規制とは?改正資金決済法を弁護士が5分で解説」をご覧ください。
②監督規制
暗号資産交換業者に課される監督規制としては、たとえば、以下のようなものがあります。
- 帳簿書類の作成・保存義務
- 報告書の提出義務
- 立入検査等
このほかにも、一定の場合には、監督行為の一環として、業務改善命令や登録の取消・抹消等を受ける可能性があります。
※監督規制について詳しく知りたい方は、「仮想通貨交換業の法律規制とは?改正資金決済法を弁護士が5分で解説」をご覧ください。
3 資金決済法に違反した場合の罰則
資金決済法では、各事業における規制が細かく定められています。
これらの規制に違反した場合、事業者は罰則を科される可能性があります。
(1)前払式支払手段発行業
事業者が情報提供義務に違反した場合、
- 最大30万円の罰金
を科される可能性があります。
また、供託義務に違反した場合には、
- 最大6ヶ月の懲役
- 最大50万円の罰金
のいずれか、または両方を科される可能性があります。
さらに、法人の場合は、違反行為者とは別に法人に対しても、
- 最大1億円の罰金
が科される可能性があります。
(2)資金移動業
登録を受けずに資金移動業を行った場合、
- 最大3年の懲役
- 最大300万円の罰金
のいずれか、または両方を科される可能性があります。
法人の場合は、違反行為者とは別に法人に対しても、
- 最大3億円の罰金
が科される可能性があります。
また、履行保証金の供託等に違反した場合、
- 最大1年の懲役
- 最大300万円の罰金
のいずれか、または両方を科される可能性があります。
(3)暗号資産(仮想通貨)交換業
登録を受けずに暗号資産交換業を行った場合、
- 最大3年の懲役
- 最大300万円の罰金
のいずれか、または両方を科される可能性があります。
法人の場合は、違反行為者とは別に法人に対しても、
- 最大300万円の罰金
が科される可能性があります。
また、利用者財産の管理義務に違反した場合は、
- 最大2年の懲役
- 最大300万円の罰金
のいずれか、または両方を科される可能性があります。
法人の場合は、違反行為者とは別に法人に対しても、
- 最大3億円の罰金
が科される可能性があります。
4 まとめ
前払式支払手段や為替取引、暗号資産を取り扱う場合には、必ず資金決済法による規制を確認しておく必要があります。
各事業に課される規制のなかには、罰則が設けられているものもあるため、注意するようにしましょう。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。