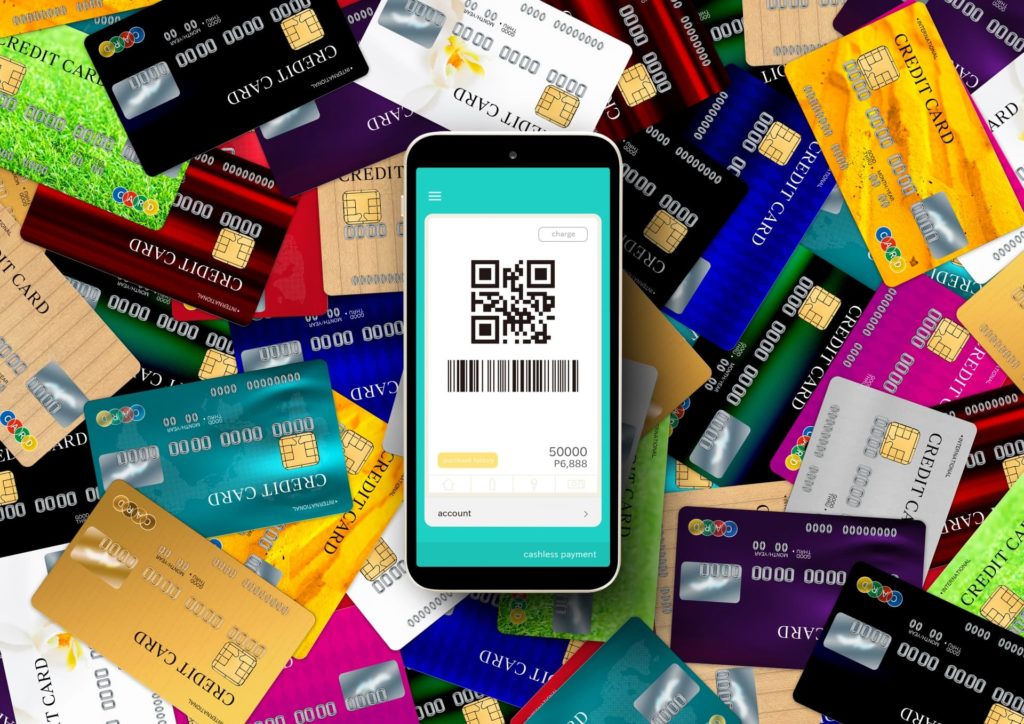はじめに
2021年5月7日、「クレジットエンジン株式会社」が、債権管理回収システム「CE Servicing」の提供を開始すると公表しました。
オンラインレンディングプラットフォーム「CE Online Lending Platform」を提供するクレジットエンジン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:内山 誓一郎、以下 クレジットエンジン)は、金融機関や事業会社、弁護士事務所向けに債権管理回収システム『CE Servicing』の提供を、本日5月7日より開始することをお知らせします。
PR TIMESより
債権を有する事業者は、その支払期日や支払額、支払いの有無などをきちんと管理する必要があります。
また、期限を過ぎても支払いを受けられないケースが想定されるため、事業者は、債権を回収するためのフローを確立しておくことも必要になってくるでしょう。
今回は、債権を回収するためのフローを中心に、クレジットエンジン社が提供する「CE Servicing」のサービス内容にも触れながら解説していきたいと思います。
1 債権回収のフロー
債権を回収しようとする場合、以下のような流れで回収を図ることが一般的です。
- 電話・メールによる請求
- 内容証明郵便等による請求
- 訴訟(支払督促)による請求
- 強制執行
↓
↓
↓
(1)電話・メールによる請求
まずは、電話やメールで未払債権の支払いを請求します。
支払いを失念しているケースもあるため、この段階で支払いを受けられる場合もあります。
感情的になって、いきなり弁護士の名前で内容証明郵便を送ったり、訴訟等を提起したりすると、取引先との関係性やそれ以降の取引に悪影響を及ぼす可能性もあるため、注意が必要です。
(2)内容証明郵便等による請求
電話やメールで請求をしたにもかかわらず、請求に応じない場合は、内容証明郵便などの書面で支払いを請求します。
ここでいう「内容証明郵便」とは、書面の名宛人と差出人、書面に記載されている内容、書面が送られた日にちなどを郵便局が証明してくれるものです。
内容証明郵便は、相手方に対し心理的プレッシャーを与えることができ、後に裁判になった場合の証拠にもなるため、広く一般的に利用されています。
(3)訴訟(支払督促)による請求
内容証明郵便等の書面で請求しても、請求に応じない場合は、訴訟を提起します。
訴訟を提起する際には、請求額や請求原因などを記載した訴状を作成し、証拠などとともに裁判所に提出します。
また、取引先において財産を処分するおそれがあるような場合には、訴訟提起前もしくは訴訟提起と同時に保全手続きを行うこともあります。
そうすることで、取引先が財産を勝手に処分することを防ぐことができるのです。
(4)強制執行
訴訟を提起すると、最終的には、和解で終結するか、もしくは、判決を言い渡される形で裁判は終結します。
もっとも、和解が成立したり、勝訴判決が出たりした場合であっても、支払いが100%保証されているわけではありません。
このような事態になっても、請求に応じないケースもあります。
その場合、訴訟により得られた和解調書や確定判決を基に、強制執行手続きに踏み切ることを検討する必要があります。
「強制執行」とは、和解調書や確定判決などの債務名義に基づき、国が強制的に債権回収を実現してくれる制度です。
強制執行の対象となるのは、不動産や預貯金口座といった債務者名義の財産です。
2 債権を回収する場合の注意点
債権を回収する場合、主に以下の2点に注意する必要があります。
(1)時効期間
債権は、一定の期間が経過すると時効により消滅し、それ以降、支払いを請求できなくなります。そのため、回収を行おうとする債権が時効にかかっていないかを確認する必要があります。
時効期間については、基本的に民法の規定によることとなります。
-
【民法166条1項】
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
時効の成立が迫っている場合には、早急に手を打つ必要があるため、注意が必要です。
(2)資産状況
債権を回収しようとする場合は、強制執行による回収までを見据えておく必要があります。
そのため、相手方の資産状況を調査しておくことは必須です。
裁判により勝訴判決を得ても、相手方に資産がなければ、手詰まりとなってしまうため、あらかじめ資産状況を把握しておくことが必要になるのです。
3 「CE Servicing」のサービス概要
「CE Servicing」は、テクノロジーを活用した債権管理回収システムです。
搭載されたさまざまな機能により、債権管理業務の効率化を図ることができます。
先に見たように、債権管理業務は相手方の数に応じて煩雑化するため、そこに多くの人員を割かなければならないということも実際にあります。
「CE Servicing」は、債権に関する管理業務や回収業務をオートメーション化することで、人的コストや管理コストの削減を可能にしたシステムです。
また、AIを使った機械学習により蓄積されたデータを基に、債権回収率の向上を図ることができるようになっています。
「CE Servicing」は、クレジットエンジン社のグループ会社であるLENDY債権回収株式会社にて、利用を開始し、今後は金融機関をはじめ、法律事務所やサービサー(債権回収会社)への提供が予定されています。
事業者によっては、多くの債権を抱えていて、管理業務の効率化が一つの課題になっているところもあると思います。
債権には時効もあるため、「CE Servicing」のようなサービスを導入し、管理業務の効率化を図ることも選択肢の一つといえるのではないでしょうか。
4 まとめ
未回収の債権を多く抱えることは、事業者にとっても大きな損失です。
今回は、一般的な債権回収フローを見てきましたが、フローにあてはめて機械的に進めていくのではなく、相手方との関係性やそれまでの実績などを考慮したうえで、柔軟に対応することも大切です。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。