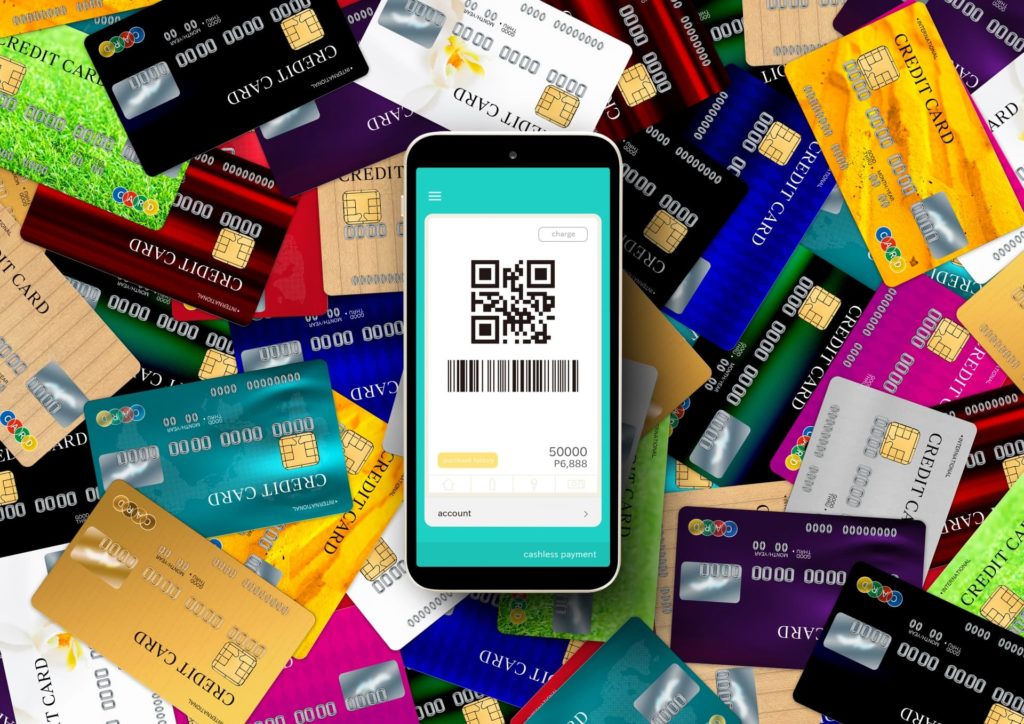はじめに
FinTech(フィンテック)サービスが増えてきている昨今、利用者にとってより便利となるサービスが今後も出てくると考えられます。
これからFinTechサービスを開始しようと検討している事業者もいらっしゃると思いますが、そのときに必ず押さえておかなければならないのが「資金決済法」という法律です。
資金決済法は「前払式支払手段」や「資金移動業」を規制する法律ですが、それぞれの該当性を判断しなければならない局面に立たされるケースもあります。
みなさんは、そもそも両者の違いを正確に理解していますでしょうか。
自社サービスがどちらにあたるかで、遵守しなければならない規制の内容も変わってきます。
今回は、前払式支払手段と資金移動業の違いについて、弁護士がわかりやすく解説します。
1 前払式支払手段とは
「前払式支払手段」とは、以下の3つの要件をすべて満たすものをいいます。
- 金額やサービスの数量が記載・記録されていること
- 記載・記録されている金額やサービスの数量に応ずる対価が支払われていること
- 物品を購入するときやサービスの提供を受けるときに、代価の支払いに使用できること
たとえば、交通系電子マネー(SuicaやPASMOなど)や商品券、IC型のプリペイドカードは「前払式支払手段」にあたります。
(1)前払式支払手段における2つの種類
前払式支払手段は、さらに、「自家型前払式支払手段」と「第三者型前払式支払手段」の2種類に分類されます。
①自家型前払式支払手段
「自家型前払式支払手段」とは、前払式支払手段発行者との間でのみ代価の支払いに使用することのできる前払式支払手段のことをいいます。
たとえば、発行者との間でのみ使用できる商品券や、ゲーム内でのみ使用できるコインやポイントなどが挙げられます。
②第三者型前払式支払手段
「第三者型前払式支払手段」とは、発行者だけでなく他の事業者との間でも使用できる前払式支払手段のことをいいます。
たとえば、交通系電子マネーや加盟店の全店舗において使用できる商品券などが挙げられます。
以上のように、前払式支払手段には2つの種類がありますが、前払式支払手段に該当する場合であっても、資金決済法による規制を受けないケースがあります。
たとえば、6ヶ月以内の使用期間が設けられている前払式支払手段、入場券や乗車券などは、資金決済法による規制の適用が除外されているため、以下で見るような規制が課されることはありません。
(2)前払式支払手段発行者への規制
自家型前払式支払手段については、特に登録などを受けずに発行することが可能です。
もっとも、基準日(毎年3月末もしくは9月末)において未使用残高が1000万円を超えた場合、財務局長への届出が必要となります。
これに対し、第三者型前払式支払手段については、発行前に財務局長の登録を受けることが必要です。
また、自家型か第三者型であるかを問わず、前払式支払手段を発行する事業者には以下のような規制が課されます。
- 情報提供義務
- 表示義務
- 資産保全義務
特に「資産保全義務」は事業者にとって負担が重く、経済的基盤がしっかりしていない事業者などにとっては、大変厳しいものといえます。
※「資産保全義務」の詳細、資産保全義務を回避する方法について詳しく知りたい方は、「資金決済法の供託金とは?支払義務の回避方法2つを弁護士が徹底解説」をご覧ください。
2 資金移動業とは
「資金移動業」とは、銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいいます。
ここでいう「為替取引」とは、現金以外の方法で資金を移動する取引のことをいい、身近なところでいえば、「銀行振込」が為替取引にあたります。
(1)資金移動業における3つの種類
従来、資金移動業に類型は設けられていませんでしたが、2021年5月に改正資金決済法が施行されたことにより、以下の3つの類型が設けられました。
- 第1種資金移動業
- 第2種資金移動業
- 第3種資金移動業
これらは、主に、取引において取り扱うことのできる金額に違いがあります。
※資金移動業の類型について詳しく知りたい方は、「PayPayマネーの残高上限額が変更!背景にある資金移動業の改正」をご覧ください。
(2)資金移動業への規制
資金移動業を行うためには、財務局長の登録が必要となります。
登録を受けるためには、以下の要件を満たしていることが必要です。
- 株式会社または外国資金移動業者(国内に営業所があることが必要)であること
- 一定の財産的基盤があること
- 体制が整備されていること
- 他の資金移動業者と同一・類似の商号や名称を使用していないこと
これらのうち一つでも満たさない要件がある場合、登録を受けることはできません。
また、登録を受けた後も以下のような規制を課されることになります。
- 履行保証金の保全
- 情報の安全管理
- 委託先への指導
- 銀行等が行う為替取引との誤認防止のための措置
- 利用者保護のための措置
このほかにも、金融ADR制度に対応するために一定の措置を講じる必要があり、また、報告書を作成し定期的に金融庁に提出することが義務付けられます。
※資金移動業の登録要件や登録後の規制について詳しく知りたい方は、「資金移動業の登録に必要な4つの条件とは?登録後の規制とともに解説」をご覧ください。
3 まとめ
前払式支払手段と資金移動業は、一見似ているように思うかもしれませんが、両者はまったく異なります。
それぞれには、違った規制が設けられているため、求められる準備や対応も異なってきます。
該当性等の判断が難しい場合は、専門家に相談することをおすすめします。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。