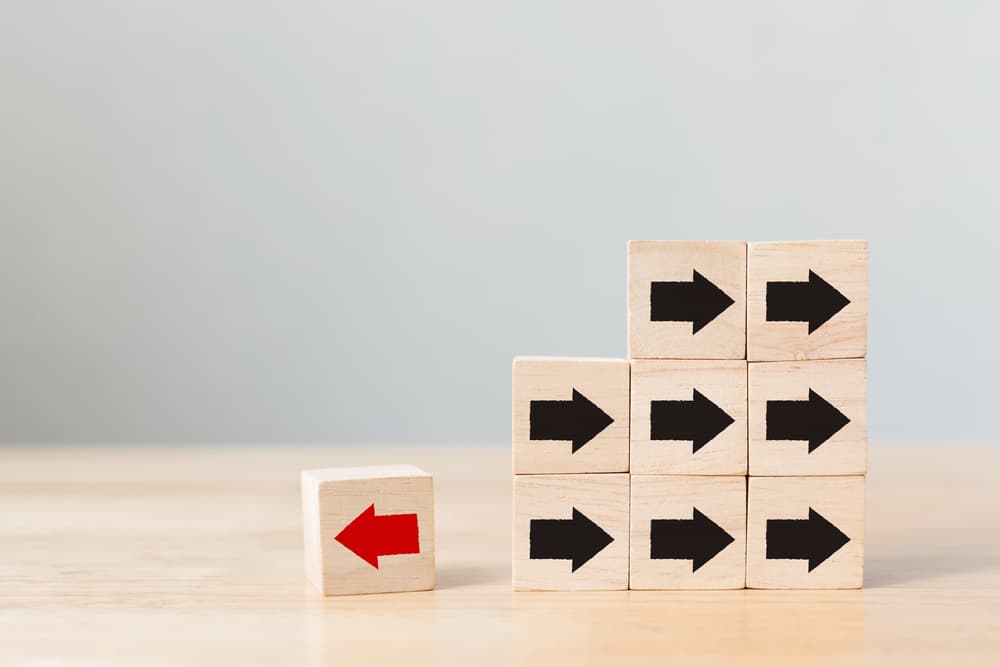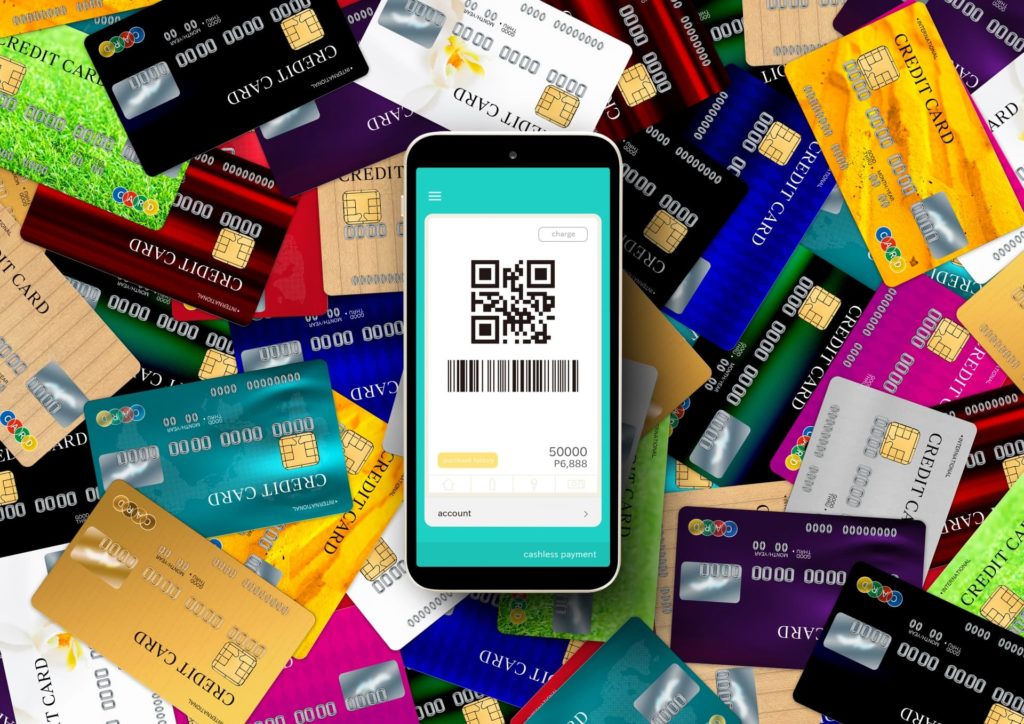はじめに
資金調達の方法として、「社債」もしくは「株式」を発行する方法がありますが、この両者について、どのような違いがあるかをご存知でしょうか。
両者はまったく異なるものであり、それぞれには独自のメリット・デメリットもあります。
そのため、資金調達をしようとする事業者は、その点も十分に考慮したうえで、自社に適する方法を選択することが必要になってきます。
今回は、社債と株式について、その違いを中心に弁護士がわかりやすく解説します。
1 社債と株式の違い
事業者側から見ると、社債発行により調達した資金と株式発行により調達した資金とでは、その性質において大きな違いがあります。
「社債」と「株式」を大まかに説明すると、以下のようになります。
- 「社債」の発行:お金を貸してくれる人を募る
- 「株式」の発行:お金を出資してくれる人を募る
つまり、事業者にとって、社債を発行して調達したお金は「借金」そのものであり、株式を発行して調達したお金は「資本」ということになります。
そのため、社債を発行した場合、事業者はその返還期限を迎えると、元本や利息を支払わなければなりません。
これに対し、 株式には当然ながら社債のような返還期限は設けられておらず、事業者が元本・利息について、返済義務を負うということもありません。
また、社債とは異なり、株式を購入して株主になった者は、事業者の経営に参加したり、事業者の経営を監督したりすることができるようになります。
このように、社債と株式とでは、調達したお金の性質や資金を提供した投資家の立場という点において大きな違いがあるのです。
2 社債を発行するメリット・デメリット
(1)メリット
社債を発行するメリットとしては、主に以下の2点が挙げられます。
①償還日まで元本を返済する必要がない
社債は、満期になるまでは利息を支払うだけでよく元本を返済する必要はありません。
たとえば、銀行から融資を受けた場合、月々の返済が負担となり資金繰りがなかなか安定しないということがあります。
ですが、社債の場合、償還日までは利息のみの支払いで済むため、満期までにしっかりとした返済計画を立てることで、資金繰りを安定させることが可能です。
②投資家が経営に関与することがない
社債は、事業者が投資家からお金を借りているだけのことです。
そのため、投資家は返済に関する意見を述べることはできても、事業者の経営自体に口出しすることはできません。
できるだけ経営に関与されたくないという事業者は、株式ではなく社債を発行する方法で資金調達をする方が適しているといえます。
(2)デメリット
社債を発行するデメリットとしては、主に以下の3点が挙げられます。
①借金である
社債はあくまでも借金であるため、満期になったら必ず返済しなければなりません。
また、銀行から融資を受けた場合、返済が困難になるとリスケに応じてくれることがありますが、社債の場合、基本的にリスケすることはできません。
そのため、返済計画をしっかりと立てておくことが必要になります。
さらに、発行した社債は財務上負債として計上されるため、銀行等の金融機関から別途融資を受けようと考えている場合には、負債総額によっては審査で落とされる可能性もあります。
②コストがかかる
社債を発行する場合、会社法上、社債管理者の設置が義務づけられています。
ここでいう「社債管理者」とは、社債権者のために、弁済の受領や債権の保全などを行う者のことをいいます。
社債管理者は、銀行や信託銀行など一定の事業者しか就任できないこととされているため、社債を発行する事業者はこれらの社債管理者に管理業務を依頼する必要があります。
この場合、一定の手数料を負担しなければなりません。
③発行手続きが複雑である
社債は、簡単に発行できるものではありません。
会社法が定める要件や手続きに則って、発行することが必要であり、手続き自体も複雑なものになっています。
3 株式を発行するメリット・デメリット
(1)メリット
株式を発行する一番のメリットは、なんといっても、返済義務を負わずに資金を調達できるということにあるでしょう。
また、株式を発行して調達した資金は、貸借対照表では「資本」として扱われるため、新たに金融機関から融資を受ける際にもプラスに働きます。
(2)デメリット
既に見たように、株式を購入した株主は、事業者の経営に参加できるようになります。
そのため、場合によっては、株主である第三者に経営権を握られてしまうリスクがあります。
株式会社では、株式を多く保有すればするほど、経営に関する発言権も大きな影響力をもつことになります。
たとえ多くの資金を調達できたとしても、株主の意向に沿わないような経営方針を打ち出していると、会社の経営権を失うことにもなりかねないため、注意する必要があります。
新株を発行する場合には、持株比率などを十分に考慮するなどして、既存株主とのバランスにも配慮することが必要です。
4 まとめ
社債と株式がまったくの別物であるということをご理解いただけたでしょうか。
両者を比較検討する際には、「返済義務の有無」「経営参加の可否」など、押さえておくべきポイントがあります。
これらのポイントをきちんと理解したうえで、自社に適した方法を選択するようにしましょう。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。